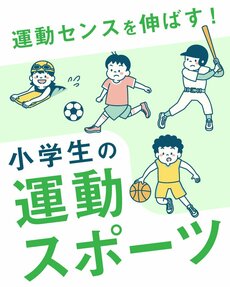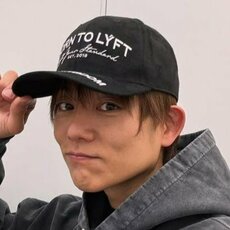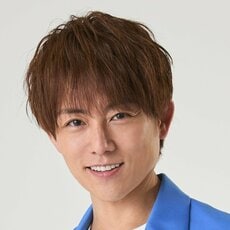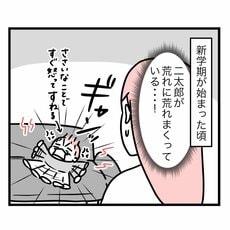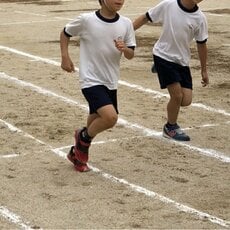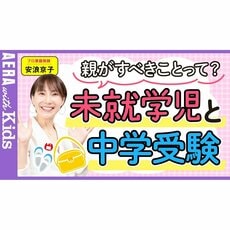矢萩:何でもいいよ、全部受け入れるよ、というスタンスは確かに大事なんですけど、やったらやっただけ成長する、という体験も大事です。やりたいことだけやらせて、評価もなく、成長を感じさせるような体験もあまりなく、何でも受け入れる方向に全振りしてしまうと、その環境から卒業できなくなって、一条校に戻れなかったり、社会に適合できなかったりという可能性もあるんです。そのような問題が今、一部のフリースクールやオルタナティブスクールでは認知され始めています。少し話が逸れましたが、なんとなくこのご相談から少し繋がるものを感じたので。
■○も×もつけないで「どうやって考えたの?」と尋ねる
安浪:すごく大切な話だと思うので、ぜひ別の機会でお話したいです。マルバツの話に戻しますと、たとえ星やハートにしても、そこがバツだ、ってわかるじゃないですか。それも嫌ならマルもバツもつけないで、マルやバツに関わらず「どうやって考えたの?」って聞かれてはどうでしょうか。実際、私の授業でもそうすることが多いです。
矢萩:それはいいと思います。「どうやって考えたの?」みたいな対話ってやっぱり大事です。「定量評価」と「定性評価」という言葉があるんですが、「定量評価」は10問あったらいくつマルになるかを測るもの。いわゆる点数ですね。それに対して「定性評価」は数値では測れないものを評価することです。例えば、「これはどうやって考えたの?」って聞いたら、ここまでわかったんだね、とか、その考え方はいいね、とか、取り組む姿勢はよかったとかいろいろな評価ができるんですね。そういうふうに一問一問やっていくと、よいところを評価しながら違うところは違うよ、と言って改善していく流れが作れるんです。それがドリルや問題集のような単位だと、構造的に難しくなります。
安浪:そうするとこのご質問者さんの場合、塾という構造的に難しい環境の中でどうすればいいですか?、と聞いていることになりますよね。まだ3年生なら思い切って塾をやめてもいいと思います。塾に行くとどうしても大量の問題をこなさないといけないので。家でやる量を減らして、少しずつリハビリ的にやっていくのもありなのかな、と。
次のページへ○と×には必ず「あいだ」がある