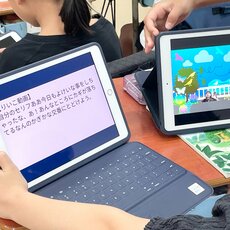消費税には「逆進性」といって、所得が低い人ほど、負担が大きくなる性質が課題として指摘されています。そこで軽減税率を適用し、食材や日用品など、生活に影響の大きいものは8%のままにしたり、商品券などを配ったりして、金銭面でのサポートを国が行う案などが、現在検討されています。
具体的にどのような制度が導入されることになるのか、ぜひみなさんも注目してください。
(※)間接税というのは、税金を国に直接納めるのではなく、スーパーやコンビニなどのお店を通して間接的に納める税金です。
■消費増税は待ったなし!
人口減少・少子高齢化が急速に進み、どんどん増える社会保障費(医療や介護、生活保護などにかかる費用)。例えば国民全体の医療費を見てみると、1989(平成元)年には20兆円弱だったのが、現在では42兆円を超え、平成の間で倍以上に跳ね上がっている。こうした社会保障費を補うという目的で消費税は導入された。
■消費税の「逆進性」とは?
消費税には、所得が低い人たちほど負担が大きくなる「逆進性」という特徴がある。例えば、1万円の商品に10%の消費税がかかって1万1000円を支払う場合、月収が100万円の人と10万円の人とでは、税金分の千円の重みがまったく違う。
そこで、政府は所得が低い人の負担感を軽減するため、「軽減税率」という制度を導入予定。これは例えば、米や野菜、肉など、スーパーなどで買う食材や日用品などに限っては、8%のままにするというものだ。
同じフランスパンでも、イートインは10%、テイクアウトは8%になる。
【今月のポイント】
・増え続ける社会保障費を補うため、日本では1989(平成元)年から消費税が導入された。
・消費税には「逆進性」といって、所得が低い人ほど負担が大きくなるという特徴がある。
・生活に影響の大きい食材等の税率を8%のままにする制度「軽減税率」について、現在は議論の真っただ中。
※月刊ジュニアエラ 2019年1月号より
![ジュニアエラ 2019年 01 月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/619raahqQYL._SL500_.jpg)