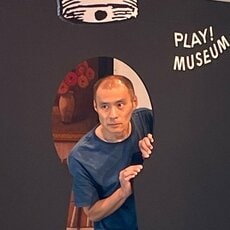歌人・俵万智さんが現代の言葉について論考した著書『生きる言葉』(新潮新書)が話題です。SNSなどで短い言葉のやり取りが増えている今、「言葉の力」は失われているのでしょうか。俵万智さんにじっくりとうかがいました。※前編<俵万智、寮に住む一人息子に6年間毎日ハガキを書いた理由 「書くのはものの数分。“なんでもない言葉”を届けたかった」>から続く
【写真】俵万智さんが寮で暮らす息子に6年間毎日送っていた自筆のハガキ(本人提供)言葉と心は、ひもづいている
――俵さんは「最近の子どもの言葉が乱れている」と感じることはありますか? 「ウザい」「キモい」「ダルい」など、短い言葉で切り捨てるような会話が増えているのではないかと、問題視されることもあります。
いつの時代も「子どもの言葉の乱れが気になる」って言われますよね。気になる言葉は時代によって違いますが、子どもが乱暴な言葉を使いたがるのは今に始まったわけではないと思います。
私の息子は今大学生ですが、小学生くらいの時は乱暴な言葉ばかり使いたがる時期がありました。私も子育ては初心者だったので少しあわてましたけど、よくよく聞いてみると、『ドラえもん』に出てくるジャイアンの強さにあこがれて、マネしたかったみたいです。
「てめえ!」とか「うめえ!」って言うんですが、シューマイのことまで「しゅーめえ!」って。それは違うんじゃないの、って(笑)。
ともあれ子どもって、言葉を変えることで成長した、別な自分になれたような気がするのだと思います。「今はそんな時期なんだな」とひとまず見守るのもいいのではないでしょうか。
――「そんな言い方はやめなさい」とは、言わなくていいですか。
「この言葉はいい、この言葉はダメ」と言葉狩りをするのではなく、大人はいったん立ち止まって、「この言葉は、どんな心とひもづいているんだろう」と考えてみてほしい。単純に悪い言葉を楽しんでいるなら、楽しませてあげればいい。ブームが過ぎれば使わなくなります。
けれど、何か心の問題や悩みや不安とひもづいているなら、真の原因についていっしょに考えていく必要があると思います。言葉のおかげで心の問題にも気づけるわけなので、言葉って本当にありがたいものだなと思います。
次のページへLINEなどのトラブルに備える