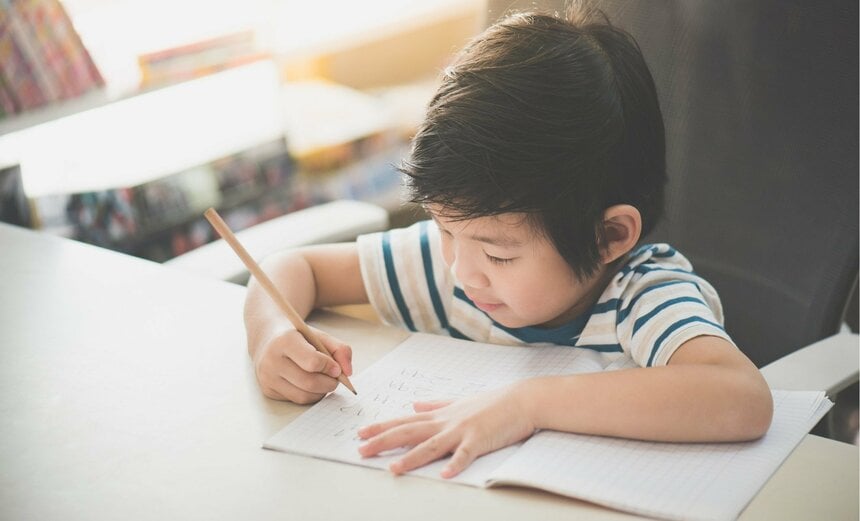1、2年生で自宅学習が身についているかどうかが3年生以降の伸びにつながっているといわれます。一生の財産となる「学習習慣」を身に付けるのに最適なのが低学年。学びを習慣化するにはどうしたらいいのかを現役小学校教諭、アフタースクールに詳しい専門家、教育評論家の3人に教えてもらいました。「AERA with Kids 2025年春号」(朝日新聞出版)からご紹介します。
【図】学びを習慣化する6つのキーワードはこちら学習習慣はキラキラ期の低学年から身に付ける!
「英語、プログラミング……昔はなかったものがたくさん。漢字や計算は当然できないとわが子が心配……」。親は低学年のうちに学習習慣を身につけさせたいと考えるもの。でも子どもの様子を見ていると「難しい!」とも思います。
鎌倉小学校教諭の根本哲弥さんは「低学年はキラキラ期。大好きな親に褒めてほしい強い気持ちのあるうちが学習の土台をつくるチャンスです」と語ります。
「頑張ろうとする心や姿を当たり前とせず、親が勇気づけ、価値づけしていくことが大切です」
教育評論家の石田勝紀さんは「1年生の最初は、友達が家でどう過ごしているか知りません。なかなか学習しない子もいることを知る前に『自宅学習は当たり前』の環境をつくるのがおすすめです」と話します。
家庭での時間をどう使うかも親にとっては悩みどころ。「思い切って、主権を子どもに渡してみて。主権=責任を持つことなので、過ごし方を徐々に考えるようになります」と話すのは新渡戸文化アフタースクールの織畑研さん。
「ただし、時計を見るクセをつけて時間感覚を身につけることが先。1年生の夏休みまでに徹底してみるといいでしょう」(織畑さん)
また、3人が口をそろえるのが「学習習慣づくりは親子で楽しむのがカギ」ということ。頑張りを見える化して、楽しみながら達成感を共有すると良いそう。さらに「家庭は本来、学習の場ではない」とも。子どもが甘えてガス抜きする場であることが大切です。
子どもが予定を決めて見える化すると、時間感覚も身に付く
低学年のうちは、時間通りに行動し始められない子も。学童ではどのように対応しているのでしょうか? 織畑さんに聞きました。
次のページへ時間通りに行動できるようになるのは?