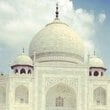インドが、中国を抜いて人口「世界一」になった。急速な経済発展を続け、世界企業のトップにはインド出身者が名を連ねる。その勢いと熱気は高まる一方だ。AERA 2023年8月7日号の記事を紹介する。
* * *
「暮らしは年々良くなっています。相変わらず交通渋滞はあるけど、自宅から徒歩2分のところに地下鉄の駅ができ、とっても便利になりました。幼かった頃に比べると、街も家も格段に美しくなった」
と話すのは、インド南部の都市・ベンガルール(バンガロール)で生まれ育ったモヒタ・ルーイさん(28)。カトリック系の私立の女子高から大学に進学し、電子工学を専攻。マーケティングを学ぶプログラムにも参加し、首席で卒業したという。英会話講師やパソコン事業会社など数回の転職を経て、現在は映像メディア関連企業で働く。
「同じ仕事をしても、米国の本社スタッフは私の10倍の給与をもらっている。インド人の人件費は安すぎる」
とこぼすが、給与は毎年、約10%のペースで上がっているという。週末は同僚や友人たちとレストランで食事を楽しみ、時々、ワインやチーズについて学ぶワークショップに参加。週1度は、趣味のサルサダンスのレッスンに通うのが日常だ。そんなモヒタさんは、こう話す。
「私はインドのアッパーミドルクラス。もっと裕福になって、大きな家で暮らし、世界中を旅したい」
若い世代が、迷うことなく将来の夢を口にできるポジティブな雰囲気が今、インドの国全体を覆っている。それもそのはず、今夏、インドの人口は中国を抜き、14億2860万人で世界1位になった。名目国内総生産(GDP)は世界5位だが、コロナ禍での落ち込みからのV字回復も目覚ましく、ここ数年のうちに日本を追い抜き、世界3位になるとみられている。
GDPの伸び率を支えているのは、2009年からインド政府が進めるデジタル公共インフラ「インディア・スタック」だ。名前、年齢のほか、指紋や瞳の色などの生体情報をデータベース化し、国民一人ひとりに12桁の識別番号を与えるシステムで、23年7月までに農村部にいたるまで9割の国民の登録が完了しているという。
その結果、これまで公的な身分証がなかった貧困層の人たちが銀行口座を開設できたり、就職することができたり、政府の補助金を受け取ることも可能になった。路上の花売りの女性も電子決済を取り入れることができ、売り上げを伸ばしている。貧困層の底上げがそのまま国の成長を加速させているのだ。(編集部・古田真梨子)
※AERA 2023年8月7日号より抜粋