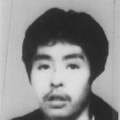――空舵(からかじ)という言葉が報じられています。
「舟は激流で船体が浮くことがあります。そうすると、舵が水に届かず空中で空振りする状態になる。それを空舵といいます。そうなると舵が取れないので舟の方向が定まらない。さらに、舵を取る船頭が転落したとなれば、舵が完全にきかなくなります。流れが速い場所で空舵になると方向が定まらないということになります」
――救命胴衣は装着しているのですね。
「腰に巻くタイプのものを必ずつけます。お客様、船頭とも同じです。お客様がきちんと装着しているか、船頭が確認してから出発します」
――船頭がさおでどの岩を突くのか、櫂をどうこぐのか、技を見せるのも保津川下りの魅力です。
「そこそこ年数を積めば、どこにどんな形の岩がある、今日の水位はこれくらいだからその岩が水面からどれくらい出ているとかわかる。流れの速さからどこで岩に竿をつくのか、櫂はどうこぐか自然と身につきます。その日の流れ、水位、天候によって微妙に変わるけど、経験で頭に入ってくるものです」
――船頭はそれぞれやることが決まっているんでしょうか。
「保津川下りは船頭3人、4人なりの共同作業で安全にお客様に楽しんでいただくもの。その呼吸が合わないとだめ。過去に、呼吸が合わずに起きた事故もあった。今回もどこかで4人の呼吸が合わなかったのかもしれないし、船尾の船長が落下したのも何か影響があったのかもしれない。20mほどの長さがある舟を操り、お客様を安全に送り届ける。チームワークなくしてできません」
――今後はどうなるのでしょうか。
「これまで事故が起こると、しばらく休んで検証してきました。今回も桜のシーズンで予約も多いかき入れ時だけど、当面は休んで原因究明となるはずです。ここできちんと検証して次につなげていかないと、400年の歴史がついえてしまうことにもなりかねない。こういうときこそ、一致結束してことにあたるべきだ」