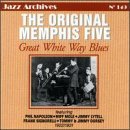
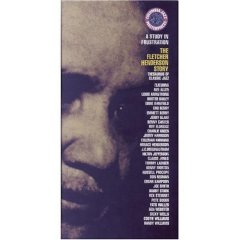

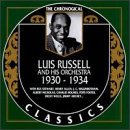
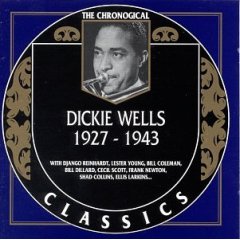
●先駆者たち
初期はリズム楽器だった
19世紀末とされるジャズ創成期から、トロンボーンはトランペットやリード楽器とフロント・ラインを構成してきた。ただし、初期の役割はベース・ラインを吹いてリズムとハーモニーを補強する裏方にすぎず、ベースのようなリズム楽器だった。こうした奏法をテイルゲイト・スタイルと呼ぶ。バンドが車で街路を行進するときに、スライドの伸縮がハタ迷惑なトロンボーンは、車の最後尾(テイルゲイト)に追い払われたことに由来する。
「テイルゲイト・トロンボーンの父」と呼ばれるのがキッド・オリー(1886-1973)だ。その力強い演奏は、ルイ・アームストロング(トランペット)のホット・ファイヴをはじめ、20年代を代表する名演の誕生に貢献した。20年代の半ば、ジャズがアンサンブル中心からアドリブ中心に移行するにともなって、トロンボーンもリズム楽器からメロディー楽器へ、脱テイルゲイトの動きを見せはじめる。ジャズ創成期から30年近くたっていた。
リズム楽器からメロディー楽器へ
先鞭をつけたのは、白人バンド、ニューオリンズ・リズム・キングスのジョージ・ブルニーズ(1902‐1974)だ。23年3月の《ティン・ルーフ・ブルース》でのメロディアスなソロは脱テイルゲイトを示唆している。これをさらに推し進めたのが、これも白人のミフ・モール(1898‐1961)だ。ビッグ・トーンによるリズミックなスタッカート・ラインは、トロンボーンの地位をリズム楽器からメロディー楽器に引き上げた。後進の白人奏者に及ぼした影響は絶大で、その代表格がジャック・ティーガーデンとトミー・ドーシーだ。
黒人側でもメロディー楽器への移行は進行していた。トロンボーンをメロディアスに演奏した先駆者に、キング・オリヴァー(コルネット)のバンドでルイの同僚だったオノレ・デュトレー(1894‐1935)と、ブルースの名手で初期のフレッチャー・ヘンダーソン楽団の主力ソロイストだったチャーリー・グリーン(1900‐1936)がいる。こうした先駆者の成果をふまえ、ルイのアドリブ奏法を手本にして、トロンボーンをソロ楽器として確立する難事に挑戦したのが、黒人ではジミー・ハリソン、白人ではティーガーデンだった。
●ジミー・ハリソン(1900‐1931)
フェイクからアドリブへ
ハリソンは16年に中西部で活動をはじめ、22年にニューヨークに進出する。初録音は25年10月のブルー・リズム・オーケストラのセッションだが、入手はむずかしい。直後の11月に、ほぼ同じメンバーで同じ曲をガルフ・コースト・セヴン名義で再録音している。《サンタクロース・ブルース》はフェイクの域を出ないが、《キープ・ユア・テンパー》では未完成ながらルイ風のアドリブを見せる。ルイがニューヨークに進出したのは24年6月で、ホット・ファイヴの初録音は25年11月だから、かなり早い反応といっていいだろう。
27年1月にヘンダーソン楽団に参加し、ソロイスト陣に名をつらねる。同楽団でのソロを追っていくと、日増しにルイ・スタイルに磨きがかかっていく様子がよくわかる。注目すべきは高音域の多用で、トロンボーンの表現力を飛躍的に高めた。28年の春にティーガーデンと出会い、ともにルイを手本とする二人は意気投合し、昼となく夜となく研鑽に励んだとされる。ただし、29年5月までは依然としてルイ・スタイルで通していて、相互影響の跡は見い出せない。録音のうえで目だった変化が現れるのは、それから1年半後だ。
悲願を盟友に託して逝く
30年12月2日のヘンダーソン楽団の《キープ・ア・ソング・イン・ユア・ソウル》と3日のチョコレート・ダンディーズの《グッドバイ・ブルース》では、ティーガーデン・スタイルに様変わりしている。ところが、31日のダンディーズのセッションではティーガーデン色は薄れ、ミディアム・ブルースでフレーズの語尾に大きなヴィブラートをつけるなど、個性の萌芽が見られる。31年7月に、スタイルを完成させることなく胃ガンで逝き、トロンボーンをソロ楽器として確立する悲願は盟友ティーガーデンに託された。未完ながら影響をうけた代表格に、黒人ではディッキー・ウェルズが、白人ではドーシーがいる。
●ジャック・ティーガーデン(1905‐1964)
早くもスタイルは完成間近
ティーガーデンは20年にプロ入りし、中西部での活動を経て、27年11月にニューヨークに進出する。卓越したテクニックと本物のブルース・フィーリングは一気に注目を集め、モールを追い落として、ナンバー・ワン・トロンボーン奏者の地位に躍り出た。28年3月、ロジャー・ウルフ・カーン楽団の《シーズ・ア・グレート・グレート・ガール》で、初めてソロの機会を与えられている。どう聴いても、ティーガーデンその人にほかならない。しかも、ベテランの風格すら漂わせている。ときに22才、驚異の新人というほかない。
ここでのマイルドなトーンによる歌心に溢れたスタイルと、やがて出来あがるスタイルとの差はわずかだ。初期のアイドル、モールの影(注)も、レコードを聴き漁ったとされるルイの影も見い出せない。長めに見ても2年でルイの影響を脱し、スタイルを完成しつつあったことがわかる。このあとのハリソンとの関係についても、相互影響の跡はうかがえない。ティーガーデンの側に立てば、スタイルではなくて志を一にしたにとどまるのではないか。ともあれ、29年3月までは完成間近のスタイルを仕あげることに費やされる。
キング・オブ・トロンボーン
完成したスタイルは、29年4月のレッド・ニコルズ&ファイヴ・ペニーズの《インディアナ》や《ダイナ》にとらえられている。このあと、30年代の初めまで数々のスタジオ・セッションに参加し、31年2月の《ベーズン・ストリート・ブルース》をはじめ、多くの名演を残した。ティーガーデンの功績として、ジャズ演奏に「寛ぎ」を持ち込んだことも特筆に価する。33年の暮れから38年の暮れまで在団したポール・ホワイトマン楽団にはジャズもどきの生温い演奏もままあるが、ティーガーデンの演奏は常に水準をこえていた。
ティーガーデンは生涯を通じて衰退とは無縁で、円熟の一途をたどる。そのヴォーチュオーゾぶりは、戦後のルイ・アームストロング&オール・スターズでも遺憾なく発揮された。ジャズ史上のベスト・プレイヤーの1人に選出されて然るべき巨人だろう。影響をうけた後進は白人に多い。代表格は、ディキシー系のルー・マクガリティ、中間派のアービー・グリーン、モダン派のボブ・ブルックマイヤー、のちに前衛派に転じたラズウェル・ラッドだ。黒人では、スウィング派のJ・C・ヒギンバッサムに影響の跡がうかがえる。
●J・C・ヒギンバッサム(1906‐1973)
野性派に見えて知性派
ヒギンバッサムは中西部での活動を経て、28年9月にニューヨークに進出し、直後にオリヴァーのディキシー・シンコペイターズで初録音の機会を得ている。ビッグ・トーンで豪放なソロをとっているが、影響源は指摘できない。スタイルが一変するのは29年3月、ルイのサヴォイ・ボールルーム・ファイヴのセッションだ。ここでのヒギンバッサムは、力強さとアーシーな味はそのままに、ティーガーデン流のスムースな歌心を見せている。
30年の半ばになると、大きなヴィブラートやダーティー・トーンを織り込むようになり、黒いティーガーデンとでもいうべきスタイルは完成に向かう。ヒギンバッサムのスタイルは、野性的な見かけに反して構成力に富んだ知性的なものだ。アルコール依存から最盛期は短く、32年12月にヘンダーソン楽団で録音した《ニュー・キング・ポーター・ストンプ》あたりが最後の名演だろう。影響をうけた代表格に、黒人ではウェルズとモダン派のJ・J・ジョンソンが、白人ではバップ期に活躍したモダン派?のビル・ハリスがいる。
●ディッキー・ウェルズ(1907‐1985)
ジャズのベルリオーズ
ウェルズは27年1月にニューヨークに進出し、直後にロイド・スコット楽団で初録音に臨んでいる。ここでの朗々型のソロに、ウェルズが夢中になったとされるハリソンの影は見い出せない。ハリソンに夢中になるのは、もう少しあとのことだろう。続く29年11月のセシル・スコット&ブライト・ボーイズのセッションでも、変化は認められない。31年8月のルイ・ラッセル楽団のセッションでは、朗々型からスウィング派に変貌しているが、発展途上だ。おそらくこの時期に、ハリソンの楽想の消化に努めていたものと思われる。
33年3月のヘンリー“レッド”アレン(トランペット)のセッションから、暖かく大きなヴィブラートに彩られた、ロマンチックなスタイルを打ち出しはじめる。晩年のハリソンと全盛期のヒギンバッサムの楽想を融合発展させたものだ。34年からは、トーンはマイルドに、フレーズはスマートに、より洗練されていく。個性を確立した雄姿は、37年7月にパリで録音された名セッションにとらえられている。ロマンチックだが力強く情熱的なウェルズを、評論家のヨアヒム・E・ベーレントはロマン派のベルリオーズにたとえた。
旧き良きスタイル
ウェルズが名をあげたのは、38年から45年と、47年から50年にかけて在団したカウント・ベイシー楽団だが、長めに見ても39年頃にインスピレーションの泉は涸れている。情熱的なスタイルは短命に終わりがちだが、ロマンの香りを満々とたたえた「旧き良き」スタイルが時流にあわなくなっていたのかもしれない。影響をうけた代表格はともに黒人で、50年代に中間派ジャズで活躍したヴィック・ディッケンソンと、J・J・ジョンソンだ。
注:29年3月のジャック・プティ楽団のセッションでは、モール流の豪快でリズミックなアプローチを見せ、被影響を裏づけている。
●参考音源
[Kid Ory]
Kid Ory's Creole Trombone (22-24 Living Era)
[Georg Brunis]
New Orleans Rhythm Kings and Jelly Roll Morton (22.8-23.7 Milestone)
[Miff Mole]
Great White Way Blues/The Original Memphis Five (22.5-27.8 EPM)
The Cotton Pickers (22.7-25.8 EPM)
Red Nichols & his Five Pennies (26.12-28.5 Decca)
[Jimmy Harrison]
The Fletcher Henderson Story (27.1-31.2 Columbia)
Benny Carter 1929-1933 (30.12 Classics)
Spinnin' the Webb/Chic Webb (31.3 GRP)
[Jack Teagarden]
Rockin' Chair/Jack Teagarden (28.3-47.5 Victor)
King of the Blues Trombone/Jack Teagarden (28.11-40.7 Sony)
B.G. & Big Tea in NYC/Benny Goodman & Jack Teagarden (29.4-34.10 GRP)
[J.C.Higginbotham]
The Complete Hot Five and Hot Seven Recordings/Louis Armstrong (29.3 Sony)
Luis Russell 1930-1934 (30.1-30.12 Classics)
The Fletcher Henderson Story (31.10-37.3 Columbia)
[Dickie Wells]
Dickie Wells 1927-1943 (27.1-43.12 Classics)
Benny Carter 1929-1933 (33.4 Classics)
The Complete Collection of Count Basie and his Orchestra on Decca (38.8-39.2 Decca)
































