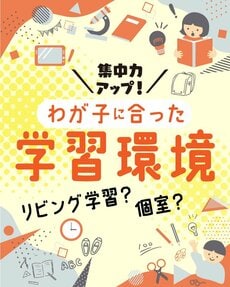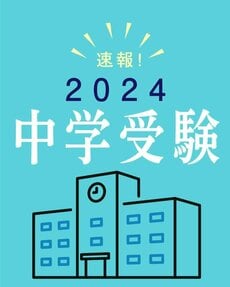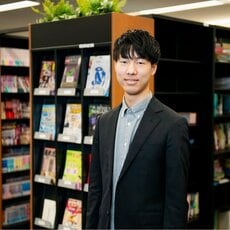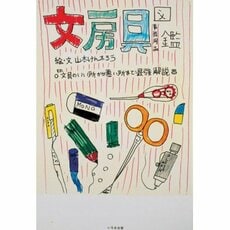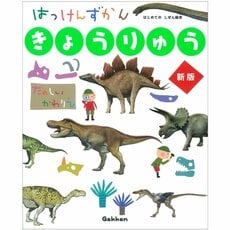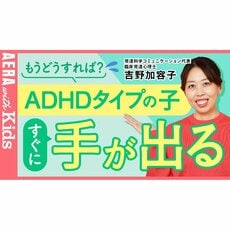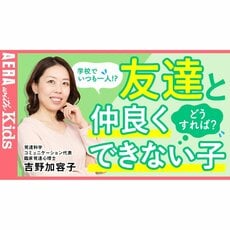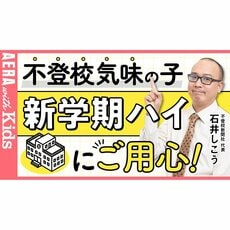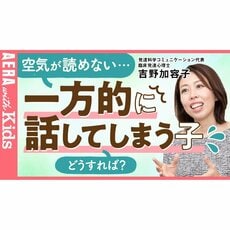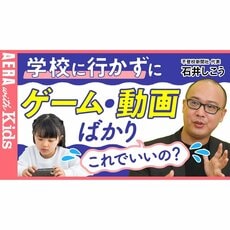私たちの祖先はいつ、どこで生まれ、どのように進化したのか? 数万年前の人類世界のようすを、最新の研究成果をもとに見てみよう。毎月話題になったニュースを子ども向けにやさしく解説してくれている、小中学生向けの月刊ニュースマガジン『ジュニアエラ』に掲載された記事を紹介する。
* * *
最初の人類は700万~600万年前ごろ、アフリカに現れたと考えられている。進化を重ね、現在、生きている人類「ホモ・サピエンス(新人)」が誕生したのは、30万~20万年前とみられる。アフリカを出たあと、ホモ・サピエンスはまとまった集団をつくり、アラビア半島を経て、中東からヨーロッパやアジア、さらにオセアニアやアメリカ大陸へと広がっていった。アフリカを出た時期は6万~5万年前からとされ、この長い旅は「グレートジャーニー(偉大なる旅路)」と呼ばれている。
じつは、グレートジャーニーに先立つ12万年前ごろ、アフリカから中東へ移動した小集団がいたことが知られている。これに対し、今年1月、イスラエルで見つかった化石から、約19万~17万年前にもアフリカを出た小集団がいたことがわかったと、イスラエルなどの研究チームが発表した。これまでの説より5万年以上も前にアフリカを出たホモ・サピエンスがいたことになる。好奇心と冒険心に富んだ祖先が、こんなに古くからいたのかもしれない。
■最古の洞窟壁画はネアンデルタール人が描いた!?
グレートジャーニーを始めたホモ・サピエンスがユーラシア大陸に移動したころ、そこにはネアンデルタール人が既にいた。しかし、その後、ネアンデルタール人は2万年前までには絶滅してしまった。ホモ・サピエンスに比べて知力が劣っていたので、生存競争に敗れたと考えられている。たとえばフランスのラスコーの壁画制作で有名なクロマニョン人はホモ・サピエンスで、絵を描くような芸術活動は他の人類にはない能力とされてきた。