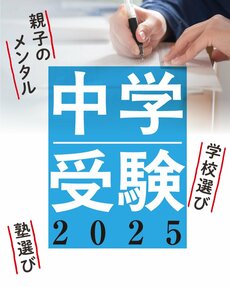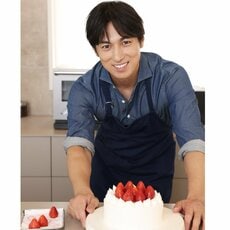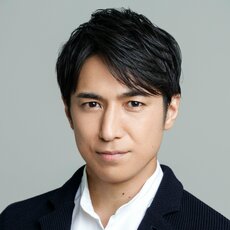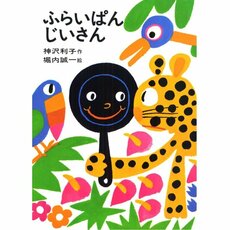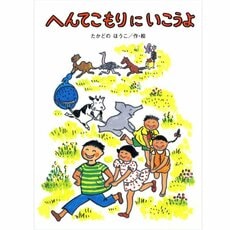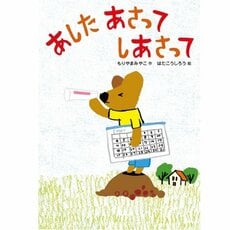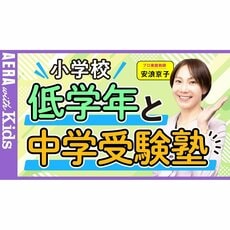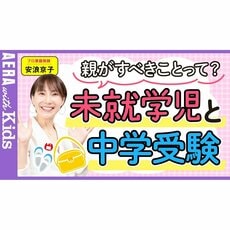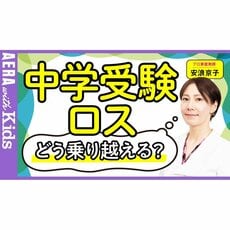運動会シーズン。過去の記事を再配信します(2025年4月17日の記事を再編集したものです。本文中の年齢等は配信当時)。
【マンガ】「なぜ学校に行けないの?」と聞いても、子どもが「わからない」と言うのはなぜ?(全31枚)東京都八王子市の公立中学校で、支援教室の教員を務める中澤幸彦先生。支援教室の生徒一人ひとりが、「好き」「楽しい」と感じられることに出会い、「なりたい自分」に近づけるような授業のあり方を模索しています。中澤先生が、授業中に、特に意識しているのは、生徒への声掛けです。授業中の言葉がけを少し変えるだけで、生徒たちの授業への主体性が大きく変わったといいます。家庭での教育にも活かせる、「子どもの心に響く言葉選び」についてお聞きしました。
体育は「スポーツ」水泳は「バカンス」…言葉が意識を変える
3年前に八王子市の中学校の特別支援教室に配属になりました。それまで14年間、体育教諭として市内の別の学校に勤務していましたが、実は、以前の私は典型的な”怖い教師”でした。
10年前に、生活指導主任として配属された学校は、職員室に生徒が怒鳴り込んできて、先生と生徒がバトルをするような、いわゆる”荒れた学校”だったのです。
生徒が暴れるのを止めようと、教員が強く注意すればするほど、生徒の心も荒れてしまう……全くの悪循環でした。
これではダメだと思い、「生徒に寄り添うとは何だろう」と、私は自分に問いかけるようになったのです。
例えば、体育の授業は、走ることも泳ぐことも「ちゃんとやらなくちゃいけないもの」、「速さや強さを競うもの」と思われがちです。しかし、これでは、体を動かすのが苦手な生徒は、よけいに苦痛を感じてしまいます。
そこで、まず体育の授業中に行った”改革”の一つが「言葉を変換すること」でした。生徒たちの苦手意識を減らしてもらおうと、体育は『スポーツ』、水泳は『バカンス』と呼び方を変えてみたのです。
たったそれだけのことで、生徒たちも面白がって、驚くほど授業に積極的に取り組んでくれるようになりました。
体育の本来の目的は、技術や記録を伸ばすことだけではありません。ライフスタイルや興味関心に応じて体を動かす楽しさを知ったり、生涯にわたりスポーツを通じた自己実現に挑戦したりすることでもあるはずです。生徒の様子から、楽しんで体育の授業に取り組んでもらうことが、まず大切だということに、気付かされました。
次のページへ長距離走は億劫になるけど…