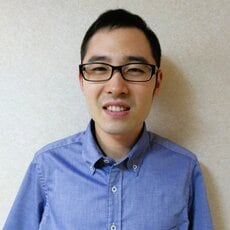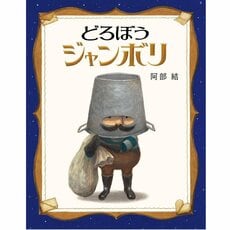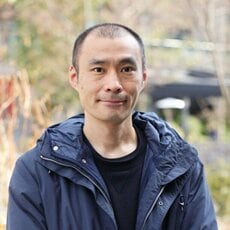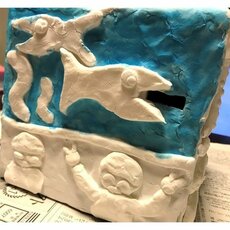イラストエッセイスト、コラムニストとして多方面で活躍する犬山紙子さん。自身が体験してきた女の子の理不尽さを自分の子どもに味わわせたくないという思いから、7歳になる娘さんが生まれて間もないころから「ジェンダー教育」を始めたそうです。『私、子ども欲しいかもしれない。』(平凡社)『アドバイスかと思ったら呪いだった。』 (ポプラ文庫)という著書でも知られる犬山さんがジェンダー教育に力を入れるようになったきっかけや思い、手助けになっているものについてうかがいました。※後編<犬山紙子が子育てで“本当になくなってほしい”と思う親の対応とは 「謙遜じゃなくて、ただの悪口だと思うんです」>へ続く
【写真】犬山さんと娘さんのショットはこちら(ほか、全3枚)この社会で女の子を育てるのがすごく不安だった
――「ジェンダー教育」を意識されるようになったきっかけを教えてください。
私は、子どもを産んだときに、「すごくうれしい」「本当にかわいい」という気持ちと同時に、この社会で女の子を育てるのは不安だな、という思いがとても大きかったんです。というのも、私自身が女として生きてきて、女じゃなかったら受けなかった理不尽な思いというのがあったからです。友人やまわりの人に話を聞いても同じような気持ちを抱えていました。
日本はジェンダー・ギャップ指数でかなり遅れているという現実もあるなかで、娘に女の子だからという理由で自分の意志を取り下げることなく、自分でよかったと思って生きてもらうためにはどうしたらいいかと考えたのがきっかけだったと思います。
――女性特有の理不尽さについては、子どものころから感じていましたか?
私は算数がすごく好きで算数の勉強をしていると、「女の子なのに、算数が好きなんてすごいね」と言われることがありました。これは一見褒め言葉のようなんですけど、“女の子は算数が苦手”であるという前提がある言葉ですよね。やっぱり算数では男の子にかなわないのかな、と思うようになりました。他にも、食事のときに動くのはなぜか女性だけなんだろうだとか、かわいくしていないと冷遇されるんだなあとか、意見をはっきり言うと気が強いと言われたりだとか。
また、中学になると電車通学になって、そこで痴漢に遭ったんです。それまでは親に守られ、まわりからも子どもとして扱われていたのが、急に大人の男性から性の対象として見られてしまう。これは男子にもありえることですが、当時は学校や家庭での性教育もまだまだな時代で、痴漢に遭ったことに対して怒っていいのかもわからなかったし、親に言って心配させたくない、まわりに相談して逆に自分が責められたらどうしようという思いもありました。加えて、それをまわりに言うと自慢だと思われるかもしれないという懸念もありました。痴漢に遭うだけでも理不尽なのに、ちゃんとした性教育を受けていないために適切な対応がとれなかったんです。
次のページへカウンセラーを頼る大切さ