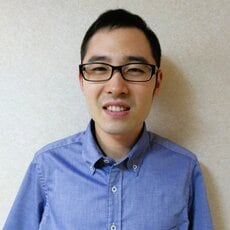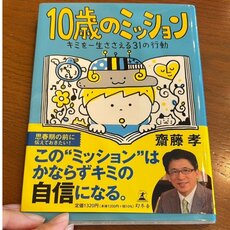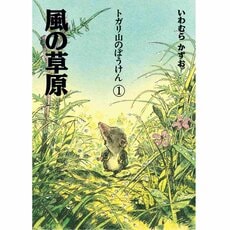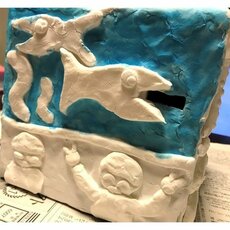休校期間が長引く中で、いつもより子どもと過ごす時間も増え、親の負担も増加。これまで以上に子どもの言動や振る舞いが気になるかもしれません。「発達障害かもしれない」と思ったときにまずは子どもの“困り感”を正しく知り、適切なサポートをすることが大切です。「AERA with Kids春号」(朝日新聞出版刊)では、発達障害の主な症状や対応について、長年、多くの発達障害児の診察をしてきたどんぐり発達クリニック院長の宮尾益知先生にお話をうかがいました。
* * *
「じっと座っていられない」「かんしゃくを起こす」「読み書きが苦手」などは、幼少期や小学校低学年にはよくあることです。しかし、何度も繰り返され、日常や集団生活に支障をきたすようなら、「発達障害」を疑う必要があるかもしれません。
「多くは、その子が属する2カ所以上の環境でうまくなじめない場合に診断がつきます。最近は3歳児健診や進学前相談で見つかることも多いですが、はっきりとした診断名がつかないまま、入学後や思春期に生きづらさが出ることもあります」
と言うのは、宮尾先生。
診断がつかなくても、発達に凸凹(でこぼこ)や強い特性があると、発達障害の「傾向がある」とか「グレーゾーン」という言い方がされることもあるかもしれません。いずれにせよ、独断での判断は禁物。本人が感じている“困り感”は何かを見極め、専門家と連携した適切なフォローが大切です。
「こだわりが強いのがASDで、ADHDは注意力が散漫」など主な傾向について大まかな理解を持つ人も多いでしょう。しかしこの二つでも知的障害を伴う場合と伴わない場合、軽度重度、複数の障害が重なるケースなど、発達障害の現れ方はさまざま。心配ならまずは医療機関にかかることをお勧めすると宮尾先生は言います。
「発達障害の診断は差別するためではなく、必要な支援や医療ケアを受けるためのもの。アメリカやイギリスは医師の診断書がなければ行政の支援が受けられません。日本はそこまで厳しくないですが、カルテがなければ継続的な診察はできないのです」
小児科や地域の発達障害者支援センターに問い合わせて、発達障害に詳しい医療機関につないでもらうこともできます。
「診断を受け、カルテができたら、定期的な診察、保護者への指導必要に応じた服薬、また、臨床心理士や作業療法士などの専門家と療育的指導もしていきます」
日常生活やコミュニケーションに問題はないものの、学習を通して見えてくる障害が学習障害です。幼児のころには気づかないこともありますが、小学1年生が終わるころになっても読み書きや計算などが難しいと、学習障害の診断がつきます。