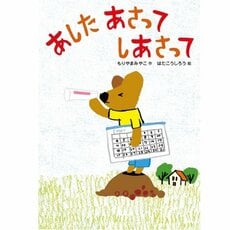高濱:先日、研究者の落合陽一さんのお母様・落合ひろみさんと対談したんですが、彼は子どものときにゴキブリをずっと飼っていたと話していました。なかなか受け入れにくいと思いますが、「ゴキブリが好きなら、まあしょうがないかな」って見守っていたそうです(笑)。
yuu:受け入れてくれるお母様、すごいですね(笑)。
高濱:子どもたちが興味を持つものって、大人から見ると何になるんだろうと思うものだったりもします。でも子どもにはそんなこと関係ないんです。だから、子どもに寄り添って「それ面白いね」って伴走してあげてほしい。大人の価値観で「そんなの意味ない、お金にならないよ」って言い始めてしまうと、その子の可能性を摘み取ってしまいかねない。
yuu:私は小学生のころ、リカちゃん人形が大好きで洋服を作ったりしていました。今、親子リンク服のブランドを立ち上げて、子どものときしていたことがつながってくるのかなと。そう考えると、私の息子にも対象がなんであれ、何かを突き詰めていく経験をやらせてあげたいなと思います。
高濱:親御さんの気持ちもわかりますけどね。「電車ばっかりじゃなくて、少しは算数もやろうよ」みたいな(苦笑)。
親は「博士力」をどうサポートする?
yuu:わかります。親が寛容な心を持つことも大事でしょうか?
高濱:というか、「わが子の目が輝いていることを楽しむ」ことです。赤ちゃんのころはそうしていたはずなのに、いつのまにか自分の価値観を持ち込んでしまう。わが子が夢中でなにかをしている姿を慈しむ気持ちを忘れないでほしいですね。
yuu:私は大学時代、東大に入ることがゴールで燃え尽きてしまっている人が多いことが衝撃的でした。小学校高学年くらいからずっと勉強を頑張ってきて、大学に入れたから好きなことしていいよと言われても、難しいのかなと思います。
高濱:社会で求められている力と受験に必要な力が乖離しすぎているのは本当にそうですよね。
親御さんを見ていて一つ感じるのは、特に母親が男の子の関心に寄り添えない例が多いのではないかということ。どろんことか戦いとか、虫の足をちぎってみちゃうとか。男の子が目を輝かせて「いいこと思いついちゃった!」って言うことって、母親にとっては大体止めたいことですよね(笑)。でも、ちょっとがんばって見守ってほしい。
次のページへプラレール分解に集中する息子を見て