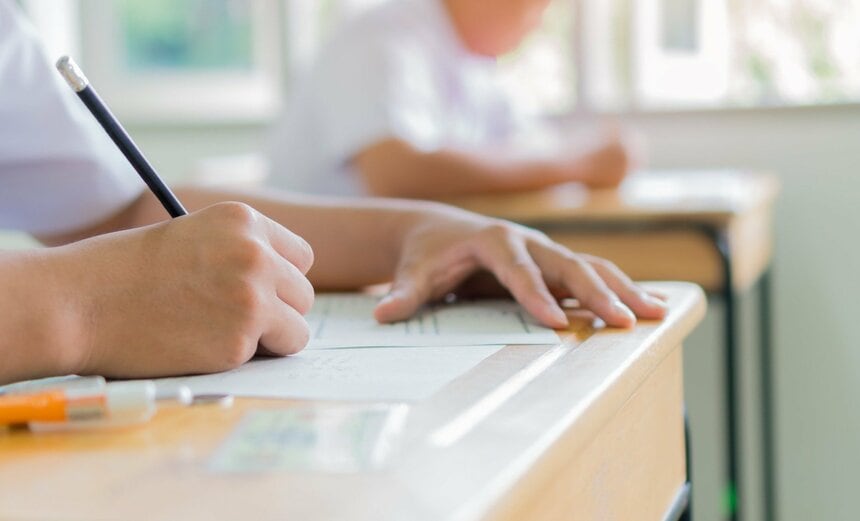首都圏を中心に相変わらず人気がある中学受験。競争の激しさが増す一方で、親も子も目の前の「受験勉強」に追われがちです。しかし、そうした状況に警鐘を鳴らすのが、4人の子ども全員を東大理三に合格させた佐藤亮子さんと、数多くの受験生を志望校合格へと導いてきた中学受験専門カウンセラー・安浪京子さん。本記事では、2人の共著『中学受験の意義 私たちはこう考えた』から一部を編集し、その“本質的な学び”のヒントをお届けします。
【マンガ】「偏差値の高い学校」への思いを捨てきれなかった母が、「路線変更」を決断して“わかった”こととは(全38枚)中学入試の難化で促成栽培化!?
安浪:今、全体的な中学入試の傾向を見てみると、入試問題が難しく、範囲が広くなってきています。それに合わせて塾のテキストも改訂するたびに範囲は広がり、難化しています。
佐藤:こういうものはどんどん難化するものなんじゃないでしょうか。以前、進学塾の浜学園から30年前の灘の入試問題をもらったことがありますが、私でも解ける問題が結構ありました。でも、今の問題は無理ですね。
安浪:そう。灘をはじめ、最難関校で出たような問題が、難関校、中堅校…と降りてきて、どんどん出題されるようになるんです。
佐藤:オリンピックの競技が高度化していくのと似てますよね。でも子どもは生物学的にそんなにすぐに賢くならないでしょ。
安浪:だから今、大変なんです。内容が難化して、ボリュームが多くなっているのに、ゴールの時期は決まっているから学力をじっくり育てることができず、促成栽培のようになってしまう。昔は5年生からでも間に合いましたが、今、難関校以上を目指している場合、5年からだともともと持ってるもの(資質)がないと難しいです。第一、量が終わらない。
佐藤:受験って結局、定員が100だったらそこに入るための競争ですからね。みんなその席目指して頑張ってやっているわけですから、ゆっくり寄り道していたら通らなくなる。
中堅校が難しくなったってホント?
安浪:それに今は中学受験に対する考え方も多様化していて、最難関校や難関校に挑戦できるような力を持っている子でも、親が無理せず本人が行きたいところで、といった偏差値至上主義の選び方をしない家庭が増えています。それ自体は良いことなのですが、従来は最難関校や難関校にチャレンジする子たちがそれを回避して学力的に余裕を持った学校選びをすることで、おのずと難関校や中堅校が難化しています。もちろん、うちはここしか狙いません、という層も一定数あるんですが、真ん中やその上あたりが難しいんです。中堅校はほんとに大変。
次のページへ関東・関西の入試傾向の違い