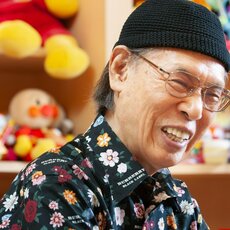スマホ依存だけではない! 「電子スクリーン症候群(ESS)」に注意
――親子の日常で、澤口さんが「危険だな」と感じることは?
「テストでいい点数をとったら、ゲームを30分長くやってもいいよ」という具合に、ゲームをごほうびにしてしまうような場面は、危険だなと感じます。つい言ってしまいがちなのですが、スマホやゲームはたばこやアルコールと同じ依存物質だということを心にとどめておきたいところです。
また、近年、米国の精神科医・医学博士のビクトリア・L・ダンクリー博士が提唱した「電子スクリーン症候群(ESS)」も注目を集めています。これは、スマホやゲームなどの電子スクリーンによる、気分や認知、行動や社会性への影響のことです。
具体的にはちょっとしたことでイライラしたり、落ち着きがなかったり。また、考えがまとまらない、集中力や記憶力の低下などもあげられます。さらにチックや片頭痛、対人コミュニケーションへの不安や気持ちの落ち込みなど。
もし、デジタル機器に頻繁に触れているお子さんに、ここ2、3カ月の間にこのような心配な変化が見られたら、ESSの可能性を疑ってもいいかもしれません。依存症ではなくても、確実にデジタルによる影響が表れていることが考えられるからです。
親子で、プチ・デジタルデトックスを試してみよう
――わが子に思い当たる症状がある場合、まずどうしたらいいでしょうか。
ダンクリー博士は、ESSの治療法に「リセットプログラム」を提唱しています。これは、3週間電子スクリーンのない生活をしてみることです。
実際、3週間のスクリーン断ちはかなり難しいものです。しかし、このプログラムの目的は、デジタルから離れることで「脳をしっかり休ませて、どうなるか」を見ることにあります。先ほどお話しした、心配な変化の原因がデジタル機器によるものなのかを見極めるための、アレルギー検査のようなものなのです。もし、デジタルを3週間断つことで、本来の姿を取り戻すことができたら「あの変化はデジタルが原因だったのだ」ということがわかりますね。
次のページへ親子でデジタルのない生活を体験してみよう