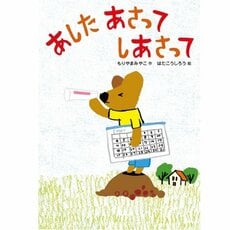――もしも問題が起こった時は、どうしたら良いでしょうか?
黙ってやめたりせず、早めに職員に相談することです。現場の職員には言いにくいことだったり、運営自体の問題だったりする場合は、保護者仲間と連れ立ってでもいいので、役所に相談するのもいいでしょう。
なお、入学したばかり1年生の保護者からの相談でよくあるのが、「6年生のおにいちゃんをこわがっているから、あの子をやめさせてください」というものです。でも、小さな1年生が、体の大きな上級生に圧倒されるのは当たり前です。学童側に伝えれば、きっと上級生に「小さい子にはやさしくしてあげてね」なんて伝えてくれて、気づいたらきょうだいのように仲良く遊んでいた……なんていうことも多いんです。
環境に慣れていないことで起こる心配事もありますので、気になることがあってもすぐにダメと決めつけず、少し様子を見ることも大切です。
学童で育まれる「非認知能力」とは
――子どもたちが楽しく放課後を過ごせるといいですね。
学童って本来、とてもいいところなんですよ。1年生から6年生までの多様な子どもたちが交流し、おにいちゃんおねえちゃんから遊びを学んだり、「何をして遊ぼうかな」と自分で考えたり、困った時に「どうしたらいいかな」と試行錯誤したり。読み書きや計算ももちろん大切ですが、それだけでは身に付きにくい、自己肯定感、自尊心、協調性、共感力といった「非認知能力」を伸ばせる場でもあると私は考えています。
子どもにとって、それぞれが自分らしい放課後を過ごせることが一番大事です。学童保育はもちろん、必要に応じて自治体ともコミュニケーションをとりながら、子どもファーストで環境を整えてあげてくださいね。
知られざる〈学童保育〉の世界 問題だらけの〝社会インフラ〟

萩原和也

著者 開く閉じる