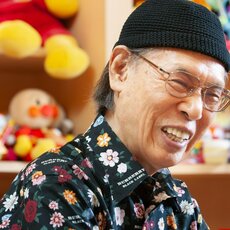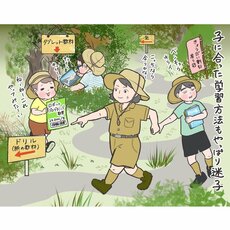学校へ入ると下駄箱がなく、すっきりとした昇降口の小学校――。そんな下駄箱ナシ、上履きナシの公立小中学校が東京都港区や中野区などで出てきました。履いてきた1足の靴で学校生活を過ごす「一足制」が増える背景には、どんな理由があるのでしょうか。
【写真】下駄箱がない!?すっきりとした港区立小学校の様子はこちら(全3枚)上履きの存在自体が子育てのストレス
小学生親子にとって、週末の憂うつともいえる上履き洗い。「金曜には持って帰るのを忘れて、月曜には持っていくのを忘れます。しかも子どもが自分で洗わないので面倒です」と“上履き地獄”からの解放を願うのは、小学2年と3年の男児を育てる都内の40代女性です。持ち帰らない、上履き袋に入れない、自分で洗わない、乾かない、しかも忘れていく……。「上履きの存在自体が子育てのストレスになっている」と感じる親も少なくありません。
学校でバレエシューズタイプの上履きに履き替える習慣は日本独自で、全国を見渡すと外で履く靴と上履きの二足制を導入している学校が圧倒的に多いのが現状です。土足を脱いで上がる習慣は寺子屋の時代には既にあったとされ、一般的なバレエシューズタイプの上履きを履くようになったのは戦後から。以後、上履き文化は続いてきました。
ところが最近は東京都港区や中野区、台東区、品川区などで、上履きを廃止する学校も出てきました。たくさんのメリットが考えられるためです。持ち物の負担軽減、スペース確保、昇降口での滞留の解消、自由な出入り、災害時の避難の円滑化、下駄箱周辺のトラブルの解消などの観点から、検討が進められているようです。
港区の小学校はほとんど上履きナシ
港区では、ほとんどの区立小学校で上履きナシの制度が導入されています。港区教育委員会によると、グラウンドを人工芝化したタイミングなどで導入が始まり、すでに小学校は19校中18校、中学校は10校中7校が上履きを廃止しています。この制度の導入の最終的な判断は学校長に委ねられますが、背景には港区の地域特性もあるようです。
次のページへ雨の日はどうするの?