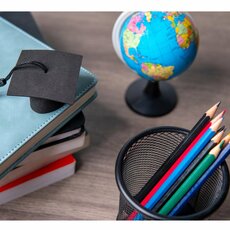高貴な身分の女性たちは活発に動くことを封じられていました。それでなくても当時の衣服はドラマで見るような形ではなく、ほとんど腕を袖に通すことすらせずに布団をかぶっているような状態で過ごしていたので、実際そんな気楽に動くとすぐ脱げちゃうんです。
その高貴な女人に仕える女房(身の回りの世話をする召使)たちもまた同じような服装をしています。長袴も穿いているのでお姫様の世話をするにもそう簡単にパタパタと立ち歩けません。
そこでちょっとした用なら「いざる」のです。
「いざる」とは、膝を使って座ったまま動くこと。部屋の中の移動くらいならこの方法を使うことも多かったようです。
と説明すると、子どもたちが早速家の中を「いざり」始めました。
「わー膝いってぇー!」
「廊下で競争だ!」
と大盛り上がり。
息を切らして戻ってきた次男が一言。
「お母さん、平安時代の人ってめっちゃ体力あるね!」
違う違う、そうじゃない。そんな長距離いざらない。
ところで最近若者言葉がどんどん簡略化して、「いいことも悪いことも感情をなんでも『ヤバイ』で済ませるようになった」「日本人はバカになってきた」、そんな嘆きを耳にすることがあります。
うちの子たちもよくヤバイヤバイと言うし確かにもっと語彙力を高めたほうが……というのも一理あるんですが、実は繊細な感性を爆発させている平安時代にもざっくりした表現があるんです。
それが「いみじ」。
これ、よい時も悪いことにも使う形容詞。まさに「ヤバイ」と同義。
「ためしにヤバイって言いそうな時に〝いみじ〟に言い換えてごらん」
とやってみると、これまた面白い現象が。
「やっb……いっみじぃ〜」
「これやば……いみじくね?」
しばらくして三男(5)より「いみじって言いにくいからイヤ」と苦情が入りました。
「そうだよね、その時代の言い方を現代語の中で使うの難しいよね。じゃぁ〝いみじ〟の前に〝あな〟ってつけてごらん?今でいう〝うわぁ〟みたいな意味だけど、言いやすくなるよ」
「そこまでして言いたくないかな」
デスヨネー。(完)
ま、“ヤバイ”だって江戸時代からなんですけどね。
次のページへ母が興味のあることを家族に伝え続ける理由