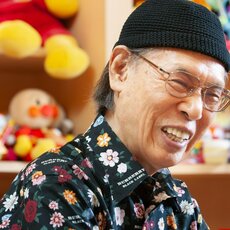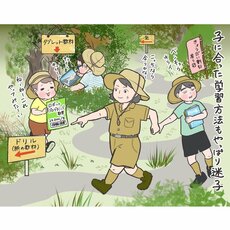基本的には同じです。学校に行ったり休んだりを繰り返しているお子さんには、その日の朝や前日に「学校へ行くかどうか」を確認しましょう。その際は、「明日は行くの?」「今日は行くの?」といった質問を、問い詰めるのではなく、「夜ごはんは何が食べたい?」と聞くのと同じくらい軽い調子で尋ねるのが理想です。本人が「行く」と言えば行かせ、「行かない」と言えば休ませる。自分の予定を自分で決め、それを必要な人にきちんと伝えることは子どもが将来、社会参加をするために必要なスキルです。こうした習慣を、家庭の中で自然に身につけられるよう心がけましょう。
――子ども自身で「明日は行く」と決めたのに、翌朝になると「やっぱり行きたくない」と言い出すこともありますよね……。
子どもは気が変わるものです。「行きたくない」という最終的な判断を尊重して、残念な素振りは見せずに淡々と応じることが大切です。不登校になりたての時期にそうするのは難しいことではありますが、前日に「行く」と言っても、当日になって休む可能性はある。そう心積もりしておくと、親の気持ちも少し軽くなります。そこで、「昨日は行くって言ったじゃない」と責めたり、「一度決めたことは変えていけない」と諭したりするのはNG。不登校のお子さんにとっては、学校の話題そのものがしんどいこともあります。大切なのは、子どもが安心して自己決定でき、困り事を相談しやすい環境を整えることです。
――新学期は最初こそ登校できても、しばらくすると再び行けなくなることもあります。親はどんな心がまえでいればいいのでしょうか?
2学期に入り頑張って通っていても、その反動が必ずやってくると覚悟しておきましょう。私の経験では、大半の子が再び行けなくなっています。子どもが「頑張る」と言うのを止める必要はありませんが、「これをきっかけに通えるようになってほしい」と望んではいけません。子どもが登校するかどうかに一喜一憂していると、それが子どもへのプレッシャーになる場合もあります。子どもが自分で考え、自分の価値観を保っていくためには、親が理想を手放し、期待を押し付けないことが大切です。理想を手放すことは一筋縄にはいきませんが、心がけてほしいですね。
次のページへ「期待しない」ことは見捨てること?