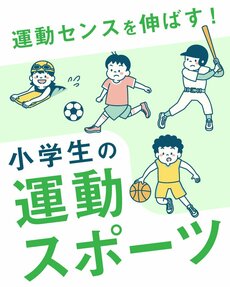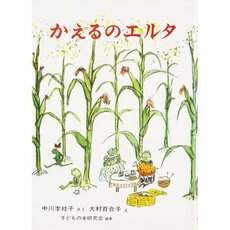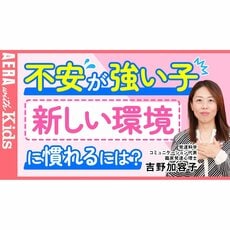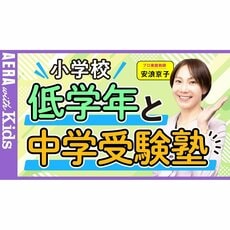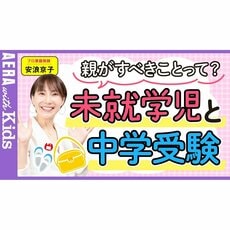ジェンダーに関わる本を急いで与える必要はない
心理発達的に、3歳くらいになると自我が芽生え、集団生活も徐々に始まって自分と他人との区別がつくようになり、世界が広がると言われています。社会性が身についてくるとともに、想像力を働かせてより絵本の内容も理解できるようになっていきます。
近年は、海外絵本を中心に、ジェンダー平等を意識した作品が登場しています。ただ、ジェンダーに関わるような物語は、少し難しいですから、想像し、理解して読めるようになるには未就学児だとまだ少し早いかもしれませんね。
こうした絵本を未就学児の子どもたちに急いで与える必要はなく、子どもたちが日々成長していく中で、改めて男の子、女の子といった問題が、社会の課題であるとなんとなくわかってきた頃に、ジェンダーについて描かれた絵本を与えてみるのがいいのではないかな、と思っています。
――ジェンダーの平等性について描かれた絵本というのは、数多く出版されていますか?
やはり、絵本のメインは昔から人気のベストセラーで、ジェンダーをテーマにしている本というのは、数としてはそれほど多くはありません。しかし、「#MeToo」の運動などに始まり、女性差別を無くそうという動きが、色々な分野で起こっていますよね。そうした中で、ここ数年、絵本の世界も少し変わってきて、新しいジェンダー観を表現した作品も発表されています。
実は子どものほうがジェンダーバイアスから自由
――新しいジェンダー観がある絵本にはどんなものがありますか?
例えば、「女の子、男の子どちらが主人公であってもいい」「それぞれが自分らしく活躍していい」といったようなメッセージが込められた絵本も人気を集めてます。そうした絵本を少し読んでみるというのも、よいのではないでしょうか?
昔ながらの絵本はやはり、子どもたちの心を捉える素晴らしいものですが、もし「男性優位のジェンダー観が描かれている絵本ばかり読み聞かせることに抵抗がある」「早いうちからジェンダー教育をしたい」、という親御さんであれば、10冊のうち3冊くらいジェンダーに関わるような物語を意識して読んでみてもいいかもしれません。
次のページへ読み聞かせで一番大切なことは…