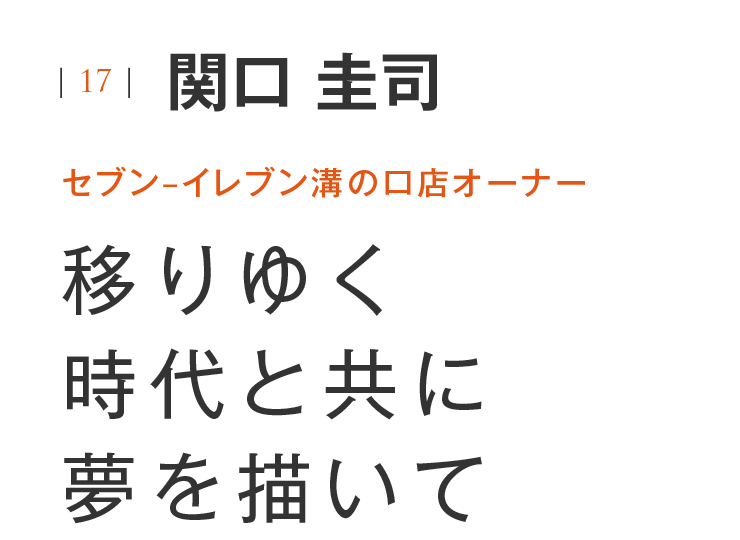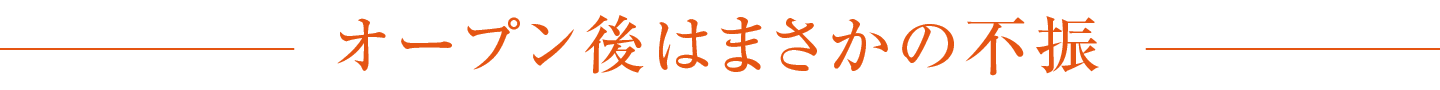オープンから数年後の圭司さんと妻の久子さん。まだ30代前半、毎日がむしゃらだったという(1980年前半、溝の口店で撮影)
まさしく、挑戦だった。43年前、24歳で「セブン-イレブン溝の口店」のオーナーになった関口圭司さん(67)の人生ストーリーには、そう思わせる重みがある。
加盟した1977年当時、セブン-イレブンは関東エリアを中心に200店ほどしかなかったという。
「『セブン-イレブンを始めます』と、近隣のお客さまにご案内に行ったら、必ず『それ何ですか?』と返されて。クリーニング屋や文房具屋と、よく間違われましたよ」
そう圭司さんは苦笑する。信じられない話だが、セブン-イレブンが無名の「町のよろず屋」だった時代、圭司さんのように将来を夢見て新たな商売に挑んだオーナーたちがいたからこそ、今がある。
「商売の大変さはよく知っていましたから、大学卒業後は、一般企業に就職したんです」
圭司さんは、地元に根を張る米屋の跡取り。継げば9代目だったが、あえてサラリーマン人生を選んだ。それが入社1年半でコンビニオーナーに転身するのだから、人生、何が起こるかわからない。
きっかけは、セブン-イレブンの本部担当者が実家の米屋を訪れたことだ。
「父親はセブン-イレブンのことを全く知らなかったので、仕事で小売業をリサーチして知識があった私も一緒に対応したんです。そこからです、興味を持ったのは」
高度成長期を経た日本じゅうが、高揚感であふれていた時代だ。未知の可能性を持つコンビニというビジネスに心が動いたことは、自然なことかもしれない。
「そんな時です。セブン-イレブンに加盟したオーナーのグループがアメリカに視察に行くという話を聞いて、よし、自分も行くぞ!と。すぐに会社を辞めました」
この行動力が圭司さんの武器だ。「商売の道を歩むなら」と父親があと押し、自宅の隣に建てたアパートの1階を店舗に、セブン-イレブン溝の口店が77年3月31日、オープンした。
と、順風満帆に進んだかに見えるが、開店後長らく「不振続きだった」そうだ。コンビニという新しい店の立ち位置が、世の中に確立されていなかったからだろう。
「商店街からはうまくいくわけがないという大反対の声が聞こえてくるし、お客さまからは『何を売っている店かわからない』と言われるしで、どうしたらいいのか……」
抱いた期待が大きかっただけに、業績不振はショックだった。仕事を辞めてまで嫁いできてくれた久子さん(65)に、苦労をかけたくないという焦りもあった。どうにも気持ちが上がらない。そんな中、転機は突然やってきた。
「当時、イトーヨーカ堂の常務だった鈴木敏文さん(現セブン&アイ・ホールディングス名誉顧問)が店にお見えになって、じっくりお話しする時間をいただきました。帰り際、店が入ったビルの屋上から町を見渡されて『この店はもっと伸びるよ』とおっしゃってくださった。勇気が湧きました」
諦めない。圭司さんは、以前にも増して前向きに働きだした。
業績を上げるには、多くのお客さまに来店してもらうことが先決だった。店は各種交通機関が交差する溝の口駅のすぐ近く。街の再開発などで客足の流れが変わることはあったが、立地は悪くない。なぜ、お客さまが増えないのか。大きな課題だった。
圭司さんは課題を抱えこまず、信頼する従業員や本部のOFC(店舗経営相談員)に積極的に話したという。
「特にOFCさんは店に対して客観的な視点を持っているので、話していると参考になる。その中からやるべきことを洗い出し、店のためになりそうなことは何でもやってみました」
時には来店客が売り場をどう買い回るかを朝昼晩に分けてリサーチ、時間帯別の売れ筋商品を確認した。またある時は、当時はなかったPOS(販売時点情報管理)システムの代わりに手作業で客数や客層をカウント、お客さまの嗜好を探ったりもした。
とらえた手ごたえは、すぐに実践に生かす。深夜にサラリーマンの来店が増えることを見越して子どもたちへのおみやげ用のぬいぐるみを並べたり、若い女性客のために流行のヘルシードリンクをいち早く発注してみたり。チャレンジを重ねた。
高度なデータ分析技術がない時代だったが、真摯にお客さまと向き合えば、自然と「便利なもの」「必要なもの」、そして「売れるもの」が見えてくる。こうして常に新鮮な売り場づくりに徹するうちに、業績は少しずつ上がっていった。
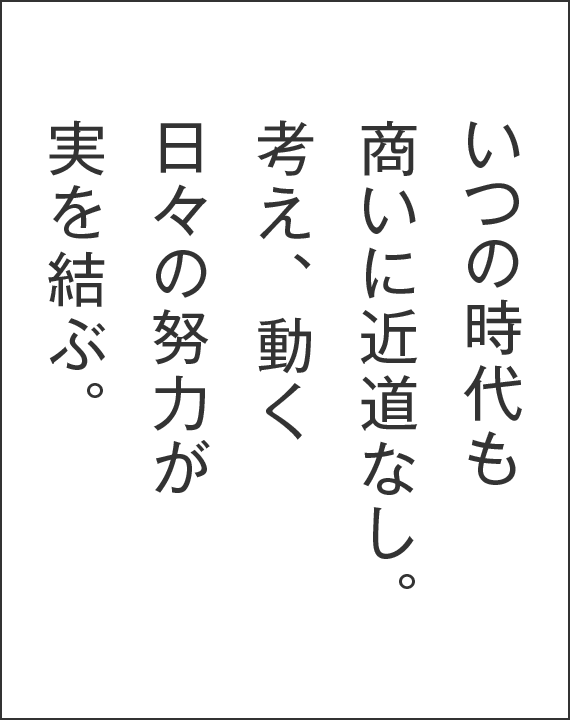

長女の関口久美子さん(41・右)と夫の直樹さん(43)が店を回す。
「両親を見習って頑張りたい」(久美子さん)
商売は上り調子の時ほど、歩みを休めることも必要だ。圭司さんは言う。
「40歳前の時、ビルを建て替えるために店を18カ月くらい、閉めたことがありました」
がむしゃらに走り続けて業績を安定させ、気づけば90年代。全国各地にコンビニができ、業界は成長期に突入していた。その時に閉店、である。
「一度、お客さまの立場に戻って世の中を見てみたい。そしてセブン-イレブンって、どんなお店であるべきなのかを考え直してみたかったんです」
言葉どおり、店を閉めている間、圭司さんは一切仕事をしなかった。
結婚し、子育てをしながら売り場に立つようになった長女の関口久美子さん(41)は、当時のことを覚えている。
「両親がずっとうちにいて、失業しちゃったのかと心配でした。でも今は、お客さまの気持ちを知りたいという父の考えがよくわかります」
仕事がない分、いつでも自由に買い物にでかけた。好きな場所に足を運び、映画やアートなどにもよくふれた。そんな日々を過ごす中で、わかったという。
「時間に余裕のあるお客さまは、コンビニを選ばない」
時間があると、広い売り場をゆっくり見て回りたくなる。商品もあれこれ吟味して買いたい。コンパクトな売り場に、オリジナル商品が数多く並ぶセブン-イレブンは、やはり多忙なお客さまの暮らしを支える店であるべきだ──頭でわかっていたことを、圭司さんは体感した。
「揚げ物や総菜の発注により力を入れるようになりました。忙しくて手間をかけられなくても、この店ならおいしい商品がサッと買えて便利。セブン-イレブンの価値は、そこにあるんです」
セブン-イレブンの価値は、「便利」を提供すること──それが商売の指針となった。

ふたりで歩んだセブン-イレブンの道は「平坦ではなかったが楽しかった」と圭司さんと久子さんは振り返った

「あれもこれもほしい」と購買意欲が刺激される美しい
売り場は、圭司さんのこだわりだ
リニューアルオープンして以降、圭司さんは一層、従業員とがっつりスクラムを組むようになったという。
長年自分の店で働いている従業員たちに、もっと幸せになってほしかった。幸せの定義は人それぞれだが、何より自分が成長できたと感じた時、人は大きな喜びを得るのではないだろうか。
日々の業務のほか、リーダー格の従業員を定期的に集めてミーティングや勉強会を重ねた。単に集めるだけじゃない。自宅の一室に設けた会議室で久子さんお手製の食事つきという好待遇だ。
「努力した人を認めるのは当然のことだし、一人ひとりの役割を明確にして任せることで、仕事に誇りを持つことができる。ちょっと体育会のノリでしたが、私を含め、みんなで切磋琢磨できたと思います」
こうしてチームで店の運営に向き合ったのち、多くが独立してオーナーになっていった。だが不思議と、圭司さんは「誰にも独立を勧めたことはない」そうだ。
「私がやってきた姿を見て、自分も頑張ってみようと思ってくれたんでしょう」
と、うれしそう。横で話を聞いていた久子さんが言う。
「独立したみんなが活躍されている話を、まわりの方々から聞きます。どの店も、昔からオーナーがこだわってきたように商品がきちっと並んでいてきれいと聞くとうれしいです」

現在、メインで店を切り盛りしているのは、圭司さんと久子さんの背中を見て育った久美子さんと夫の直樹さん(43)だ。
家業を継ぐ形で店に入ったふたりは「自分たちはまだまだ修業中。店の運営はオーナーの足元にも及ばない」と謙遜するが、「接客って楽しいですよ」と笑顔を見せる姿勢は、親譲りなのだ。
そんな二世夫婦を見守りながら、圭司さんは「これからはもっと感性を磨いて、新しい挑戦をしたい」と意欲を見せる。このアクティブさは今に始まったことではなく、圭司さんと久子さんは40代のころから毎年家族で海外旅行に出かけ、見聞を広めてきた。「コンビニオーナーは広い視野を持ち、社会を知ることが大切」、そんなメッセージとも思える。
「人生、年齢やキャリアに応じた働き方ってあると思うんですよ」
商売という道に、定年はない。

SHOP DATA
セブン-イレブン溝の口店
住所
神奈川県川崎市高津区久本1-2-5
特徴
1977年3月31日オープン。コンビニ黎明期から試行錯誤を
重ねて成長。現在は2012年8月オープンの「セブン-イレブン
川崎溝の口中央店」を含む、2店舗を経営