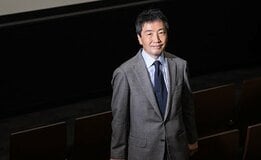【Vol.12】あらゆる問題が「見えるようになる」ために いま求められるリベラルアーツの学び/阿部温子教授
国家を超えた枠組みがつむぐ
国際関係に着目
畑山:リベラルアーツ学群の学群長でもある阿部先生。専門は政治学、国際関係論とのことですが、どのような研究の道を歩んでこられたのですか。
阿部:私が学生時代を過ごしたのは、まさに冷戦構造が目の前で崩壊していく時でした。1987年に東京大学に入学し、1989年に法学部3年生で専門を選ぶ際、いったん「私法コース」に進んだのですが、6月に天安門事件、11月にベルリンの壁崩壊のニュースを目の当たりにし、「政治コース」への変更を決めました。高橋進先生(ヨーロッパ外交史・国際政治)のゼミでドイツ政治について、塩川伸明先生(ロシア政治・比較政治学)のゼミで東欧について学んでいた4年生の頃には、湾岸戦争も起こりました。そんな時期に、鴨武彦先生(国際政治・安全保障・国際統合論)が、当時のヨーロッパ共同体(EC)について書いている論文を読み、「国家」という枠以外の共同体について興味を抱きました。
畑山:卒業後は、ケンブリッジ大学に留学されたのですね。
阿部:1991年秋、開設されたばかりの「ヨーロピアン・スタディーズ・コース」に入りました。そこで「貿易を主体とした日欧関係」について研究するうち、国家や共同体以外にも、地方や企業といったレベルでの交流が、国際関係の形成に影響していることを知りました。当時、日本の自動車企業が北イングランドの斜陽の町に工場を作り、好評を博しました。日系企業が雇用を創出し、地域文化に対して敬意を払い、地域復権をサポートしていたんです。「EC対日本」で貿易摩擦が問題になる一方で、日本企業からの駐在員がウェールズ語を習い、代わりに折り鶴を教えるといった交流があった。それは、貿易摩擦のフェーズを変えるものだったと感じます。国家に視点を置いた構図だけでは見落としてしまう、そういう点に関心を持ちました。


畑山:国よりも、もっと細かいレベルで関係が深まっていたのですね。それからは、どんな研究を。
阿部:モノが動く、カネが動くことは、すなわちヒトが動くということ。しだいに「ヒトの移動」、つまり移民研究に関心が移っていきました。最初の単純なきっかけは、「外国で学んでいる、いまの自分は移民なのだろうか」という自らへの問いでしたね。国際関係学会に出向き、そこからはドイツや英国の移民政策を調べていきました。日本でも、「移民」という言葉は使わなくても、その問題は潜在的に存在していました。5世代、6世代にもわたる在日コリアンがいるのに、日本国籍を自動的には得られないのです。そうやって移民問題を見ていくと、どうしても「国家」という単位で割り切っていくことに無理が生じていると思うのです。
畑山:無理が生じていると言うのは?
阿部:民主主義では「意思決定」への参画が広く開かれているはずなのに、「外国人」である移民は国籍を変えない限り、そこに参加できない。それなのに、国単位で決められたことに翻弄されてしまう。特に、移民で、女性で、家事労働に従事する人たちは「三重苦」で、意思決定から排除されています。そうなると、ジェンダーのこともしっかり勉強しなければならない。今、自分の関心のキーワードを拾っていくと、「政治」から「国際関係」、「移民」、そして「女性」になっています。
リベラルアーツの学びで
諸問題を自分ごととして捉える
畑山:僕も先生と同時期の1992~97年、米国に留学していました。構造主義が崩壊し、ポストモダンを経て、当時は何もかも不透明な時代。そして先生の今のお話を聞くと、まさに80、90年代から現在に続く、民主化、国家、国を超えたコミュニティ、人種といった諸問題は、経済・政治・文化のアプローチからすべて対応できますね。
阿部:冷戦構造が崩壊した当時、先がどうなるか不透明でも、まだ希望を抱く風潮があったと思います。ところが、今回のロシアによるウクライナ侵攻で、歴史が戻ってしまった。特に、政治的な意思決定をする人たちの戦略が、国境という枠を超えて、他のところまで視野に入れていくことに対応しきれていない。ずっと昔から、経済は国境では切れないと言われていますが、政治はまだグローバルになりきれていないのです。
畑山:なるほど。そして次に、リベラルアーツ教育についてもうかがいたいと思います。桜美林大学のリベラルアーツ学群が掲げるのは、学際的思考を駆使し、優れた分析・表現力をもって社会貢献を行う、国際性を有した「自立した学習者」を育成することです。遥か昔は、教養を積み、さまざまな学問分野を会得した人が社会を良くしていく、というような側面がありました。ところが科学という手法が出てきて以降、科学的アプローチであらゆる真理を発見できるとして、学問が細分化されていきました。人文学領域でも、例えば「言語学」が「言語科学」になりましたよね。現代で「リベラルアーツ」というと、どうしても「大学人としての共通教育、教養教育」と見られることが多いですが、学群長として、どんな思いでリベラルアーツ学群を捉えていますか。
阿部:学生が関心を持った問題について、さまざまな角度から取り組むことができ、また、それらの視点を総合することができている。それは社会の中で「市民」として生きていく時、とても頼もしい力になると思うんです。例えば、科学の恩恵を受け、私たちの生活が成り立っているいっぽう、その負の部分について見過ごすことはできない。わかりやすいテーマで言えば原発問題ですね。自分たちの問題として「見えるようになる」ためには、リベラルアーツによって養われる、複合的で多面的な問題へと取り組む力が役に立ちます。

科学に政治、生命倫理。
あらゆる事象に向き合い、行動を起こす
畑山:「他人ごと」でなく「自分ごと」で捉えていくことが重要だと。
阿部:リベラルアーツ学群の「統合領域」という新しい13プログラムでは、科学分野について取り組む「科学コミュニケーション」という専門プログラムも加わります。「文系だから」「数学が苦手だから」と避けてしまいがちですが、人文・社会領域から入ってきた学生にこそ、科学分野での問題に、どう目を向け、取り組むか考えてほしい。教員陣も、自分の専門だけに凝り固まっている姿勢を見せてはいけないと思っています。私もかつて、「自然理解」という講義で、「生きること、老いること、死ぬこと」というテーマに、生命倫理のトピックをたくさん盛り込みました。中絶の問題、介護、いわゆる「安楽死」。そういったものを「自分ごと」としてどう捉えるかが重要です。
畑山:生命倫理と言えば、まさに今年、米連邦最高裁が、「中絶は憲法で保障された権利」とした1973年の「ロー対ウェード判決」を全面的に破棄しました。
阿部:意思決定がなされるには、やはり政治です。「どういう問題として生じているのか」「社会で何が起こっているのか」に対する関心を持って、疑問を持った際には実際に動かなければいけない。米国だったら、デモや投票行動で「参加」をすることで、本当に良い方向にも悪い方向にも変わり得る。そういった時に、まさにリベラルアーツ的な学びが活きてくるんです。
畑山:たしかに、米国では銃規制をめぐる時にも同様でしたが、キャンパスの中で政治的なトピックに対するレスポンスがとても速いし、大きい。日本の学生は遠い話として聞いているかもしれないけれども、そういう点に関してはリベラルアーツに啓蒙性がありますね。いま世界で起きている、あらゆる事象に即した学びです。最後に、学群長としてのこれからの展望をお聞かせください。
阿部:2021年度に新カリキュラムが始まって以降、初めて、2023年度から学際的に学ぶ「メジャー(主専攻)」と「マイナー(副専攻)」両方を必修とする学生が登場します。新カリキュラム改革の一つの成果として、学生たちの関心がバランス良く、多種多様になるようサポートしたい。先ほどもお話ししましたが、新しくできる「統合領域」プログラムの、特に理系的な分野についても、魅力を高めていきたいですね。また、学んだ知識を活かして社会貢献につなげる「探究サービスラーニング」の科目についても、内容を洗練すべく、力を尽くしていきたいと考えています。


阿部温子
桜美林大学 リベラルアーツ学群 学群長
1991年、 東京大学法学部 (政治コース) 卒業。1992年、University of Cambridge Faculty of History M. Phil. in European Studies 修士課程修了。1997年、University of Cambridge Faculty of History Ph.D. in International Relations 博士号取得。米国ジョージ・メイソン大学でアシスタント・プロフェッサーとして教鞭をとった後、日本学術振興会特別研究員(ポストドクター)として筑波大学に在籍。2000年、桜美林大学国際学部専任講師、2018年、桜美林大学リベラルアーツ学群領域長。2021年4月より現職
文:加賀直樹 写真:今村拓馬
桜美林大学について詳しくはこちら
このページは桜美林大学が提供するAERA dot.のスポンサードコンテンツです。