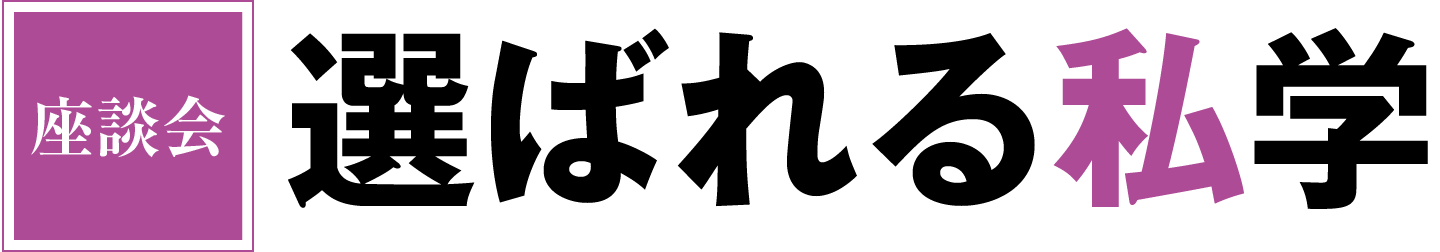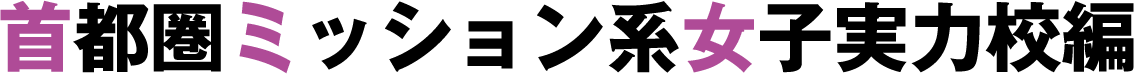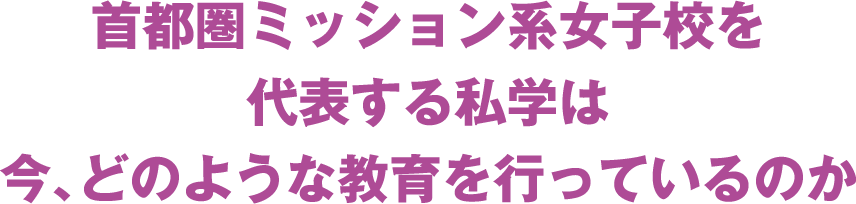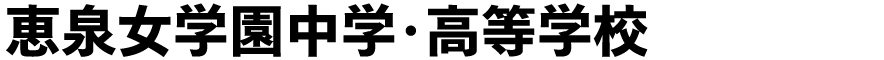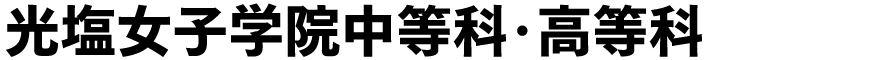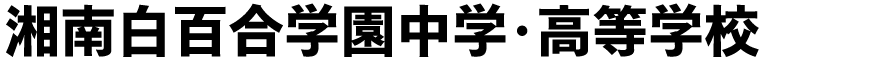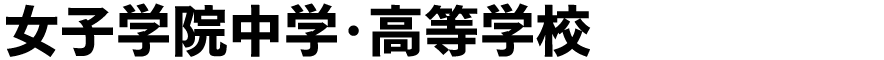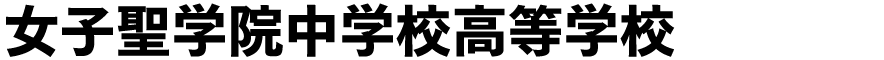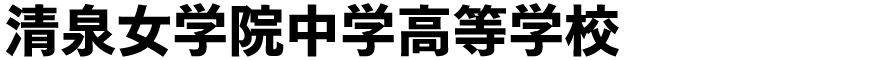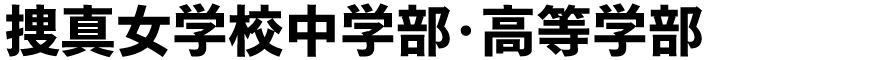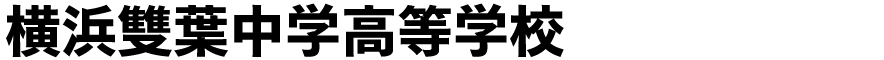キリスト教主義の学校は創立以来「1人ひとりが特別な存在」という信念のもとで、生徒を慈しみ育ててきました。変化の激しい時代にあって、今、ミッション系の学校が注目されています。

アルカディア市ヶ谷7階「雲取」(2025年5月12日)

監修/森上展安
森上教育研究所
代表

司会/高橋真実
森上教育研究所
アソシエイト

恵泉女学園
中学・高等学校
校長 本山 早苗
もとやま・さなえ

光塩女子学院
中等科・高等科
校長 烏田 信二
からすだ・しんじ

湘南白百合学園
中学・高等学校
校長 岩瀬 有子
いわせ・ゆうこ

女子学院
中学・高等学校
院長 鵜﨑 創
うざき・はじめ

女子聖学院
中学校高等学校
副校長 山本 真実
やまもと・まみ

清泉女学院
中学高等学校
校長 小川 幸子
おがわ・さちこ

捜真女学校
中学部・高等学部
校長 島名 恭子
しまな・きょうこ

横浜雙葉
中学高等学校
校長 木下 庸子
きのした・ようこ
今に続く教育の理念
1人ひとりを大切に

司会:高橋
Q1
学校の理念、女子教育の特徴などを教えてください。
本校は宣教師ではなく、一人の日本人女性の河井道が創った、プロテスタントの学校です。教育理念は「神を恐れ 人を愛し いのちを育む」。世界に目を向けて平和を実現する女性となるため、自ら考え発信する力を養うことを教育の使命としています。一人ひとりの個性を大切にするのが創立以来の校風で、本校には制服がありません。生徒は自由闊達に伸び伸びと過ごし、自分の考えを発信する力が育っています。本校の特色として、園芸の授業があります。いのちを育てる園芸は平和と協働の象徴であり、本校の心の土壌となっています。

本山
(恵泉女学園)
本校の校名は聖書から引用しています。「あなたがたは世の光。あなたがたは地の塩」の、光と塩をとって命名されました。教育理念もその一節に関連させて、「そのままのあなたがすばらしい」と掲げています。女子校は異性の目を気にすることなく、生徒が伸び伸びと過ごせる場所です。本校の生徒は友達を認めあい、穏やかで優しい雰囲気を持っています。また性差による役割分担がないため、主体的に活動しています。

烏田
(光塩女子学院)
本校の起源は330年前、フランス・シャルトル郊外の村でルイ・ショーヴェ神父が「貧困を抜け出すには教育を」との思いから、白百合学園の設立母体であるシャルトル聖パウロ修道女会を創立したことに始まります。「愛ある人として」という教育の指針は、今の湘南白百合学園にも受け継がれています。フィリピンの子どもたちへ文具を贈るボランティア活動など、建学の精神を日常で実践しています。女子校ならではののびのびと挑戦できる環境や、ロールモデルとなる先生・先輩の存在、発達段階に応じた女子教育のプロがそろっている点も本校の大きな強みです。

岩瀬
(湘南白百合学園)
本校は1870年、ジュリア・カロゾルスによって築地の居留地内に建てられたキリスト教のプロテスタント校です。建学の精神である「しっかりとした教養を身につけ、社会で活躍できる女性を育てること」は、今でも受け継がれています。入学式の時には新入生に「あなた方が女子学院を選んだのではなく、一人ひとりが神様に選ばれてここにいる」と語りかけています。学校の方針として自主自立を大切にし、生徒の活動に対して、教員からの干渉はほとんどなく、多くの行事が生徒の自主的な運営のもとに行われています。

鵜﨑
(女子学院)
女子聖学院は1905年に、バーサ・F・クローソンによって築地の宣教師館に設立されました。今年で120周年を迎えます。現在はJR山手線駒込駅近くの緑豊かなキャンパスで生徒たちは伸び伸びと過ごしています。建学の精神を「神を仰ぎ人に仕う」と掲げており、礼拝をもって一日が始まります。学校生活はもちろんのこと部活動の合宿などでも毎朝の礼拝は欠かしません。キリスト教に初めて触れるという生徒も多いのですが6年間で自然と習慣となり、自由登校期間になった高3生の中には、「礼拝に参加したい」と、わざわざ出席する生徒もいます。思春期の中学生は、難しい時期でもありますが、礼拝を通して自分を受け容れられるようになります。そして「自らの言葉で発信して行動を起こし、社会に貢献する人」を育む土台を作っていきます。本校は学校行事が盛んで、運動会が大いに盛り上がるのも女子校ならではですね。行事は生徒が運営し教員はサポートに回っています。リーダーの高校生の姿を見て、中学生は「いずれ自分も」と思うようです。

山本
(女子聖学院)
本校はスペインの修道会が作った学校です。校舎は戦国時代の北条早雲が築いたとされる玉縄城の跡地に建てられ、高台にあって見晴らしが良く緑豊かなキャンパスです。本校の特徴は「歌声が響く学校」。毎朝聖歌を歌い、中・高各々の合唱祭があります。クリスマスにはハレルヤコーラス、入学式や卒業式にはロッシーニの合唱三部作、創立記念日には、創立者、聖ラファエラ・マリアを讃える「麦の賛歌」を歌います。修道会のシスターにとって、海を渡って日本に来るのは大変なチャレンジだったと思いますが、その思いを引き継ぎ、本校は「チャレンジャーであれ」が今年の教育目標です。教育理念は、創立者の聖ラファエラ・マリアの「周りの人の幸せのために働くことが本当の愛」という言葉が、生徒の心にしっくり馴染むようです。進路も、いかに社会に貢献できるか考えて決めるように話します。女子教育の良さは、活発な生徒も大人しい生徒も居場所があること。女性教員が多いので、ロールモデルとして出産や子育てをしながら働く姿を見る、いい機会になっています。

小川
(清泉女学院)
捜真は1886年、アメリカ人女性宣教師が横浜山手で7人の少女に聖書や英語を教えたことに始まります。横浜市神奈川区の一番高い所にあるので西に富士山、東にはスカイツリーを臨めます。校名は真理を捜し求めるという意味で、その「真理」とは「学問の真理」「人生の真理」にあたると考えています。生徒には、「一人ひとり神様から与えられた人生の使命があり、その長い旅のなかに中高の6年間があるのですよ」と伝えています。私自身の言葉として教育理念を「良き市民」と捉え直し、「社会に出たとき、捜真での学びを生かして世の中に貢献しようとする意識を持ってほしい」と語っています。御殿場に自然教室という宿泊施設があり、毎年そこで2泊3日過ごすのが、生徒の絆を強める大切な行事です。「捜真ファミリー」という言葉が使われるのですが、家庭的な雰囲気の中で、生徒たちは安心して自分のやりたいことを見つけ、それに向かって進んでいます。

島名
(捜真女学校)
本校は1900年に創立されたカトリック校です。修道女として初めて来日した、マザー・マチルドによって創立されました。国内に5校、世界16ヶ国に姉妹校があり、隣接するインターナショナルスクール「サン・モール・インターナショナルスクール」とも、課外授業や部活動などで交流しています。教育方針を、すべての人が「かけがえのない独自の価値観を持った存在である」とし、「人と世界、未来をつなぐ」ことを教育目標に掲げています。朝の祈りでは、ガザやウクライナで起こっていることなども含め、生徒と一緒に平和について祈ります。生徒自身がクラス目標を作ったり、学園祭を運営したりするなど、活動的です。女子校は行事の準備も運営も、すべて自分たちでやらなければなりません。大学に進学した卒業生が「役割に、男女差があることに驚きました」と話していましたが、男性女性としてではなく、人間として成長できるのが女子校のよいところですね。生徒たちは“よい意味で”たくましく育つのではないでしょうか。本校の生徒も強く、しなやかに育っていると感じます。

木下
(横浜雙葉)
ネットワーク生かし
多彩な国際交流

司会:高橋
Q2
探究やグローバル、高大連携は、学校教育において重要な位置を占めています。御校の特色ある活動は。
礼拝の時に、生徒が感じたことを話す「感話」は本校の伝統です。全校生徒が1年に3回担当し、生徒は何を伝えようか真摯に考え、原稿用紙3~8枚程度につづります。この感話が、恵泉の探究活動のベースといっても過言ではありません。その延長上に、2月に行う一日修養会があり、「共に生きる」を大きなテーマとして、中1の「私」から徐々に広げ、高2は世界について考え議論します。高3の8月には清里で2泊3日で行う修養会があります。今まで過ごしてきた友と語らい、自身を振り返って、希望する進路に向かう決意を固めます。本校は特色である園芸と共に、理科好きの生徒も多いですね。中3の探究実験では、グループに分かれて実験から発表まで生徒主体で行います。3月のサイエンスデーには東京理科大学の先生を招き、中学生が数学や脳科学の講義を受けました。その後大学訪問もしています。日本新聞協会主催の「いっしょに読もう!新聞コンクール」では、5年連続東京都優秀学校賞を受賞し、東京私学中高協会の「英語スピーチコンテスト」では、昨年度高校暗唱の部で1位を獲得しました。生徒の活躍を見ると、本当に頼もしいですね。国際教育は、多様性を受容する恵泉の基本姿勢です。本校は英語教育に定評がありますが、短期や中期の留学制度も整っており、カナダやオーストラリアだけではなく、シンガポールなど、アジアのプログラムもあります。

本山
(恵泉女学園)
探究活動は中1からスタートします。生徒1人ひとりが各教科から深めたいテーマを設定し、中3ではSDGsに関連させて学びを深めます。活動の後はプレゼンをしたり、中学3年次にポスターセッションを行ったりしています。また、水曜日の6時間目を利用して任意の特別講座を開いており、そのひとつ「国際NPOの活動に参加してみよう!」では、アフリカのマラウイに住む子どもたちを支援するNPO法人「せいぼ」の協力のもと、親睦会(バザー)でチャリティーコーヒーを販売したりしています。他にも「図表を読む」「日経ビジネスを読む」「声学を学ぶ」「目指せ!図形女子!」など、普段の授業では扱うことのできない学びを取り入れ、生徒の知的好奇心に応えています。国際はオーストラリアの短期研修、同国とニュージーランドへのターム留学を導入。今年はターム留学に12人が参加する予定です。サイエンスは、中学生は教科書だけでなく数多くの実験を行い、実験後は必ずレポートを記します。夏休みには希望生徒対象に「ものづくり選手権」が開かれ「ストローを使って、高くて丈夫な塔を建てる」などのテーマに、試行錯誤しながら取り組んでいます。高2の理数探究基礎は数学、理科、情報の教科横断の授業で課題を設定して研究します。高3の理系生物選択の希望者を対象にバイオテクノロジーの実験を行ったりもしています。これらの研究活動は大学と提携し研究をサポートしてもらい、発表の講評にも参加してもらいます。

烏田
(光塩女子学院)
本校では、高大連携がとても盛んで、現在8つの大学と協力関係を築いています。東京学芸大学とは、数学科の授業研究を継続しており、今年で7年目になります。昨年度からは、全教科を対象に授業研究を実施し、その振り返りや指導もお願いしています。上智大学とは、同じカトリック校というご縁もあり、タイへのスタディツアーに参加しています。医療系では、北里大学、順天堂大学、昭和大学医学部と連携し、医学部ガイダンスでの講演や大学ツアー、キャリア教育としての講座などを実施しています。また、お茶の水女子大学の研究所とは、地元・江ノ島の自然の観察を通しての探究活動や、中3で1年かけて行う「環境」をテーマにした探究活動で「テーマ設定」の段階で専門的な指導を受けられるのもありがたいです。東京農業大学とは、オホーツクキャンパスでの2泊3日のプログラムに参加して大自然に触れる体験や、藤沢市の街づくり課と農大とコラボした探究活動など、ユニークな学びを展開しています。さらに、近隣の中高一貫校とも連携した取り組みも増えてきました。こうした地域や他校との協働も、新たな学びを生み出していますね。授業の中でも、中1から高1までは週2時間、高2では週1時間、教科の枠を越えた「探究の時間」で、生徒たちは答えのない問いに向き合い、自ら課題を見つけ解決に向かう力を育んでいます。高1・高2では自由にテーマを設定して中学で培ったスキルを活かして論文を執筆したり、作品を制作したりしています。また、本校のグローバル教育は、語学力の育成はもちろん、多様な価値観に触れながら国際的な視野を広げていくことを大切にしています。中1から国際教育プログラムを用意し、高1では全員がアメリカ、マルタ島、国内研修のいずれかを選んで海外研修に参加しています。中3でのターム留学や短期留学に挑戦する生徒も多くいます。

岩瀬
(湘南白百合学園)
1日の始まりとなる礼拝は、内省し深く考える大切な時間でもあります。短い時間ですが、神様の前で自分と向き合います。ほかにも、週1時間の聖書の授業や、中2のごてんば教室、高3の修養会、有志参加の春の修養会などがあります。学校をあげて探究活動を行っているわけではありませんが、生徒たちは常に考える習慣がついています。授業や行事を通して多くの話し合いを持ちます。結論を得るというよりも他者の意見を知り、考えを深めることを目的としています。国際プログラムは特に設けておらず、個人の留学は認めています。海外大学へは毎年数名の生徒が進学しており、学校としてもできる限りのサポートを行っています。高大連携に関しては、京大などの出張授業を受けたりしていますが、連携にまでは至っていません。生徒は各自で大学の研究室を訪ねたり、コンテストに個別に応募したりします。数年前は生物学オリンピックで日本代表になり、海外の大会に出場した生徒もいました。また、カリフォルニア大学バークレー校の村山斉教授から宇宙創生の話を聞き、当時中学生だった生徒が刺激を受けて素粒子を研究し、高2の時に高校生チームの一員として、スイス・ジュネーブにある欧州原子核研究機構(CERN)で開催された国際素粒子実験に参加しました。アジア・アフリカ週間では、現地で活動しているNPO法人の方から話し聞き、献金をして継続的に支援をしています。多くの卒業生がさまざまな分野で活躍しており、在校生もその影響を受けて自ら行動を起こしています。

鵜﨑
(女子学院)
女子聖学院の探究は、自分の問いを出発点に、他者と学びを深める6年間です。中学では教科横断型の学びを通して身近な関心を広げ、問いを立てる力を育みます。高校では少人数ゼミで社会と向き合うテーマを掘り下げ、調査・対話・発信の力を養成します。自分自身と誠実に向き合いながら、他者との関係性の中で視野を広げ、自分らしい言葉で世界と関わる姿勢を育てていきます。国際教育は、英語を「思いを伝えることば」として位置づけ、ネイティブと日本人教員による連携授業で、段階的に英語で発信する力を伸ばしていきます。海外研修はカナダ、英国、オーストラリアの3ケ国で、短期からターム留学、1年間の長期留学のプログラムが用意されています。海外の24校の国公立・州立大学への指定校推薦制度があり、利用する生徒もいます。高大連携は、東邦大学看護学部や芝浦工業大学と連携し、生徒が専門的な視点に触れ、将来のキャリアを主体的に考える機会となっています。またユネスコスクール・キャンディデート校として、隣にある姉妹校の男子校と一緒にSDGsをテーマにした実践的な活動なども行っています。

山本
(女子聖学院)
本校の授業は65分です。ディスカッションやグループワーク、プレゼンが多いので、その時間が必要なのです。探究活動は中3年次に「My Story Project」を実施。2年から準備を始め、1年かけて探究し、作品を仕上げたりスライドを作って年度末に発表します。ほかにも世界遺産検定を目標に世界遺産や環境について学んだり、校内模擬国連を運営し、校外や海外の模擬国連に参加したりする生徒もいます。タイで開かれた模擬国連では、ベストポジションペーパー賞を受賞しました。また本校生徒がAI倫理会議を立ち上げ、他校の生徒と、AIの進歩に伴い発生する倫理的な問題について話し合っています。24年度にはゲストスピーカーとして、河野太郎デジタル大臣(当時)を招きました。議論の内容は内閣府に提出しています。倫理の時間は、教員が工夫して現代の中高生に合ったプログラムを作っています。たとえば中1は「友達が少ないのはよくないことなのか」話し合い、中2、3年の異文化理解がテーマの時は、イスラム教の方を呼んで、日本でイスラム教信者が生きて行くうえで不便なこと、受けた差別などを話してもらいました。高3は命について考えます。命のコマーシャルを作るというアクティビティーでは、殺傷処分にされてしまう犬猫、マイクロプラスチックを取り込んで命の危険にさらされる海洋動物などを取り上げ、いろいろな視点で考えていましたね。

小川
(清泉女学院)
探究や高大連携は、広い世界を知る上で大切なプログラムと考えています。自ら行動できることがキリスト教教育の特色と捉え、「奉仕する」「関わる」「探究する」「行動する」の4つを「SEED(種)」として表しています。生徒たちは、アジアに絵本を届ける、子どもホスピス、子ども食堂など、自主的にボランティア活動を行っています。2000年には当時の生徒が「カンボジア学校建設運動」を立ち上げ、ピートゥヌー小学校の校舎を建設しました。それ以来交流が続いており、現地ではカンボジアの内戦の凄惨さを学ぶプログラムもあります。またウクライナを支援するため卒業生がポーランドに立ち上げた「ASAGAO」と連携し、勉強会を開いたり、文化祭の売り上げの一部を寄付したりしています。高大連携では現在13大学と教育協定を結んでおり、大学教授に来ていただいたり、研究室を訪問したりしています。科目履修生として、大学の授業を受けている生徒もいます。海外研修ではカンボジアのほかオーストラリア、マレーシアなども訪問します。パナマやコスタリカなど、様々な地域に留学する生徒がいます。訪問するだけでなく、オーストラリアやオランダなど毎年多くの留学生を受け入れています。

島名
(捜真女学校)
探究は総合学習として「関係性の創造」をテーマに、6年間一貫して行っています。例えば東日本大震災後も支援を続けるNPOに同行して、東北地方を巡ってサポートしたり、身近な所では子ども食堂、横浜港に着岸する外国船船員の方々の支援なども行っています。また毎年カンボジアを訪れ、内戦の跡を見たり、スラム街での支援活動を続けています。理科は、学園が豊かな自然に覆われているので、中学生は植生を観察。豚の心臓の解剖など、実験や実習も多く、授業は反転学習を取り入れ、ディスカッションやプレゼンテーションが豊富です。クラブ活動も盛んで、新聞部は県コンクールで表彰、演劇部は県大会に出場、かるた部は関東大会出場など、表彰されました。運動部もバレー部が県大会出場、テニス部が横浜ブロック団体7位、ハイキング(登山)部が全国大会出場と活発に活動しています。

木下
(横浜雙葉)
どの大学を選ぶかより
「どう生きるか」を大切に

司会:高橋
Q3
女子校ならではのキャリア教育や進路指導はどうされていますか。
憧れの先輩をロールモデルとして、先輩から学校生活や進路について、卒業生から大学での学びやキャリアの話を聴く機会がとても多いです。高2の3月に行われる卒業生による進路相談会には毎年60名近くのOGが訪れます。高2・3年生は科目選択制で、希望進路に応じた柔軟なカリキュラムを組むことができます。高3生になると進路面談も頻繁で、一対一の小論文や過去問指導にも細やかに応じています。

本山
(恵泉女学園)
キャリア教育は中1から体系的に行います。中1は身近な大人から「働く」ことをテーマしたインタビューを実施。そのなかから6人程度にお願いして、学校で講演してもらいます。中2はNPO法人「16歳の仕事塾」から派遣された講師の話を聞きます。中3は専門家による講演を行うとともに、社会問題に目を向けて、ボランティア活動を行います。高1は卒業生による講演会やキャンパスツアーを通して、大学や学部学科を幅広く選んでいきます。高2は卒業生が来校して大学ガイダンスを実施し、進学先の大学を絞り込んでいきます。

烏田
(光塩女子学院)
進路指導は「生徒がよりよい人生を生きるためのサポートである」と位置付け、学期ごとに面談し、高1からは進路選択と具体的に進学に向けた指導を行っていきます。受験期には志望理由書や小論文の添削、面接の練習などをきめ細かく指導をしています。

岩瀬
(湘南白百合学園)
学校側から具体的に進路を指示することはありませんし、校内では模試も行っていません。しかし学校にはデータの蓄積があるので、個別面談でそれを利用して指導します。どの大学を受けるかという目先のことよりも、将来何をやりたいのか、考えてもらうようにしています。

鵜﨑
(女子学院)

アルカディア市ヶ谷7階「雲取」(2025年5月12日)
なかなか進路を見出せなかったり、気持ちが勉強に向かわなかったりする生徒に関しては、丁寧に面談を行っています。キャリア教育として、卒業生が来校し自身の体験を在校生に語ってくれます。進路指導は「どう生きたいか」を共に考え、一人ひとりの声に耳を傾け、納得の行く道を探っています。

山本
(女子聖学院)
キリスト教の学校は、6年間で、将来どう生きていくのか、見つけることが大切な目的だと思います。学校は、生徒がやりたいことを見つけたら、教員が全力で応援するというスタンスです。

小川
(清泉女学院)
人生の目的を果たすための進路選択を大事にしています。学びたいことや行きたい大学が明確な生徒が多く、総合型選抜で良い結果を出しています。進路指導は複数の教員が一人の生徒をサポートする体制で取り組んでいます。

島名
(捜真女学校)
本校では「何をするか」より「どう生きるか」に重しを置き、6年間をかけて考えさせます。先輩の講話が与える影響が大きいようで、いろいろなキャリアのOGに来てもらい、語ってもらっています。高2より進路別コースに分かれ、キャリアガイダンスを開きます。理系が増えており、医学部は今年26人が合格しました。患者さんの立場に立って治療にあたるお医者さんになって欲しいです。

木下
(横浜雙葉)
AI全盛時代こそ
見直される心の教育

司会:高橋
Q4
AI時代に教育はどうあるべきか。最後に受験生や保護者へのメッセージをお願いします。
AIは膨大なデータの集積ですが、学校は、未知のことにチャレンジして失敗できるところです。失敗を恐れず、どんどんチャレンジしてほしいです。AIを上手に活用しながら、一人ひとりの賜物を活かして、全ての人にとって平和でより善い社会を創り出す人に育って欲しいと思います。神に愛されている者として、自分自身をまず大切にし、他者への共感力をもった人間味あふれる人を育てる学園でありたいと思います。

本山
(恵泉女学園)
AIに関しては、大きな変化に対する不安が強調されているように感じます。太古の昔から現代まで、人類は変化を繰り返してきました。今はその時期であり、不安だけではなく新しい文明の利器を喜ぶ事も大事だと思います。インベンション(発明)が積み重なって新たなイノベーション(変革)が生まれます。大事なことはどんな時代にあっても、自己肯定感を持ち、次に向かって学んでいくこと。希望を持って、未来へ進んで参りましょう。

烏田
(光塩女子学院)
いつの時代にあってもキリスト教教育の学校として、他者のために何ができるのかという視点を持ちたいと考えます。AI、テクノロジーの時代には、自己肯定感、主体性、協働性、共感力といった非認知能力(生きる力)こそが、AIにはできない人間の強みとなっていくと思います。ご家庭ではお子さんの頑張りを褒めて、道しるべを一緒に見ながらお子さんの横で伴走して進んでいただきたいと思います。

岩瀬
(湘南白百合学園)
AIは過去のデータから将来を推測することは得意ですが、今見えていないこと、予測できないことを考えるのは苦手です。それをやるのが、教育の技だと思っています。生徒の今の姿だけを評価するのでなく、隠れてもいるものを引き出すことが我々教員の使命です。特にキリスト教学校においては、信仰であるとか、感性であるとか目に見えていない物を大切にし、育てていきたい。AIは今の世の中で必要なものですが、うまく共存していきたいですね。

鵜﨑
(女子学院)
AIは便利な道具ですが、大切なのはどう使いこなすか。共存の知恵と人間らしい感性が問われる時代です。だからこそ、女子聖では対話や実感を伴う学びを重ね、多くの体験を通して自分を深めてほしいと願っています。VUCAの時代にあっても、生徒一人ひとりが自分の賜物を見つけ、それを人生の軸として歩めるよう、教員が支えていきます。

山本
(女子聖学院)
AIが人間のやることを肩代わりするようになると、「人間はどういう存在なのか」という、根本的な問いに立ち帰ります。倫理観や価値観が問われ、「どのように生きていくのか」というキリスト校の理念が大切にされる時代だと思います。人間性を大事にする教育が、ますます重要になっていくのではないでしょうか。

小川
(清泉女学院)
AIが発達すると、今の仕事の半分はなくなると言われてきましたが、教育はAIがどんなに発達してもなくならないと思います。教育は目の前にいる生徒に対する思いがあり、人の思いを理解するのが大事な分野です。キリスト教の学校は、これからの世の中でますます必要になるのではないでしょうか。生徒が自己肯定感を高め、他者の存在を認められるような心の教育をこれからも続けていきたいと思います。

島名
(捜真女学校)
AIは答えがすぐ出てきますが、むしろプロセスを大事にしていきたいと考えます。答えを出すまでの試行錯誤、友人との議論、そして答えを見つけたときの喜び、これこそが教育に必要なものです。一方AIによって時間短縮が可能になるのも事実。その時間をより創造的な学習にあてていきたいですね。受験生は日々の勉強が大変だと思いますが、プロセスも大事に、保護者の方は長い目でお子さんを見守ってほしいと思います。

木下
(横浜雙葉)
本日はありがとうございました。

監修:森上

〒156-8520 東京都世田谷区船橋5-8-1 TEL.03-3303-2115
学びの特色
大学、企業、研究機関との連携を積極的に進めており、24年度は14のプログラムを実施。津田塾大学、日本女子大学とは科目等履修制度を結んでいます。理系大学との連携も盛んで、芝浦工業大学での1週間のインターンシップに参加する生徒も。STEAM講座として「生成AIを使ってSF小説」「ドローンで動画撮影」などの講座を開催。東京理科大学をはじめ、18大学の模擬講義を実施。シンガポール国立大学とはオンラインでの研修を行ったあと、現地を訪れ交流しています。



〒166-0003 東京都杉並区高円寺南2-33-28 TEL.03-3315-1911
学びの特色
光塩女子学院は1931年に、スペインのべリス・メルセス宣教修道女会のシスターが設立しました。校名のように、生徒一人ひとりをかけがえのない存在として、大切に育てています。学年全体を6~7人の教員が受け持つ「共同担任制」をとっており、1人の生徒を複数の目で見守っています。特色のある取り組みとして倫理のカリキュラムを導入。授業以外にも、国語の多読プログラム、長期休暇の英語キャンプ、社会科では新聞ノートの作成、数学科では問題を解くコンテスト(MCA)などに取り組んでいます。


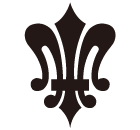
〒251-0034 神奈川県藤沢市片瀬目白山4-1 TEL.0466-27-6211
学びの特色
湘南白百合学園は、卒業までに目指したい姿として「豊かな心をつくる」「世界に通じる言語力の育成」「探究的な学びICT」「自立を育む生活」「学びの実践としての学校行事」「進路実現のための支援」「充実した理数系の学び」の7つのグランドデザインを策定。これらの7項目を基板として日々の授業、課外活動に取り組んでいます。最近では大学をはじめ、企業や医療施設、研究所などとの連携を深め、アカデミックで探究的な活動を通して、生徒たちは思考力や創造力を深めています。


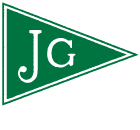
〒102-0082 東京都千代田区一番町22-10 TEL.03-3263-1711
学びの特色
女子学院では宿泊を伴う校外活動を盛んに行っています。中1のオリエンテーションキャンプから始まり、中2は「女子学院の入口」と呼ばれているごてんば教室で、ディスカッションを通して自分を見つめます。中3の東北旅行は戦前から続く伝統の行事。事前に東北の歴史、文化、自然について学習し、現地で体験します。高1は、6年かけて行う平和学習の一環として広島へ行き、原爆資料館を見たり被爆者の方から話を聞いて、学びを深めます。高3の春には、関西へ修学旅行に行き、夏には修養会を実施しています。



〒114-8574 東京都北区中里3丁目12番2号 TEL.03-3917-2277
学びの特色
女子聖学園は英語教育に定評があり、本物の英語に多く触れ、英語で思考できるようになります。まずは母国語である日本語を理解し、経験を積むことで「心を育てる英語教育」を実践しています。中学生は週に1回ネイティブ教員が2人、オールイングリッシュの授業を行います。中2、3年次にはレシテーションコンテストで、表現力を養い、高校時にはスピーチコンテストで発信力を磨きます。高2、3は選択科目に、思考力を育てる英語として「アカデミック・ライティング」を取り入れています。



〒247-0074 神奈川県鎌倉市城廻200 TEL.0467-46-3171(代表)
学びの特色
海外研修は特徴的なプログラムが用意されています。アイルランドで語学研修と姉妹校との交流、貧しい子どもたちのためにボランティア活動を行うベトナムスタディーツアー、フィリピンセブ島のカトリック校の生徒とお互いにホームステイをして異文化体験、ボストンカレッジでアメリカの大学生活を体験しつつ、アメリカ各地から参加した高校生と交流する留学など。さらにウエリントンやブリスベンなどへ3ケ月のターム留学も。24年度からは、修学旅行先の一つに台湾が加わりました。



〒221-8720 神奈川県横浜市神奈川区中丸8 TEL.045-491-3686
学びの特色
捜真女学校では教育のあらゆる場面で「ことば」を大切にしており、授業や行事の中でもアウトプットの機会を多く取り入れています。各クラスで行う礼拝の場で自分のことばで話すという機会も、自分を表現することばを養い、自分を支えることばに出合う大切な経験となります。自分のことばを身につけた生徒たちは、プレゼンテーションやスピーチなどの校外コンテストにも果敢にチャレンジし良い成績を収めています。また、総合型選抜など、ことばをいかした大学入試でも高評価を得ています。



〒231-8653 神奈川県横浜市中区山手町88番地 TEL.045-641-1004
学びの特色
海外研修も盛んで、春休みにはシンガポールとマレーシアの姉妹校を訪問(右写真)。学校で授業を受けたりさまざまなアクティビティーを通したりして、バディと深い絆でむすばれます。アメリカでは、希望者が世界レベルの名門女子大学で行われる夏期英語研修プログラムに参加。テーマは女性のリーダーシップで、英語で討論し最終日にはスピーチも行います。カンボジア・スタディツアーでは、現地の子どもと触れ合い、内戦の痛みを感じる中で、同じ世界に生きる仲間意識を育てる「地球市民教育」を充実させています。


※本コンテンツに記載されている会社名、サービス名、商品名は、各社の商標または登録商標です。