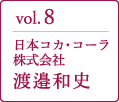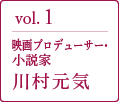文/朝日新聞出版 カスタム出版部 写真/簗田 郁子 デザイン/REGION 企画・制作/AERA dot. AD セクション


上:2019年に松山さんが描いたニューヨーク「バワリーミューラル」/下:2018年にはルクセンブルクのZidoun-Bossuyt Galleryで「No Place Like Home」という個展を開催した
キース・ヘリングやバンクシーなど、名だたるアーティストが作品を描いたニューヨークにあるパブリック・アートの壁「バワリーミューラル」。この壁に2019年9月、作品を完成させたのが松山さんです。日本での活動はほぼありませんでしたが、世界ではすでに気鋭の現代美術家として知られていました。
渡米して約20年、ニューヨークを拠点に活動してきました。僕は、アーティストの仕事は自分たちが生きている時代を可視化することと考えています。その僕が、明治神宮鎮座100周年というタイミングで作品を発表できたことを幸せに思っています。
いま、世界的にマイノリティーやジェンダーといったキーワードが注目されています。僕が取り組んでいることのひとつが、世界においてマイノリティーでもある日本特有の概念をアートという国際言語に落とし込むことです。「日本はこうだ」と特異性や個性を謳うのではなく、僕らの根底にあるアイデンティティーや要素を可視化していく感じでしょうか。
明治神宮という場所は、自然界の畏怖を感じるほどの大規模な森で、かつ100年かけて人工的に作られたという点で、世界的にユニークだと感じています。鳥居をくぐり、高い木々が並ぶ有機的な自然に入ると、身も心も清らかになります。その先に置かれた作品は、日本の文化そのものでもある神道と縁の深い鹿の角を、参道の木々をオマージュできるよう意匠的にアプローチしました。
また作品では、現代性も表現したいと考え、作品の一端には銅鏡と、現代の僕らには身近な車のホイールを見立てたものを寄り添わせました。鏡面仕上げにし、人工的なものに周囲の視線を映し出す仕掛けです。森のなかに人工的なステンレスがあるというコントラストと、万物を映すという鏡のもつ神道の哲学を融合するフィット感――明治神宮の森や日本人の身体性、精神性を表したつもりです。「我々はどういう存在なのか」をとらえてもらいたいと思いました。

これまでアートは、それぞれの時代を象徴する歴史的な出来事を、キャンバス上に可視化することで、見る者の心を奮わせるという役割を果たしてきました。世界中が、新型コロナウイルス感染症を原因とする心痛ましいニュースで溢れ、ネガティブな気持ちがどうしても勝ってしまう今だからこそ、視覚的な経験を通して、無条件に人々の心に希望をもたらすことのできるアートの真価が試されていると思います。
高校生のときは「将来の夢など抱いていなかった」という松山さん。上智大学に進学後は、授業の傍ら仲間との時間を楽しみ、セミプロとして活動していたスノーボードに情熱を傾けた。大学時代の5年間を「青春だった」と振り返る。
卒業したのは経済学部経営学科。芸術とは疎遠なところにいました。上智大学を選んだのは、父がクリスチャンでキリスト教に根ざした教育に魅力を感じたことと、キャンパスのコンパクトな感じが好きだったから。幼少期にアメリカ西海岸で暮らしていたこともあり、留学生や帰国生が多かった比較文化学部(現・国際教養学部)は「アメリカに近い」というイメージもありました。上智は第一志望だったんですよ。では、なぜ経済学部経営学科か。特に理由はありません(笑)。当時は明確なビジョンもなかったので「卒業後も“つぶしがきく”だろう」くらいに考えて受験しました。将来の夢は、大学に通っているあいだに得られるだろう、と。

入学後は、いろいろな授業を楽しみながら受けましたね。印象に残っているのは、キリスト人間学。「人とは何か」「宗教とは何か」などの講義は非常に貴重でした。福島章先生の犯罪心理学の授業など、人気のある授業も受講しました。
授業を受ける傍ら、当時の僕はスノーボードのセミプロとして活動していました。大学が休みの期間には、企業のスポンサードを受けて海外遠征もしていたんです。スノーボードに本格的に挑戦するため、4年次には1年間、休学もしています。
ただ、休学しているときも毎日のように学校へ行くほど、大学が好きでした。当時入っていたサークルの友だちに会いに行ったり、四ツ谷駅の掲示板にある友だちからの伝言をチェックして駅近くの飲み屋へ行ったり。キャンパスがコンパクトだから、行けばすぐに知り合いに会えた。兄も上智の法学部にいたので、キャンパスに愛着があったんです。あのアットホームな感じが好きでしたね。僕の青春の場所です。
結局、けがをきっかけにスノーボードを諦めたのですが、復学しても就職活動はしませんでした。ちょうど僕らの世代は学生ベンチャーの草創期で起業する同級生も少なくなかったので、影響を受けましたね。僕は「何かを表現する」仕事につきたいと考え、スノーボードが表現のスポーツであったことをきっかけに興味をもったデザイン、ものづくりを勉強してみようと、アメリカへの留学を決めました。

アーティストとして活動し始めたころの松山さん
Photo by GION
大学卒業後にニューヨーク屈指のアートスクールへ進学した松山さんは、デザインを学ぶなかでいまにつながる道を見つける。
アーティストになろうと決めたのは、25歳のときです。「アーティストになるために海外へ行く」のが普通だとしたら、順序が逆ですね。でも、それが個性になった部分もあります。ニューヨークは新しいものを受け入れる土壌がある一方、人種のるつぼであり、さまざまな差別的な壁もある。そんな場所で、かつアートとは違う分野を歩いてきた僕は、「自分のアイデンティティーは何か」を考える毎日を過ごしました。小さいころからアートに親しんでいないからこそ、アートというフィルターを通して僕あるいは僕ら日本人をどう表現できるのかを試行錯誤したのです。
アートは、作り手からの問いかけでもあります。作品を見た人に、何を考えてもらうか。皆さんも「何だこれ?」という作品を見たことがあると思います。その疑問符は、分からないからこそ知ろうとする証拠。作品にヒントがあれば、それを元に暗号を解析するように考えて自分なりの答えを導き出す。知的好奇心に対しての挑戦、アートのそうした側面に魅了されて、自分の作品をギャラリーや美術館で発表する「アーティスト」になったわけですが、まあ、どうやったら食べていけるかわからない。だから最初は「お店の壁に絵を描かせてほしい」とニューヨークの街を頼んで歩くなど、いろいろな方法を探りながら、少しずつ作品で生計を立てていったんです。
経済学部を卒業して、アーティストになる。まったく脈絡がないようですが、僕のなかではすべてつながっています。英語でいうところのディシジョンdecision(意思決定)ではなくトランジションtransition(移行)。一つひとつ――上智大学に進学して、スノーボードでけがをして、デザインを学んで、と、無関係に見える点と点がつながって今があるのです。それがどれか一つでも欠けていたら、今は違うことをしていたと思います。
僕の学生時代は、情報を自分で獲得しにいく必要がありましたが、それがよかった。今はインターネットで情報がすぐに手に入ってしまいますが、実際にそこへ行ってはじめて見える景色があります。だから今の若い人には、インターネットやメディアを介して見たものを「経験した」とは思わないようアドバイスしたいですね。僕はニューヨークで暮らすようになって、そこに見えない壁――文化の壁、言語の壁、人種の壁、肌の色の壁があることを知りました。そこにどう切り込んでいくかが、今も課題です。そんな挑戦が、誰でも普通にできるようになればと願っています。「苦労は買ってでもしろ」とは古臭い言葉かもしれませんが、かけがえのない経験、若いときにしかできない経験をしてほしいですね。大学生活は、その原点になるはずです。
提供:上智大学