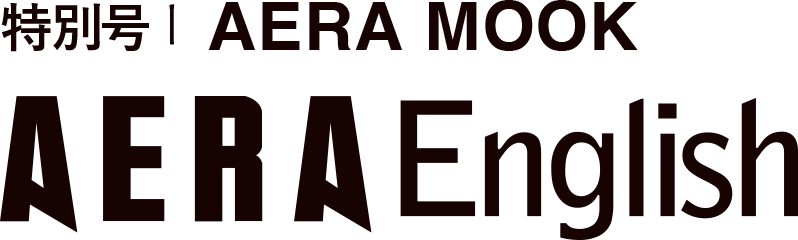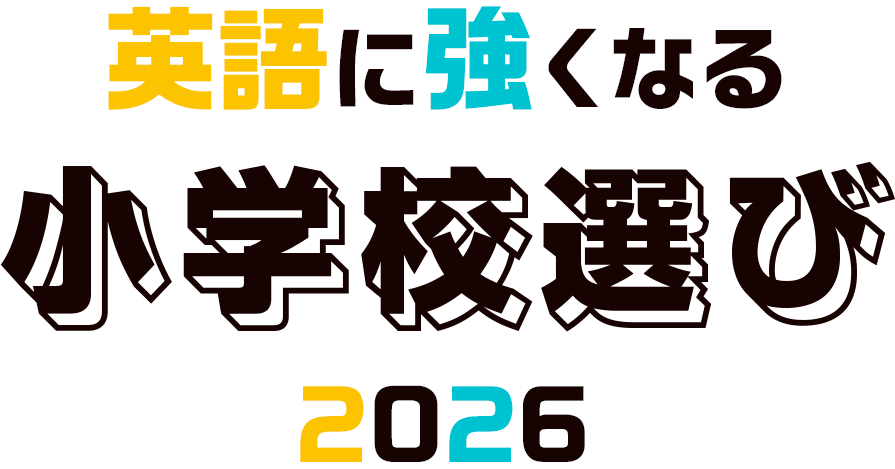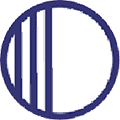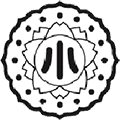賢い私立小学校選び
英語教育に力を入れる小学校が増加。カリキュラムには細かな違いがあり、子どもに合うかどうかの見極めが大事
わが子に合った私立小学校を選ぶポイントについて、
小学校における英語教育の専門家である上智大学の藤田保教授に聞きました。

- 上智大学言語教育研究センター
センター長・教授藤田 保 - ふじた・たもつ/1963年東京生まれ。
上智大学外国語学部比較文化学科卒業。同大学院外国語学研究科言語学専攻博士前期課程修了。立教大学異文化コミュニケーション学部教授などを経て、現職。
私立小学校では
特色のある英語教育が可能
NHKが文部科学省に取材したところによると、数学や社会などの授業を英語などの外国語で行っている小中学校は2025年4月時点で16都道府県49校(うち小学校は26校)。いずれも私立で、2020年(27校)の約2倍となっています。(※出典)
学習指導要領の改訂により、公立の小学校でも「外国語活動」として3年生から英語が必修化されています。私立小学校ではより、特色のある英語教育が可能であることから、この点が小学校選びの一つのポイントとなってくるでしょう。
国が英語教育に力を入れる理由は、広い視野を持ち、積極的に外国語を使える能力を子どもたちに身につけてほしいからです。保護者の時代には必ずしも必要がありませんでしたが、グローバル化が進んだ現在ではそうではなくなっています。
世界中の人とオンラインでつながることが可能になり、企業では国境を越えたプロジェクトが数多く実施されています。
インバウンドは年々、増えており、地方の観光地にも外国人がたくさんやってきます。英語が向こうからやってくるような環境なのです。
※出典:NHK( https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250615/k10014835911000.html )
下手な英語でもいい
相手に伝わる力を評価
英語を聞いたり、話したりが流ちょうにできると、人生の選択肢が広がります。現在の小学生が社会人になる2040年頃には、さらに少子化が進み、日本の産業が衰退していく可能性も指摘されています。英語ができれば、外資系企業で働くことはもちろん、日本から海外に出て行くという選択もできます。つまり、グローバルな視点で働く環境を選ぶことができるのです。この頃にはAIによる自動翻訳の精度もかなり高くなると思われますが、だからこそ、AIでは難しい、リアルで深い会話ができる人材が求められるでしょう。
このような時代に身につけるべき英語力は、ネイティブのような発音や、正しい文法にこだわって話すことでもありません。下手でも、多少の間違いがあっても自分の話したいことを相手にきちんと伝えられるようにすることです。もちろん、相手の意見もしっかり聞くことのできるリスニング力とその土台となる知識も必要です。そのためには覚えてから使うのではなく、「使いながら覚える」という態度が不可欠です。
これは自転車の練習に例えられます。子どもに自転車の乗り方を教えるとき、自転車の構造をマスターするまでは乗ることができない、となったら、いつまでたっても乗れるようになりません。途中で乗ることをやめてしまう子どもも多いはずです。そうではなく、乗りながら覚える。膝小僧をすりむくこともあるかもしれませんし、最初はヨロヨロ運転ですが、短期間で乗れるようになります。私立小学校の一部で行われている英語によるイマージョン教育やインターナショナルスクールへの進学などはまさにこの、乗りながら覚える方法といえます。
もっとも、すべての子どもにイマージョンやインターが向くとは限りません。シャイなお子さんには、伝統的な英語学習のスタイルのほうが合うこともあります。
保護者と小学校の
信頼関係が重要
英語教育のカリキュラムは小学校ごとに細かな違いがあります。さらに私立小学校は学校ごとに建学の精神や教育理念などがあります。共学・別学、また、附属の中高があり、12年間一貫教育が可能なところもあります。
小学校受験を主導するのは保護者です。どのような学校が自分のお子さんに合うかをよく検討するといいでしょう。ホームページなどで小学校の情報を入手するだけでなく、説明会に足を運び、校長先生から教育方針をじかに聞くことも大事です。実際の授業を見たり、体験授業などを通して、お子さんが楽しんでいるかを見ることも、選び方のポイントになります。
最近は授業の半分以上を英語で行う私立小学校も増えてきています。講演会などで、保護者からは、「小さい頃から英語ばかりやっていると、日本語がおろそかになるのでは?」という質問をいただきます。しかし、そのような心配はいりません。
「氷山の一角」という表現があります。これは氷山のように、目に見える部分は全体のほんの一部で、その下にははるかに大きな部分が隠れていることを示す比喩です。
言語の習得を行う脳も似たようなもので、日本語と英語という別々の入り口(山)があるようにみえても、頭の中では一つの塊(脳=「共通基底言語能力」)としてつながっています。つまり、複数の言語を学んでも混乱が生じないように脳では処理ができているのです。
例えばカナダには英語とフランス語、2つの公用語が、スイスでは4つ、インドに至っては20以上もあります。しかし、これらの国で子どもの頃から複数の言語に日常的に触れていても、それによる問題は生じていません。
私は小さい頃から他の国の言語を知ることが、むしろ母語である日本語への理解や気づき、さらには観察力につながると考えています。例えば「英語は本が複数になるとbookから『books』になるけれど、日本語にはこうした表現はないな?なぜだろう」と発想が広がります。
現代の英語教育は保護者の時代のそれとは大きく異なります。その点を理解することが大事です。また、子どもが無事、小学校に合格したあかつきには、教育方針を信頼し、学校に対して必要以上に不安を抱かないことも大事です。
子どもの教育が成功する要因の一つに、保護者と学校との信頼関係があることがわかっています。保護者の皆さんには、子どもを信じて温かく見守ってあげてほしいと思います。