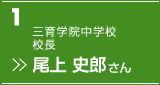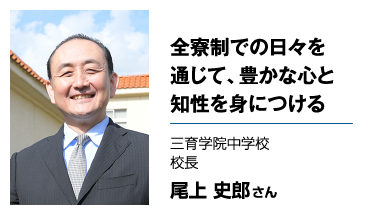西野悠基さんは、アメリカのカリフォルニアで医師への道を歩んでいる。小学校から高校卒業まで、濃厚な時間を送ったのは三育学院だ。プロテスタント系キリスト教を柱とする学びの庭で力を注いだのは勉強だけではない。野球とバイオリン演奏、聖歌隊の活動にも励み、タイムマネジメントの力や互いを思いやる心、英語力や国際性も育まれた。そして今、三育学院で手にした生き方の指針を誠実に貫ける医師になりたいと考えている。
アメリカ生活はもう10年近くになる。研修医として勤務する病院では「ケヴィン」の名で親しまれている。ニックネームではない。西野悠基さんはこう種明かしをする。
「アメリカでのフルネームは『Kevin Yuki Nishino』なんです。私も卒業したカリフォルニア州のロマリンダ大学で両親がともに医療を学び、同大の病院で生まれたからです。私が今働いているのもその病院なんですが、アメリカで生まれたので、国の法律に従ってアメリカの国籍をもっています」
5歳までアメリカで過ごし、日本に帰国して以降は三育学院で成長を続けた。東京三育小学校、茨城県にある北浦三育中学校、広島三育学院高等学校で、計12年。全寮制の中学と高校では勉強だけでなく、洗濯や掃除も自分で行った。
親元を離れ、寮生活を始めた中学入学当初は心細さがあった。ホームシックのような寂しさも感じた。ただ、同じ小学校の先輩たちの存在が頼もしく、不安はすぐに消えた。結局のところ、夏休みに実家に帰っても「早く学校に戻りたいな」と思えるほど楽しい時間を過ごせた。
キリスト教プロテスタントのセブンスデー・アドベンチスト教会が設立母体となる学び舎での記憶をたどるとき、真っ先に思い出すのはそれぞれの興味が多岐にわたっていたことだ。
「自分が所属していないスポーツを自由時間に友だちとしたり、広島の高校では全校生徒の半分以上が聖歌隊のメンバーになっていたり。私自身は中高と野球部だったんですが、友だちとサッカーやバレーボールをしたり、弦楽部でバイオリンを弾いたり、男声アカペラの活動もしたりしていました。のびのびとした環境で、さまざまなことに関心を示す先生や先輩、友だちから刺激を受け、『自分ができること』の幅が広がった実感があります」
楽譜が読めなくても、ピアノが弾けなくても、「やりたい」と思えば聖歌隊には入れた。能力以上に意志を尊ぶ学風が肌に合った。みんなで練習を重ね、関東、関西、沖縄をめぐってクリスマスコンサートを行い、賛美歌を響かせた感動は今でも忘れられない。
三育学院は中学、高校ともに全寮制を展開している。一部屋に3、4人で過ごすかたちが基本だ。“部屋民”と呼ばれるルームメートは異学年で構成される。
12歳のときに親元から巣立ち、学校の仲間たちと共同生活を送る。起床は6時。礼拝を捧げ、全員で食堂で朝食を食べ、授業に臨む。放課後には夕礼拝を行い、夕食をとったあとに約2時間の自習時間を過ごし、中学生は21時半、高校生は22時に消灯する。べらぼうに規則正しい毎日だが、息苦しさは全くなかったという。
「朝食後や夕食後に少し余裕がありますし、うまくやりくりして自分の時間をつくっている生徒が多かったですね。空いた時間に部活以外のスポーツを楽しんだり、アカペラの練習をしたり。高校生になると、下級生にとっては先輩の影響が大きかったと思います。全体の起床時間より早く起きて受験勉強に励む先輩の姿には、やはり刺激を受けますよね」
自身も「タイムマネジメントの力がついた」と感じている寮生活は、「いい意味でも悪い意味でも逃げられない」環境だった。同級生や“部屋民”と常に顔を合わせる状況で、距離が近いがゆえにいさかいが起こる場面も少なくなかった。
ただ、本気で向き合ったからこそ絆は揺るぎないものになった。 結束が強まり、互いを思いやる心が育まれた。西野さんは野球部員同士で机に向かった時間を思い出し、懐かしそうに顔をほころばせる。
「中学と高校の寮生活で、自習時間などに野球部の先輩後輩で勉強を教え合ったのは忘れられない思い出の一つです。それから、消灯後に暗くなった部屋で“部屋民”の先輩が『中1のときはこういうことを意識したほうがいいよ』とか『部活は頑張ってる?』とか、優しく気づかってくれたのもうれしかったですね」
お互いにいたわり合った12年間で、生き方の指針が決まった。西野さんが三育時代も今も、そしてこれからも心に刻むのは「誰かのために身を尽くす」という信念だ。どんなときも、「受けるよりは与えるほうが幸いである」「だから、何事でも人々からしてほしいと望むことは、人々にもそのとおりにせよ」という聖書の二つの教えが、自らの行動規範になっている。
世界中に系列校がある三育学院では、英語力も磨かれた。
小学1年生から英語にふれ、広島三育学院高では国際英語コースに進学。英語で他教科も学ぶコースではアメリカの英語の教材を使い、たとえば日本語ではどちらも「自分は行くつもりだ」と訳される「I will go」と「I'm going to go」の微妙な違いを習うなど、実践的な英語も教わった。高校2年生の夏休みから5カ月間続いたニュージーランドへの短期留学でも、英語力が鍛えられた。
「ニュージーランドでは三育学院の系列の高校に通い、現地の高校生と英語で議論する授業など、貴重な経験を積みました。最終的に国際英語コースで一緒に学んだ20人の半分以上は海外の大学に進学したので、高校の3年間は一定の英語力と国際性、あるいはグローバルに生きるうえで不可欠な論理的思考力が身につく環境だったと思います」
自身はアメリカのパシフィック・ユニオン・カレッジに留学し、小さなころからふれ合ってきた音楽を専攻した。同時に日本の大学院にあたる医学部への進学をめざし、必須の化学や有機化学、生物や物理といったサイエンス系の主要4科目、生化学や生理学などを受講。4年間の大学を卒業したあと、両親の母校でもあるロマリンダ大学の医学部で勉学に励んだ。
今は自分が産声を上げたロマリンダ大学病院の研修医1年生だ。もともとは父と同じ外科医を志していたが、医学部で実習を重ねるなかで路線変更した。
病気と治療に関する患者の宗教的理念と真摯に向き合う先生。「故人の妻である日本人女性がつらい思いをしているのに、自分は彼女とうまくコミュニケーションがとれていない気がする」と言って、精神的ケアの支援を西野さんに求めてきた先生。内科医の先生方の姿勢に感銘を受けた。病気だけでなく患者の心にも気を配り、お互いに一人の人間として何度も会話を重ねる医療のほうが、自分が追求する生き方に合う気がした。
「単に傷や痛みを治すのではなく、患者さんの人生そのものに寄り添える医師になるのが目標です。いずれは帰国し、体だけでなく、その人の心や生きる姿勢をしっかりと見つめ、献身的なケアを施す全人的な医療を日本で広めるのが自分の使命のようなものだと感じています」
こう話す西野さんの心には、「受けるよりは与えるほうが幸いである」「だから、何事でも人々からしてほしいと望むことは、人々にもそのとおりにせよ」という聖書の二つの教えが刻み込まれている。
提供:三育学院中学校