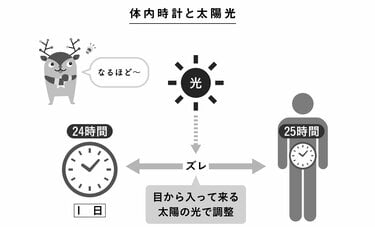垣間見える、地球の巨大なエネルギー。それは今後、大噴火につながるのか。
「正直なところ、まったくわかりません。今回のような小規模の噴火がダラダラと続く可能性はありますが、エスカレーションしないとも言い切れません」(長井さん)
火山の地下には「マグマだまり」があり、マグマがたまってくると地上の地形も膨らんでくる。噴火の兆候をとらえるため、地上に置いたGPSの観測機器などで地形のかすかな変化を観測するが、本土から遠い離島では必要な範囲に機器を設置することが難しい。噴火した後に岩石を採取し、初めて何が起こったのかが検討できるのだという。
多くの島民が亡くなった噴火も
伊豆諸島の最南端「青ケ島」では、1785年に発生した噴火で島民の約4割が亡くなった。生き残った人々は「八丈島」に避難し、青ケ島は半世紀にわたって無人島となった。1902年、鳥島は大噴火し、全島民が亡くなっている。
活発な火山活動が継続する硫黄島には自衛隊が駐留している。噴火の規模が拡大した場合、退避を迫られるだけでなく、その影響は他の小笠原の島々の暮らしにも及ぶ。本土での治療が必要な救急患者が発生した場合、海上自衛隊は硫黄島からヘリコプターを往復させて患者を運び、さらに航空機で本土に搬送している。昨年の搬送実績は、のべ1000回を超えた。
大規模な噴火が起こったとき、島の生活はどうなるのか。
小笠原村役場では、硫黄島の噴火の話題が出ることはあるものの、自衛隊機を使った救急搬送は通常どおり運用されているという。
村役場の担当者は話す。
「この件について、東京都からも特に連絡はありません。ただ、もしもというときはどうなるか。何とかしていただきたいという思いはありつつも、答えようがありません」
(AERA dot.編集部・米倉昭仁)
 米倉昭仁
米倉昭仁