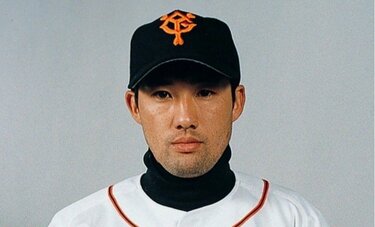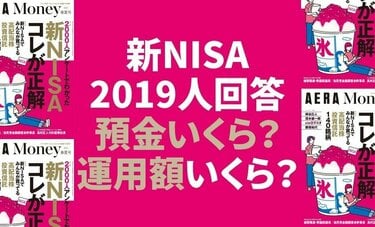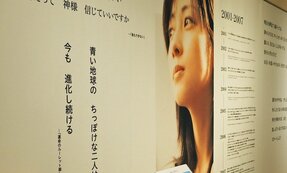大林の映画は東日本大震災を境に変わりました。「映画でしかできないことを撮る」と言っていた彼が、「この空の花─長岡花火物語」からは、自分の戦争体験を伝える、描くようになりました。私の東京大空襲の体験も入れてくれました。黒澤明監督の言葉の通り「映画で未来を平和にしてほしい」という思いがこもっていたと思います。
私が作品の良しあしを判断する基準にしていたのが、スタッフの言葉です。映画でしか表現できないことをやるのが好きだった監督でしたから、撮影中にスタッフもキャストも「どうなるのだろう?」と思うわけです。そして、初号を見るとみんな「こうなるんだ」と納得する。彼らも映画の喜びや技術的なことを学んだり感じたりするんでしょうね。だから、「また監督につきたい」と言ってくださる。「恭子さん、次いつやるの?」。それが私のバロメーターでした。
でもね、60年以上一緒にやってきて私にとっては一度も「えぇ(どうしてこれを撮るの)?」という作品はなかったんですよ。脚本を読むと私なりのイメージができますが、いつも思っていた以上のものができあがった。彼の作品に裏切られたことがないんです。だから私、「すごいよね、あなた」って遺影に向かって言っちゃうの。それはとっても幸せだったと思います。できることならあと2作撮らせてあげたかった。思い入れのあった福永武彦の「草の花」と檀一雄の「リツ子その愛・その死」。それができなくなってしまったのは残念です。
監督からはたくさんのことを教えてもらいました。例えば人との接し方。お願いした小道具が意に沿わないものだったとしても、一度は必ず褒めるんです。その後に「こういうやり方があるよ」と伝える。その姿勢は最初から全然変わりませんでした。
亡くなる10日くらい前から毎晩途切れ途切れではあるんですが、講演でもしているのか「皆さん、ありがとう」って言うんです。おもしろいのがその後、「はい、3、2、1、カット」って。撮影中なのねと思いました。しばらくして休むのかなと思う頃に、今度はポソッと「恭子さん、ありがとう」って毎晩言ってくれました。出会った時から変わることのないやさしい人でした。
 坂口さゆり
坂口さゆり