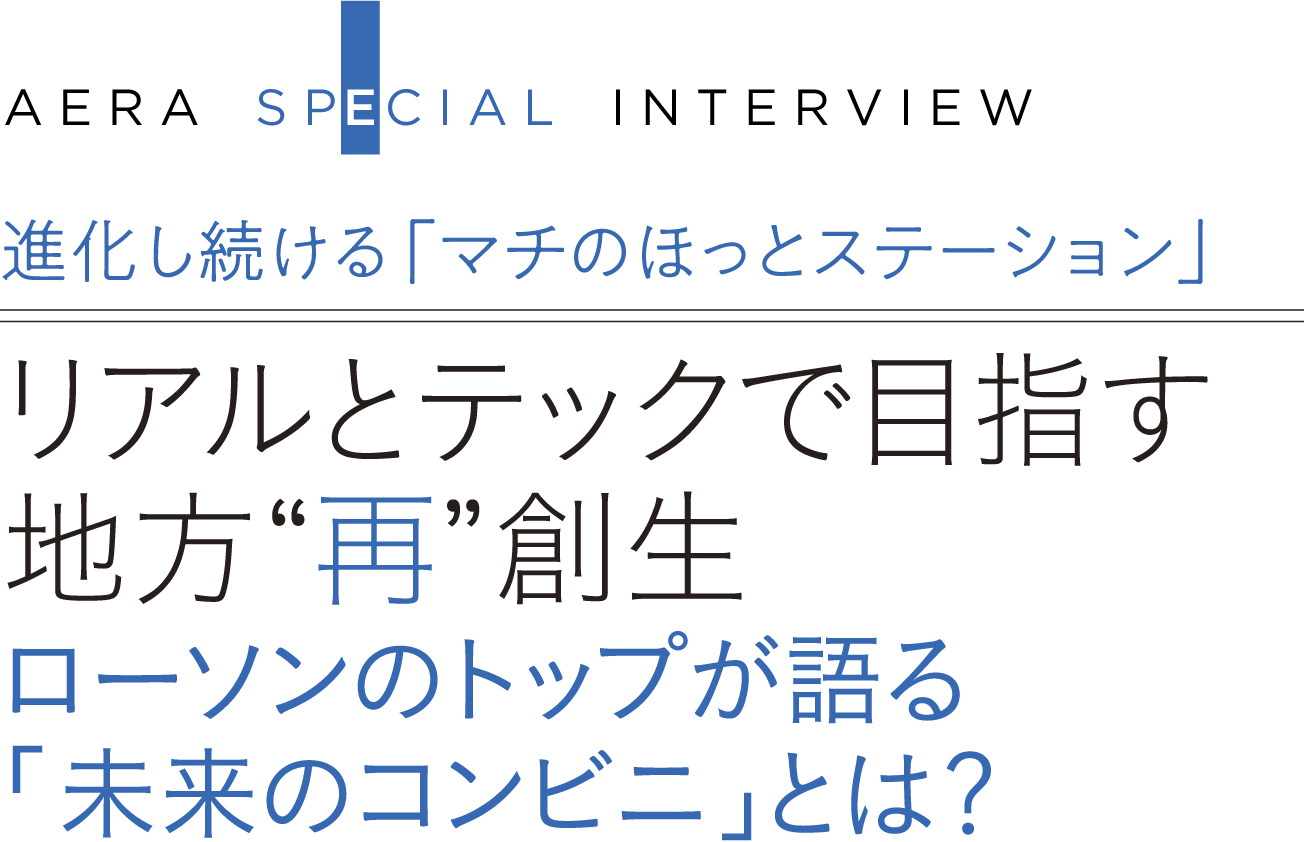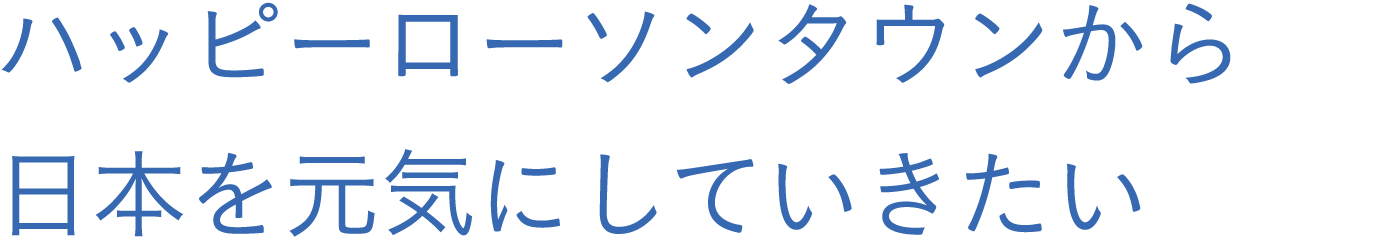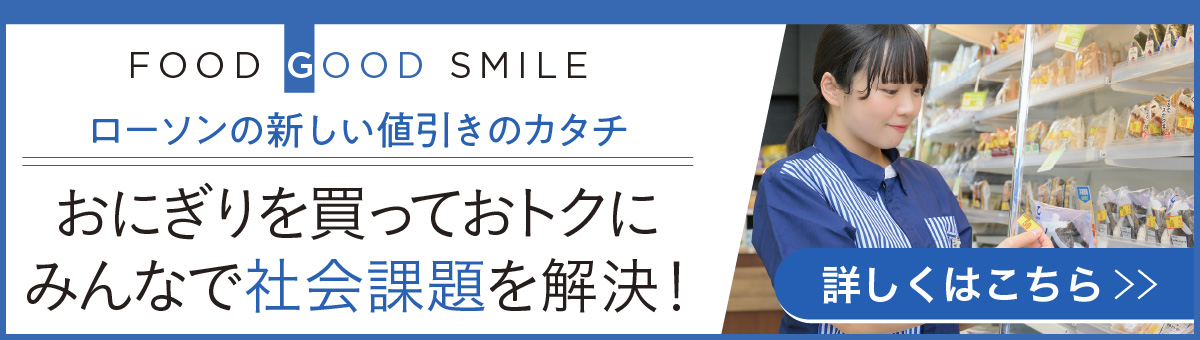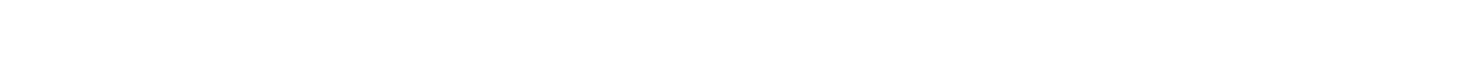
〈PR〉

地域社会の課題解決に取り組んでいるローソン。テクノロジーを駆使した「Real×Tech LAWSON」について、
竹増貞信代表取締役社長がAERAブランドプロデューサーの木村恵子と対談した。
また次頁では、食品ロス削減プログラム「FOOD GOOD SMILE」についても紹介する。
文/安楽由紀子 撮影/篠塚ようこ デザイン/スープアップデザインズ
制作/朝日新聞出版メディアプロデュース部ブランドスタジオ 企画/AERA DIGITAL AD セクション

Sadanobu Takemasu
竹増 貞信
株式会社ローソン 代表取締役 社長
1969年、大阪府出身。大阪大学経済学部卒業。93年、三菱商事入社。畜産部、グループ企業である米国豚肉処理・加工製造会社のIndiana Packers Corporation(出向)、広報部、社長業務秘書などを経て、2014年にローソン代表取締役副社長に就任。17年3月から現職。本誌で「コンビニ百里の道をゆく」を連載中。
木村 本日お伺いしたこのローソン高輪ゲートウェイシティ店(東京都港区)は、未来のコンビニ「Real×Tech LAWSON」1号店として、今年6月にオープンしたそうですね。どのような店舗なのかお聞かせください。
竹増 最新のリテールテック(小売業におけるデジタル技術)を盛り込んだ店舗です。ローソンは今年、創業50周年を迎えました。少子高齢化や地域社会の課題が深刻化するなかで、従来のスタイルのままでは店舗の維持が難しい時代が近づいています。リアル店舗の温かさを維持し、さらに発展させていくために、ロボティクスやデジタル技術の活用に積極的に挑戦していきたい。2024年にKDDIと資本業務提携契約をしたことから、その技術力を活用した新しい店舗の形を模索し、この店舗ができました。この店舗でどのような温かさをご提供できるのか検証し、得られた知見を他の店舗にも展開していくことを目指しています。
木村 この店舗ではローソン初の試みが数多く導入されていると聞きました。
竹増 はい。まず、店舗に入ると占いやマチの情報を発信する「AI Ponta」とのコミュニケーションが楽しめます。商品の棚にはAIサイネージが設置されており、お客様の行動にあわせてお得な情報などを提供し、お客様の商品選択をサポートします。さらに、家計の見直しや投資、スマホの契約そのほか暮らしの困りごとを幅広く遠隔で相談できる窓口「Pontaよろず相談所」を設置し、それぞれの専門家やサービスにおつなぎしています。
木村 震災時には、コンビニエンスストアがインフラとして大きな役割を果たすことが認識されましたが、ローソンは日頃から地域住民が困ったときに力になる存在となるということですか。
竹増 そうですね。地域社会において「ローソンがあれば安心」と思っていただけるような店舗を目指しています。

AIサイネージは、AIカメラでお客様の行動を解析。
商品選択に悩んでいると、おススメ商品を表示してくれる

Keiko Kimura
木村 恵子
AERAブランドプロデューサー
木村 クルー(従業員)さんの働き方も変わりますか。
竹増 ええ、店舗での作業負担を軽減するため、飲料陳列ロボや「からあげクン」の調理ロボ、掃除ロボを導入しています。お客様のニーズが多様化し、人手不足が深刻化しているなか、テクノロジーを導入することでクルーさんのニーズにも応える必要があります。
木村 お客様だけでなく、クルーさんの満足度もよく考えているんですね。
竹増 そうですね。ただやはり我々は「すべてはお客様のために」という思いで事業を展開しています。店舗での生産性が向上すれば、より多くのお客様によりよいサービスを提供できるようになります。ローソンは、クルーさんとお客様がコミュニケーションを取りながら交流する「人間交差点」のような存在でありたいんです。すでに2022年から導入しているアバタークルーもそのための技術の一つ。店内に設置されたモニターに投影されるのはアニメーションですが、実際には人間が遠隔で接客していますので、お客様には温かさを感じていただけると思います。これは「ローソンで働きたい」という思いを持ちながらも、障がいなど様々な事情から店舗で働くことが難しい方々がチャレンジできる機会の創出にもつながっています。
木村 働き方の多様性を広げる点でも、アバタークルーの活用は有益なんですね。実に様々な課題の解決に取り組んでいるローソンですが、今後、社会に対してどのような使命を果たしていきたいと考えていらっしゃいますか。
竹増 かつて高度経済成長期に全国に建設されたニュータウン。現在は入居率が低下し、活気が失われているところもあります。その様子を見て、ローソンは商品を販売するだけでなく、地域社会のためにもっとできることがあるのではないかと考えるようになりました。例えば、提携している無印良品とニュータウンをリノベーションしたり、ローソンが手掛ける保育園や映画館のノウハウを生かした施設を開設したり、傘下の成城石井などのスーパーマーケットを誘致したり。マチ全体を変えることは難しいですが、ニュータウンにおいてローソンが持つ機能を最大限に活用すれば、活気を取り戻せるのではないかと考えています。
木村 少子高齢化、東京一極集中、地方の過疎化が社会問題となっていますが、マチが便利になれば若い世代の移住先の選択肢となるかもしれません。
竹増 はい。これが、グループ理念である「私たちは“みんなと暮らすマチ”を幸せにします。」を具現化する、2030年に向けた「ハッピーローソンタウン構想」です。一つひとつのニュータウンを活性化させることで、日本社会を活性化させたい。ローソンは「地方“再”創生」という形で社会に貢献したいと考えています。そのためにもリテールテックを活用することが不可欠です。
木村 人手が足りない地域でも、テクノロジーによって少人数で店舗を運営するということもできそうですね。
竹増 ええ、そのような店舗でも作業に追われることなく、笑顔でお客様をお迎えすることができるでしょう。
木村 ローソンはいつも新しいチャレンジに前向きですよね。
竹増 商品づくりはもちろん、こうしたサービス面においてもチャレンジする文化がローソンには根付いています。変化し続ける時代に合わせて、商品、サービス、そして店舗のあり方も進化し続ける必要があります。社員がより新しいアイデアに挑戦できる環境を整備し、社会を牽引していきたいですね。そして、お客様にとって「振り返ればいつもローソンがある」という存在であり続けたいと考えています。
木村恵子の編集後記
メディアづくりにおいても、テクノロジーと人の温かさをいかに融合させるかは課題です。双方のバランスを取りながら融合させようとするローソンの取り組みは、ぜひ参考にしたいですね。また「Real×Tech LAWSON」からさらに発展したハッピーローソンタウン構想は地域の魅力を高め、居住者の選択肢を増やすものでもあります。ローソンは、マチや人々の生き方を変える存在になると感じました。
提供:株式会社ローソン