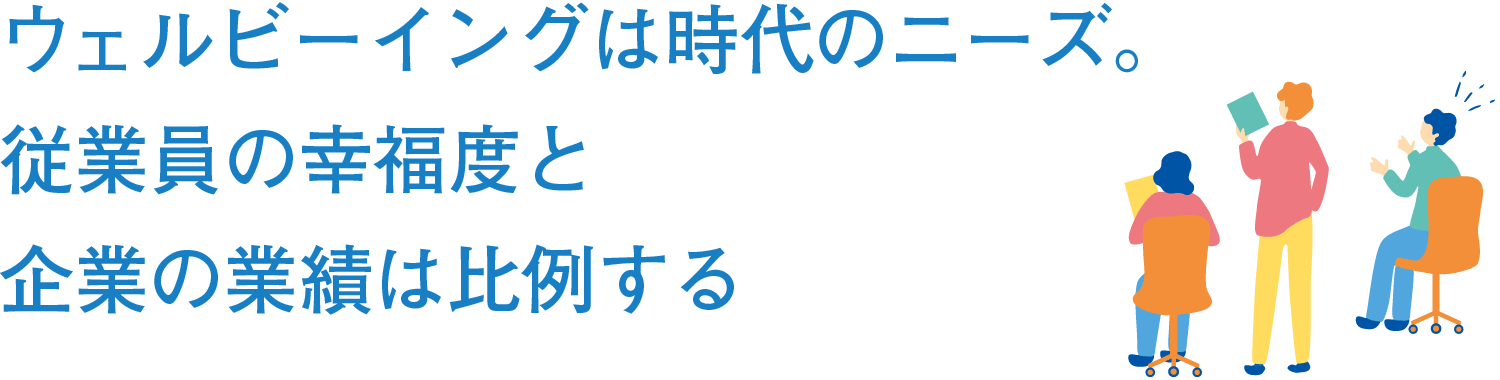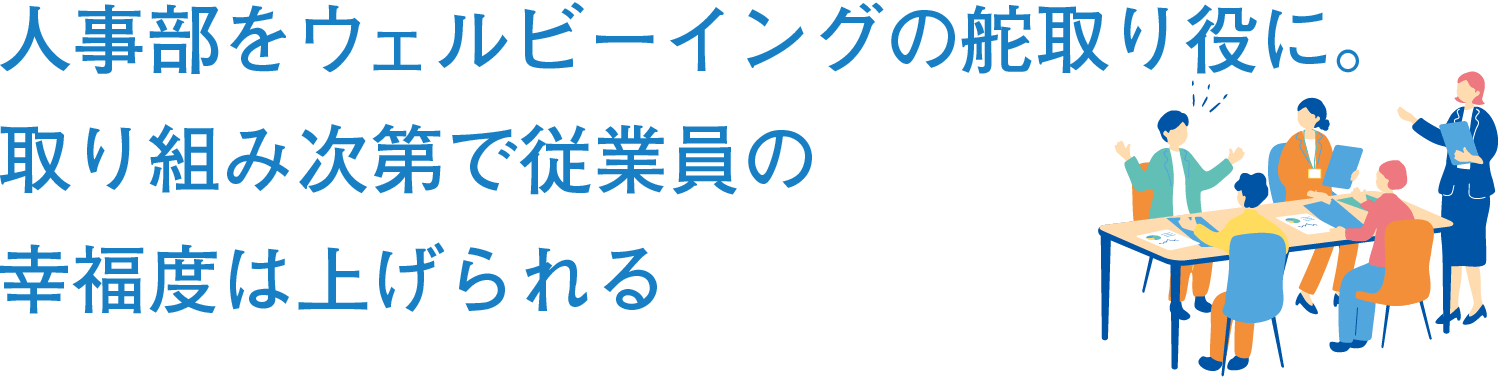働き方改革や健康経営が推進される中、注目を集めているのが企業におけるウェルビーイング。日本でのウェルビーイング研究の第一人者である前野隆司さんによると、ウェルビーイングとは「身体的、精神的、社会的に良好な状態であること」を指し、健康、福祉、幸福のすべてを包括するものだという。
「私はウェルビーイングを〝幸せ〞と訳しています。企業経営において〝幸せ〞というと、『やる気がない』『ラクしている』などと誤解されがちですが、ここでの〝幸せ〞とは、やりがいに溢れ、各人が能力を発揮できるといった広い意味での幸せな状態を含む概念を指しています。それに、『ラクしている=仕事が退屈な状態』なので、『ラク』は実は〝幸せ〞ではないんですよ」(前野さん・以下同)
近年、企業経営においてウェルビーイングが注目されるようになった背景を前野さんは次のように分析する。
「高度経済成長期からバブル期まではトップダウン型のマネジメントが適していた。画一的なプロダクトを大量生産するためには合理的に組織を回す必要があり、従業員が指示されたとおりに働く方が効率が良かったのです。しかし、時代は変わり、企業経営においても、不確実な社会の中でいかにイノベーションを起こしていくかが重視されるようになりました。そのために、トップに言われたとおりに行動する統率型の組織ではなく、各人がアイデアを出せるような創造性の高い組織が必要とされるようになったのです」

前野隆司さん
東京工業大学(現 東京科学大学)理工学研究科機械工学専攻修士課程修了後、キヤノン株式会社入社。慶應義塾大学理工学部教授、ハーバード大学客員教授等を経て、2008年から慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科教授。現在、武蔵野大学ウェルビーイング学部長・教授も兼務。『幸せな職場の経営学』(小学館)、『「幸福学」が明らかにした 幸せな人生を送る子どもの育て方』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)など著書多数
また、幸福度と労働の関係についての研究が進んだことも大きな影響を与えているという。
「幸せな人は不幸せな人に比べて3割ほど生産性が高く、創造性が3倍高いというデータ(※1)があります。また、従業員が幸せだと感じているほうが離職率は減り、企業の資産利益率が高いという研究結果(※2)もある。ウェルビーイング経営は、企業の利益アップにつながることが明らかになっているのです」
では、幸せな職場とは具体的にどのような状態なのだろうか。前野さんによると、幸せは次の四つの因子から構成されるという。
❶ 目標に向かって努力し、成長を実感できる「やってみよう!」因子
❷ 他者とのつながりによって幸せを感じることができる「ありがとう!」因子
❸ 常にポジティブで楽観的である「なんとかなる!」因子
❹ 自分らしく過ごせているかを表す「ありのままに!」因子
つまり、誰もが自分らしさを活かして前向きに取り組み、それぞれの経験・能力や考え方を認められている職場こそ幸せな職場といえる。
「ウェルビーイング経営というと、休暇や福利厚生の制度面を整えることがクローズアップされがちですが、それだけでなく、組織の在り方や風土自体を見直すことが重要だといえるでしょう」
※1 The Benefits of Frequent Positive Affect: Does Happiness Lead to Success?(Lyubomirsky、King、Diener、2005年)
※2 Jan-Emmanuel De Neve, Micah Kaats and George Ward, Workplace Wellbeing and Firm Performance, Wellbeing Research Center, Oxford, 2023
ウェルビーイング経営というと、余裕のある大企業だけのものだと感じる人もいるかもしれない。しかし、前野さんは「ウェルビーイング経営にはトップがコミットし、企業全体に理念を浸透させることが不可欠。その点で中小企業は規模が小さい分、推し進めやすい」と語る。
「たとえば、寒天を製造販売する長野県の伊那食品工業は、従業員数500人ほどの会社ですが、『会社はまず社員を幸せにするためにある』との経営方針を長年貫き、増収増益を続けてきました。それが大きな話題を呼び、日本を代表する企業からも見学者が訪れているほどです」(前野さん・以下同)
大企業であれば、人事や総務の部署が率先して動き、ウェルビーイングの仕組み作りを進めていくのも良いだろう。
「人事や総務は経営層との接点も多く、従業員の情報を集めやすい部署でもある。特に人事部はウェルビーイング経営の舵取り役として今後、企業を引っ張っていく花形部署になるのではないでしょうか。
取り組みを進める際は、同業他社の事例をそのまま取り入れるよりも、異業種での成功事例を参考にしながら自社に合う形にアレンジするほうがイノベーションが起きやすい。そのため、異業種交流会などで他の業界の情報を集めるのもお勧めです」
一方で、現場の従業員の意識改革も欠かせない。
「課長や係長であれば、まずは自分のチームのメンバーの幸福度を高めることに注力しましょう。そのための第一歩が、部下の要望や考えを聞くこと。ワン・オン・ワンミーティングを取り入れている企業は増えていますが、この時、上司はアドバイスや指示、評価を一切せずに、部下の言葉を引き出すことに徹してください。部下が日ごろ何を考えているのか、趣味は何かなど仕事以外の話題でもいいので、相手に興味を持って耳を傾けることが大切です」

もとは脳科学やロボットの研究者だった前野さん。人の心のメカニズムに興味を持ち、データやエビデンスに基づいて幸福学の研究に取り組んでいる。慶應義塾大学での社会人講座には、多様な業種の社会人が集まり、幸福学をビジネスに活かすことを目指して学んでいるという
傾聴にはコーチングのスキルが重要であり、管理職にコーチング研修を受けさせるといった取り組みも効果的だという。
自分や周囲の従業員の幸福度を知ることも大切。前野さんが開発に携わった「幸福度診断ウェルビーイングサークル」や「はたらく人の幸せ/不幸せ診断」などを使えば、オンライン上で簡単に幸福度を測定できる。
「人間ドックを受けて健康状態を知るのと同じで、どれぐらい幸せに働けているのかを知るのはとても大事。そして、健康が日々の生活習慣から成り立っているのと同じで、幸福度も取り組み次第で改善していくことができる。そして、健康を持続させれば長生きできるように、幸せファーストの組織をつくれば、利益や成長は後からついてくるのです」
一人ひとりのトライが、ウェルビーイングな組織づくりにつながっていくことだろう。