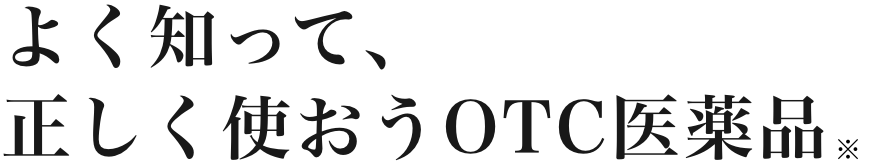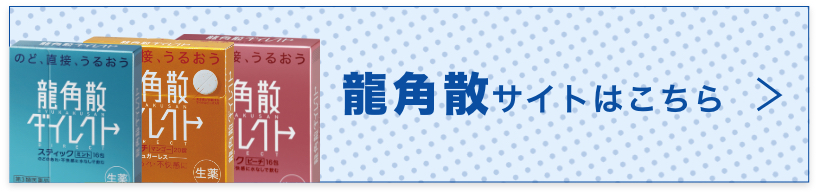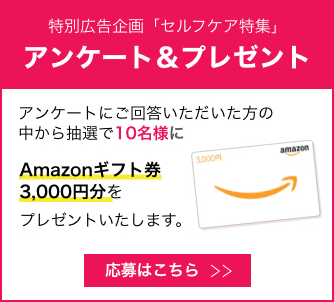〈PR〉

文/別所 文 写真/平野晋子 デザイン/アートボード 企画/AERA dot. AD セクション 制作/朝日新聞出版 カスタム出版部
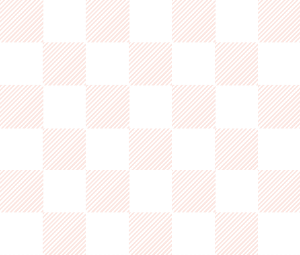
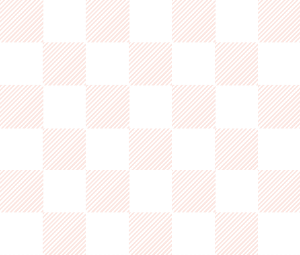
医療の第一歩は自分の体調をきちんと管理するセルフケア。その観点から、いま市販薬を用いたセルフメディケーションが注目されている。セルフメディケーションとは何か、どのように実践していけばよいのか。その重要性について、順天堂大学の富野康日己名誉教授と東京生薬協会会長の藤井隆太・龍角散社長に対談してもらった。
藤井 これまでだれも体験したことのないコロナ禍で、医療の現場は厳しい状況が続いていますね。
富野 我々医療を提供する側だけでなく、患者さんも大変です。病院に行けない、通常の治療が予定通り受けられない、感染してもスムーズに治療してもらえないのではなど、不安を抱えていると思います。日本は国民皆保険制度のおかげで、だれでも、どこででも、安価で高度な医療を受けられます。それが思わぬ形で、そういうわけにはいかなくなったのです。
藤井 私はこのコロナ禍は、受診行動や服薬行動を見直す機会ではないかと思っています。国民皆保険制度がうまく機能し続けるためには、「共助・公助・自助」が必要です。今は自助がおろそかになって、あまりにも病院やお医者さんに頼り過ぎているように思われます。先生もおっしゃっていた、自己管理、セルフケアがしっかりおこなわれているとは言えない状況ではないでしょうか。
富野 医療財政の現状を考えると、セルフケアはさらに必要になりますね。
-

-
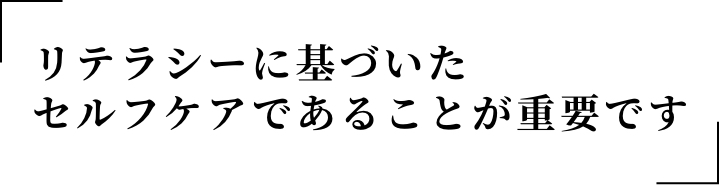
株式会社龍角散
ふじい りゅうた
藤井隆太代表取締役社長
1959年生まれ。桐朋学園大学音楽学部および研究科卒業。小林製薬、三菱化成工業(現・三菱ケミカル)を経て、94年龍角散入社。翌年から現職。日本商工会議所社会保障専門委員、厚生労働省社会保障審議会医療保険部会臨時委員、(公社)東京生薬協会会長、日本家庭薬協会副会長。フルート奏者としても活躍。
セルフメディケーションで自助に努めよう
藤井 生活習慣をきちんとするほかにも、たとえばセルフメディケーションを実践することも、自助の一つになりますよね。セルフメディケーションは最近になって提唱されていますが、日本では江戸時代から「家庭薬」の文化として根付いていました。
富野 WHO(世界保健機関)ではセルフメディケーションのことを、「自分自身の健康に責任をもち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義していますね。
藤井 日本のOTC医薬品(市販薬)は質が高いので、もっと活用してほしいと思います。ちょっとしたかぜや花粉症、消化器の症状などでは、OTC医薬品で改善がみられることもあります。
富野 処方薬と同じ成分量のスイッチOTC医薬品もありますからね。ただ、OTC医薬品でも、服用したら「お薬手帳」に記入してほしいと思います。処方薬とかぶって、倍の量を飲んでしまうような事態も起こりますから。
藤井 最近は、「eお薬手帳」などのサービスも始まっています。今後は、マイナンバーカードを医療に活用できるといいですね。乳幼児のときに受けた予防接種や、かかった病気、そこにOTC医薬品も記載すれば、データを一元化することができ、重複受診などもチェックすることができます。
富野 マイナンバーカードに抵抗を示す人もいるようですが、医療の面ではメリットがあると思います。ほとんどの人が、子どもの頃、どんな予防接種をしたかなんて覚えていないでしょう。
藤井 たとえば風疹の予防接種を受けているかどうか、いつ受けたのかなども、データ登録すればすぐにわかります。
-

-
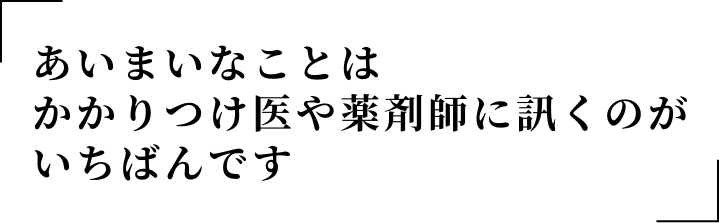
順天堂大学
とみの やすひこ
富野康日己名誉教授
1949 年生まれ。74年順天堂大学医学部卒業。同大腎臓内科教授、同大附属順天堂医院副院長、医学部長などを経て2015 年より同大名誉教授。現在、医療法人社団松和会理事長。日本腎臓学会認定腎臓専門医。日本腎臓学会・日本内科学会・日本成人病(生活習慣病)学会名誉会員。
迷ったら薬剤師やかかりつけ医に気軽に相談
富野 セルフケアやセルフメディケーションを適切におこなうためには、患者さんにはリテラシー(正しく理解して活用すること)が求められますね。
藤井 ええ、リテラシーに基づいたセルフケアであることが重要です。「セルフ」といっても、勝手にやっていいということではない。そんなことをしたら大変なことになります。
富野 まずは自分の身体の状態をしっかり把握することです。そのうえで、OTC医薬品などで対処するのか、それとも受診すべきかを慎重に判断して、適正な薬を選び、用法用量を守って服用する。それらをすべて含めてセルフケアなのだと思います。
藤井 迷ったりわからなくなったりしたら、ドラッグストアでも調剤薬局でも、薬剤師に相談すれば、適切にアドバイスしてくれます。OTC医薬品については、メーカーに問い合わせれば疑問に答えてくれます。できたらかかりつけ薬局をもつといいですね。そのほかにも、「健こんぱす」※なども上手に活用するといいでしょう。
富野 患者さん自身で情報を得ることはいいことですが、ネットの情報などは玉石混淆なので、あいまいなことは、かかりつけ医や薬剤師に訊くのがいちばんです。
藤井 情報は提供元を確認してから、得るようにしたいですね。こんな時代だからこそ、賢い患者でありたいものです。
富野 賢くセルフケアに努め、健康を維持してほしいと思います。

※医師が薬剤師と考えた市販薬アプリ「健こんぱす」(無料)
医師が薬剤師と考えたOTC医薬品を案内するアプリ。いくつかの質問に答えるだけでその症状に応じたOTC医薬品を紹介。医師と無料でメール相談できます。
https://app.medicalcompass.co.jp/lp/
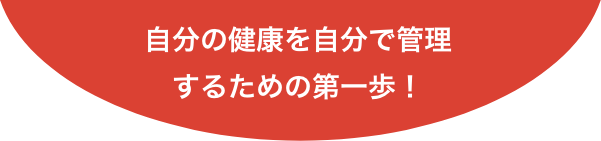
第13回 OTC医薬品普及啓発イベント
「よく知って、正しく使おうOTC医薬品」が、今年はウェブで開催中です。世界中で医療や健康への関心が高まり、自分の健康は自分で守るセルフメディケーションの考え方が注目される中、OTC医薬品の正しい知識や使い方を広く知ってもらうため、さまざまなプログラムが行われます。
※OTC医薬品とは、薬局、薬店、ドラッグストアなどで自己選択して購入できる医薬品です。OTCは「Over The Counter:オーバー・ザ・カウンター」の略で、カウンター越しに薬を販売するかたちに由来しています。
内 容
わかりやすく楽しいプログラム
専門家へのインタビュー記事/クイズ企画/「薬祖神社」の歴史/龍角散をはじめとしたOTC製薬企業によるプレゼン動画の配信等
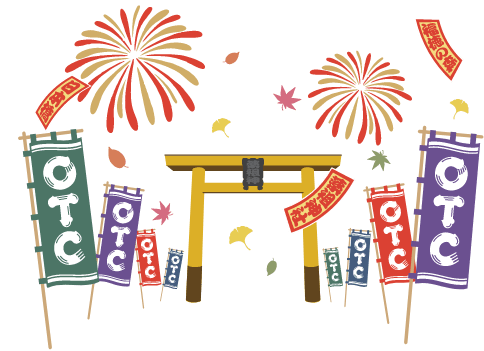
イベント動画


※「YouTube」は、Google LLC.の商標または登録商標です。
イベント特設サイトはこちら[主催]日本一般用医薬品連合会(日本OTC 医薬品協会・日本家庭薬協会)/(公社)東京薬事協会/(公社)東京生薬協会/(公社)東京都医薬品登録販売者協会
本イベントに関しての問い合わせ:otc2020@otc-event.jp(OTC医薬品普及啓発イベント運営事務局)
提供:株式会社 龍角散
CONTENTS 1 医師と患者のあるべき関係とは