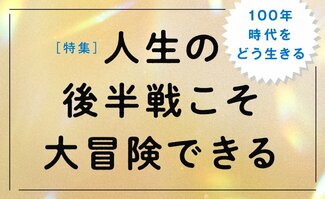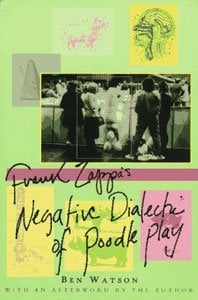
●第2章 フリークダム・アンド・ザ・ヒッピーズより抜粋
ジョージ・デュークは1968年に、ドン・エリスとともにツアーを行い、エリスからエレクトロニック・キーボードを紹介された。デュークはまた、ジャン・リュック・ポンティの一枚のレコードを聴き、手紙とテープで熱心にラブコールを送る。彼はその後、ロサンゼルスのナイトクラブで、ポンティとの共演を実現させた。
「私たちは『ドンテズ』で、同じステージに立った。それが実際、初めての顔合わせだった。だが二人とも、互いの演奏に興奮し、このままずっと演奏しつづけたいと思った。それは、一生に一度しか味わえないような高揚感だった。ジャン・リュックは、私の演奏のさまざまな要素にインスパイアーされた。いっぽう私は、哀愁の漂うあのヴァイオリンの音色に魅了され、仕事を忘れて聴き入りたいと何度も思った」
デュークとポンティは、ジャズという枠にとらわれず、新しい音楽を存分に楽しみたいと考えていた。したがって、二人が意気投合したことは、驚くに当たらない。彼らが創り出した音楽は、その後の “ジャズ・ロック” なるもの以上に即興性があり、刺激的な “ロック・ジャズ” である。そして、1969年のライヴ・レコーディング、『ジャン・リュック・ポンティ・エクスペリエンス・ウィズ・ジョージ・デューク・トリオ』では、小気味よく洗練された演奏を繰り広げる。
それは、オリジナル・マザーズの骨太い一体感と異なるものの、ザッパが、デュークやポンティを起用しはじめた時に、取り入れたエッセンスだった。特に『オーヴァーナイト・センセーション』では、それが顕著である。
デュークは当初、ザッパのさまざまな要求に関して、すぐさま同意できずにいた。たとえば、彼は初期のリハーサルで、トライアドによる三連符を演奏するよう求められたが、それを嫌った。デュークはあくまでも、ジャズ畑で育ったミュージシャンだった。だが、彼はやがて、献身的な演奏を心がけるようになり、ザッパの要求をその一環と捉えた。
ジョージ・デュークは、マザーズ・ヴァージョンのキーボード奏者として、役割をまっとうし、好評を博した。ハーモニーの素養、ブルースやファンクのフィーリング、そしてユーモアのセンスを兼ねそなえた彼は、まさに打ってつけのメンバーだった。ザッパが、次のようにコメントしている。
「俺の演奏がそれほどよかったとは思わない。だが、ジョージがいると、特にやりやすかった。彼は、とびきり優れたミュージシャンだ。だから、バックに何か面白いサウンドがほしければ、彼に頼ればいいのさ。それは、他の誰かがソロをとる間、キーボードの奏者に好き勝手に演奏させるというような、はた迷惑な話じゃないぜ。ジョージは、誰がソロをとろうが、ナポレオンだろうが、俺だろうが、誰だろうが、いつも気の利いたサポートをしてくれる男だった。俺はその後も、いろんなミュージシャンをバックに使ってきたが、彼のように感心させられたことはない」
デュークは、ザッパと活動をともにする間、ドイツのMPSレーベルに興味深いファンクを吹き込んだ。それは、80年代におけるM-BASE派の“革新”を予感させ、同時にPファンクやフューザックに繋がるものだった。彼は後に、アレンジャーやプロデューサーとしても幅広く活躍し、マイルス・デイヴィスの晩年の傑作『ツツ』では、収録曲を提供している。
ポンティとデュークは1969年、ジェラルド・ウィルソン・オーケストラのアルバム『エターナル・エクイノックス』でフィーチャーされ、ウエスト・コーストで話題になった。ザッパにアセテート盤をかけ、ポンティの演奏を聴かせたのは、パシフィック・ジャズ・レーベルを創設したプロデューサーのリチャード・ボックだった。
ザッパは同年9月に、ロサンゼルスのナイトクラブ「ジー・エクスペリエンス」で、ポンティやデュークとともに、ジャム・セッションを行った。そして彼は、アルバム『ホット・ラッツ』の ≪イット・マスト・ビー・ア・キャメル≫ に、ポンティの独特の音色を加えた。
『Frank Zappa : The Negative Dialectics Of Poodle Play』By Ben Watson
訳:中山啓子
[次回7/27(月)更新予定]
 中山啓子
中山啓子