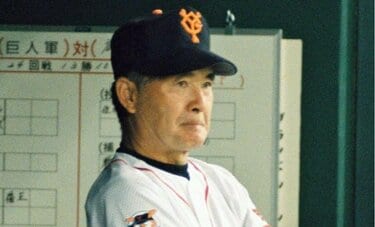まだ映画を観ていない人のために具体的な描写は伏せるが、これまで直接的に描かれてこなかった「死」がすず達を襲うようになる。そして、メメント・モリ、死を思えといったテーゼが急速に日常空間をのみ込み始める。だが、すずをはじめとした、この時代の人々は、「死の意識」に向かって、自分たちの生活を守り続けることで銃後で闘っていた。これが彼ら、彼女たちの”戦争”だったといえる。つまり、すずの戦争の始まりは、昭和16年12月8日ではなく、昭和20年3月に入ってからだったというわけだ。
半年もない間が長かったのか、それとも短かったのかはとても想像できない。途中、すず自身も右手を失う重傷を負い、このまま生きていていいのか、自分の居場所について悩むようになるが、それでも生きている以上闘うほかなかった。その居場所であった家も幸いして空襲で焼けることはなく、すずは自分の居場所に悩みを抱きつつも、生活を守る闘いは続いていく。舞台に広島が関係している以上、8月6日の原爆投下は避けては通れないのだが、その直後の様子は呉から大勢の救援隊が向かったことが描かれるぐらいで、すずの日常にはあまり踏み入ってこない。そして広島がどうなっているのかがはっきりしないまま、8月15日の終戦を迎える。
この時、終戦を告げる「玉音放送」を家で聴いたすずは「最後のひとりまで戦うんじゃなかったんかね? まだ左手も両足も残っとるのに!!」と怒りをあらわにする。国家としては戦争に敗れはしたものの、彼女たちの戦争に移して考えると、まだ負けたとは認めがたい。解釈はいろいろあるだろうが、こうした感覚があったのではないかと私は感じた。
 AERA dot.編集部
AERA dot.編集部