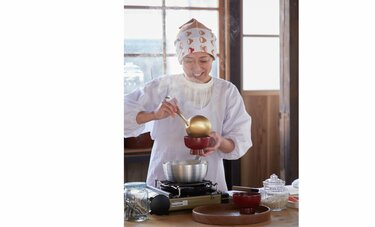働き方が変化する中、「休み方」も多様化しつつある。その一つが、取得理由を問わない長期休暇「サバティカル休暇」だ。導入企業も増え始めている。AERA2024年3月4日号より。
* * *
定年後も働くのが当たり前の時代。長く働き続けるのに不可欠な要素の一つが、長期休暇を使いこなすスキルだと言われる。リラックスできる時間や環境が心身の健康維持・増進につながるのはもちろん、将来を見据えたキャリアの棚卸しや探求のためにも「非日常体験」は貴重だという。
だが、そう言われてもピンとこない人は多いはず。年休消化もままならないのに長期休暇なんて考えが及ばない。そもそも長期休暇制度がない、という声も聞こえてきそうだ。ましてや取得理由を問わない長期休暇(サバティカル休暇)など夢のまた夢……なのだろうか。
サバティカルはラテン語の「安息日」に由来する。サバティカル休暇は1880年に米国のハーバード大学で始まった研究のための有給休暇が起源とされ、1990年代に離職対策として欧州各国に広まった。欧州諸国ではサバティカル休暇に限らず、年次有給休暇、育児・介護など多様な休暇が法制度として整備され、広く取得されてきた(下の表)。
導入検討する時期に
一方、日本ではもっぱら大学教員が学内業務を離れて専門分野の研究に打ち込むための制度というイメージがあるが、近年は導入企業も増えつつある。背景要因について、SOMPOインスティチュート・プラスの大島由佳主任研究員はこう解説する。
「高齢化に伴って長期化する就労期間の途中での休息・リフレッシュ、キャリアの振り返りや将来に向けた模索の時間の意義は高まっています。企業が人的資本経営を推進し、働く人に選ばれるためにも導入を真剣に検討する時期に来ていると考えられます」
AIの導入などによって自動化や効率化が進み、産業構造の変化も加速する中、終身雇用の崩壊も相まって個人にはキャリア自律やリスキリングが求められている。そうした現実と将来への不安に加え、子育てや介護、療養など様々な事情を抱えながら働き方を模索する人が増えている。だからこそ、と大島さんはこう続ける。
「個人がより長期的な観点を持ちながら、その時々の状況に応じて『今の職場で働く、今の仕事をする』以外の時間の取り方を柔軟にデザインできるよう、社会や企業による仕組みづくりが求められています」
 渡辺豪
渡辺豪