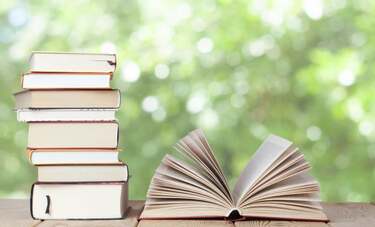STEAM教育の「STEAM」とは、Science(科学)、Technology(技術)、Engineering(工学)、Art(芸術・教養)、Mathematics(数学)の頭文字をとったもの。AIをはじめ、急激に技術が発展し変容する現代社会で、文系・理系の枠を超え、さまざまな情報を活用して日々生まれる課題を解決していく能力を育成するための教育だ。
「これからの社会で活躍するうえで必要な経験、『生きる力』をはぐくむ教育と考えています」(横山さん)
科学、技術、工学、数学と理系科目に偏っているようにも思うが、横山さんはこう語る。「テクノロジーの急速な発展にキャッチアップしなければいけないので、理系教育が軸になります。そこの変化をいままでの学校教育で十分に補うには難しい」
ただ、理系教育を強化するだけではこれまでの学校教育とかわらない。横山さんによれば、ポイントは「Art」だ。「Artにはリベラルアーツ=教養と、芸術という二つの意味がありますが、私はアーツとは『自分の考えをどうアウトプットするか』という学びだと考えています」。
課題解決力にはいろいろなとらえ方があるが、横山さんは「世の中にひとつ幸せなことをつくる」と定義づけている。知識を活用してアイデアを出し、アウトプットして周りを少し幸せにする。これが「課題解決」。
「アートという形で世の中にアウトプットし、影響を与えられるようになったらすごいことですよね」(横山さん)
理数系の授業に偏りがちなSTEAM教育だが、横山さんはすべてのカリキュラムでSTEAM的思考を取り入れる必要があると考えている。才教学園はもともと芸術系の指導に定評があり、文化祭で生徒が取り組む舞台は高い評価を得ている。その強みを生かし、地域社会や企業とも協働して多くの実体験を提供、科目横断的な学びの機会をつくっていくのがこの学園のSTEAM教育の特徴だ。