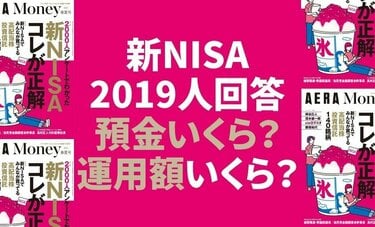実は、日本では、年間を通して食中毒は発生しています。例えば、冬の時期は、ノロウイルスをはじめとしたウイルス性の食中毒の発生が多く報告されます。「生牡蠣を食べた2日後ぐらいに、吐き気と腹痛がひどくなり、下痢が止まらなくなりました」と、冬の外来診療では、このような症状で受診する方が多くなります。
食中毒の主な原因は、細菌(カンピロバクターやウェルシュ菌など)、寄生虫(アニサキスなど)、ウイルス(ノロウイルスなど)です。アニサキスを代表とする寄生虫による食中毒は、年間を通して発生していることが報告されていますが。細菌が増えやすくなる気温や湿度が高くなる時期は、細菌性の食中毒が増加傾向になり、冬の時期はノロウイルスをはじめとしたウイルス性食中毒が増加します。つまり、日頃からの食中毒の予防が大切だといえるでしょう。
私が作りすぎてしまったカレーですが、カレーはウェルシュ菌という細菌性の食中毒を引き起こすことで知られています。ウェルシュ菌は、動物の腸管内や土壌など、自然界に広く存在している細菌であり、100度で1時間の加熱にも耐えうる芽胞という殻を作って生き残るという性質を持っています。そのため、カレーやシチュー、肉じゃがなどを調理した後、そのまま常温で保管してしまうと、芽胞となって生き残ったウェルシュ菌が、温度が下がって増殖する上で適温となった食品の中で急増してしまうのです。加熱調理しても生き残るウェルシュ菌を食することで、食中毒を引き起こしてしまうのです。
ウェルシュ菌による食中毒を予防するためには、ウェルシュ菌をいかに増殖させないかがポイントです。一つ目に、翌日に食べるカレーも、ひと味違って美味しいのですが、カレーは食べきれる量を作り、加熱調理後はなるべく早く食べることが大切です。また、農林水産省によると、ウェルシュ菌は12~50度で増殖し、特に43~45度で活発になるようです。やむを得ず保存する場合は、短時間で出来るだけ温度が下がるように小さな容器に小分けするなどし、なるべく早く冷蔵庫で保存することが二つ目の大切なポイントです。三つ目に、一度保存した料理を食べる際には、増殖しやすい環境を作らないよう中心部まで十分に加熱し、早めに食べるようにしましょう。加熱することによってウェルシュ菌を減らすことができます。
湿度の高い暑いこの時期は、どうしても熱中症対策に向きがちですが、食中毒対策もしっかり行なって、梅雨や夏の時期を乗り切ってくださいね。
山本佳奈(やまもと・かな)/1989年生まれ。滋賀県出身。医師。医学博士。2015年滋賀医科大学医学部医学科卒業。2022年東京大学大学院医学系研究科修了。ナビタスクリニック(立川)内科医、よしのぶクリニック(鹿児島)非常勤医師、特定非営利活動法人医療ガバナンス研究所研究員。著書に『貧血大国・日本』(光文社新書)
 山本佳奈
山本佳奈