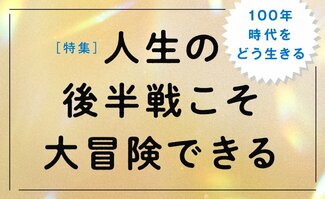ただ多くの航空事故とは異なり、鶴見事故では乗客全員が死傷したわけではなかった。それどころか、全く損傷しなかった車両もあった。二本の電車ともに、どの車両に乗ったかによって客の運命が分かれたのだ。
横浜市立大学の学長だった三枝博音(さいぐさひろと)は、下り電車の五両目に乗っていた。ちょうど上り電車が突っ込み、大破した車両に乗ったことになる。三枝の遺体は事故現場に近い曹洞宗大本山總持寺に安置された。
小池真理子の長編小説『神よ憐れみたまえ』は、「一九六三年十一月九日」という節から始まる。まさに鶴見事故が起こった日だ。大田区の久が原で夫婦を殺害した「男」は自転車で川崎に向かい、社員寮のある保土ケ谷まで横須賀線に乗ろうとした。ホームに出たとき、時計の針は午後9時42分を指していた。「男」は44分発の逗子ゆき下り電車の一両目に乗った。保土ケ谷駅の改札口に通じる跨線橋(こせんきょう)が、ホームの最も戸塚寄りにあったからだ。当時の保土ケ谷駅は、確かにそういう構造をしていた。この電車は事故に巻き込まれたが、一両目は何ともなかった。
さらに「男」にとって幸いしたのは、同じく事故に巻き込まれながら何ともなかった上り電車の最後部に会社の同僚が乗っていたことだ。詳しくは小説を読まれたいが、この偶然が「男」の運命を左右することになる。
当時一一歳だった小池真理子は、鶴見事故で母方の叔父を亡くしている。数々の悲運に見舞われながら生き抜く女性を描き出した『神よ憐れみたまえ』は、戦後史に残る鉄道事故を文学に昇華させた希有(けう)な試みとしても、長く記憶されるはずだ。
※列車やバスの発着時刻などの表記は算用数字とした

 AERA dot.編集部
AERA dot.編集部