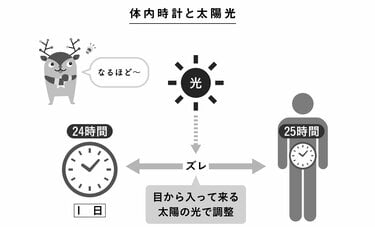……と、これが案外難しいことだというのは、私もよく分かります。私も文科省時代、毎朝、都心に向かう電車のホームに立ちながら、「もう全部放り出して、逆方向の(つまり田舎の方へ向かう)電車に乗ってしまいたい……」と思ったことが何度あったか……。
しかし、これまでを振り返ってみれば、組織には“できない人”の存在も必要だったりします。私は30代の時に、50代の部下がいたんですが、その人がまったく仕事ができない人でね(笑)。仕事をしているつもりなんだろうけど、まるで仕事になっていない。だけど飲み会になると俄然存在感が発揮される“飲み会専門”みたいな人で、明るくて楽しいムードメーカーだった。彼のおかげで雰囲気のいい職場になっていたなと思うんです。
日本型の組織は平等主義で、「できる社員」と「できない社員」で給与もあまり差をつけないのが問題だと言われたりするけれど、私はそれでいいと思う。「できる社員」には、給与よりも地位で遇するのが日本型組織なんだと思います。そして「できない社員」にもそれなりの仕事を与えることで組織全体がうまく回る。
あなたが人並み以上に働いていることは、あなたの上司も分かっているはず。いずれ昇進の機会が来るでしょう。今はあまり根を詰めすぎず、適度にサボることをおすすめします。
※週刊朝日 2019年6月7日号
 前川喜平
前川喜平