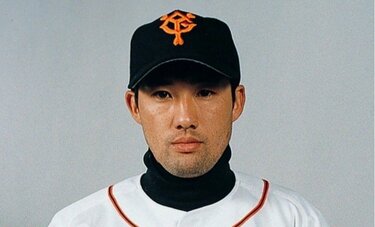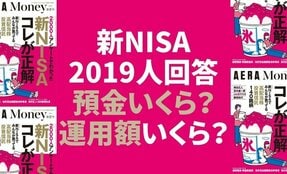――イラストレーターなどの仕事がなくなることは考えられますか?
表現者にとって、AIは作品制作方法としては多くの中の一つの選択肢にすぎない。ですから、デザイナーやアーティストの職業を脅かすのではないかということも言われているようですが、デザイナーがAIに淘汰されることはないでしょう。プロの選択眼を持って最終提案をするのは人間でしょうから。また手描きの良さを大事にする人達も残るでしょう。手描きのものの存在感が淘汰されるというのは考えられません。それに、データは意外と消えさる可能性がありますが、紙やキャンバスの耐久性は証明されています。
――南條さんにとって、AIの何が面白いと感じられますか?
言葉を入れるところからスタートすることですね。普通、人間が絵を描くときは、たとえば風景画なら見ているものの印象を受けて描いたりしますよね。でも、AIは、コンセプトありきなんです。「美しい秋の山」と指示したら、美しいと秋と山のイメージの集積からフィットする要素を突き合わせて、秋の山のイメージを生成する。言語ありきという点が非常にコンセプチュアルアート的だと感じています。
コンセプチュアルアートは、概念芸術と言われていて、コンセプトやアイデアを作品の中心的コンテンツとしているアートの一分野です。画像生成AIは、言葉から出発しているため、今までのメカニズムとは違う何かが最初から内包されていく可能性がある。そこに一つ、興味深い部分があります。たとえばAIに倫理観を持ち込んで「サステナブル」とか「大気汚染を止める」というような言葉を入れたとき、何が描かれるのか。廃墟になった工場が出てくるのか、美しい自然が描かれるのか。あるいは、もうコンピューターを使うことをやめろと言ってくるのか? ナンセンスな言葉の組み合わせが何を生み出してくるのか。その答えは見てみたいし、言語的な関わり方は画期的だと感じています。
――実際に画像生成AIを試しに使ってみたのですが、やはり人間の力というものがまだ必要だと感じました。
そうですね。結局、AIにしても相変わらずとても人間的なものなのではないでしょうか。インプットする言葉を何にするかは人間です。また、「Midjourney」や「Stable Diffusion」で40枚の絵を生成したとして、その中の一つを選ぶところに、人間が持っているアートのスピリットが顕現するわけです。
1980年代の終わりに、ポストモダンアートがアメリカで流行りました。あるアーティストが棚にボールとか、ガラスのコップ、ミットなどを置いただけのアートを展示していたんですけど、僕はそのとき「君は何も作り出していないけど、なんでこれがアートなの?」と聞いたんです。そうしたら、「これを選んでいる自分の目と選択肢の中にアートがある」と言ったんです。この宣言の大元はマルセル・デュシャンの言葉ですが、なるほどなあと思いました。AIアートもそうです。AIが生成したもののどれを自分の作品として出すか、その選択のところに自分のアイデンティティが生じてきます。
一方で、決定するところをAIに任せては、人間不在の世界になってしまう。そこは手放してはならないと思います。テクノロジーを使ってポジティブなことをやるか、ネガティブなことをやるか、テクノロジーの使い方は間違っていないか、それを見抜いていく必要があるから、人間の叡智や知恵がもっと重要な時代になるんじゃないかと思います。これから芸術を担うAIにも色々なものが出てくるでしょう。それでも最後は、AIが作ったものをいかに選ぶか、それをどう評価するかというところがとても重要な、そして人間的な根幹として残るのだろうと思います。
(構成/編集部・大川恵実)
※AERAオンライン限定記事
 大川恵実
大川恵実