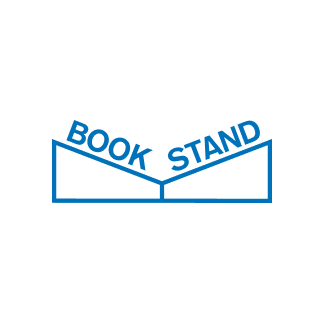25mプールにバラバラに分解した腕時計の部品を沈め、かき混ぜていたら自然に腕時計が完成して、しかも動き出す――。これが地球に生命が誕生する確率を表す例えだという。偶然が重なり奇跡的に誕生したのが生命だとすると、その命が潰える「死」にも意味はあるのだろうか?
今回ご紹介する書籍は『生物はなぜ死ぬのか』(講談社)。著者の小林武彦氏は生物学者で、『寿命はなぜ決まっているのか――長生き遺伝子のヒミツ』(岩波書店)、『DNAの98%は謎 生命の鍵を握る「非コードDNA」とは何か』(講談社)などの書籍も執筆している人物だ。同書は生物学をバックグラウンドとして生物の誕生・絶滅の意味などから「死」の理由を考察していく内容となっている。
「生き物が生まれるのは偶然ですが、死ぬのは必然なのです。(中略)『死』は絶対的な悪の存在ではなく、全生物にとって必要なものです」(同書より)
25mプールの例え(生命の誕生)が偶然だとすると、「死」の必然とはどういうことなのだろう。小林氏はこう語っている。
「生物を作り上げた進化は、実は<絶滅=死>によってもたらされたのです。
生き物にとって死とは、進化、つまり『変化』と『選択』を実現するためにあります。『死ぬ』ことで生物は誕生し、進化し、生き残ってくることができたのです」(同書より)
白亜紀の恐竜が絶滅せずに生き残っていたら、ヒトは祖先といわれている小型哺乳類から進化できなかったかもしれない。また生物は環境や外敵に適応すべく、長い年月を経て進化し続けている。つまり「死」も絶滅や進化が作った生物の仕組みのひとつ、という考え方だ。
第2章「そもそも生物はなぜ絶滅するか」で小林氏は、現代の地球は過去の歴史から見ても「絶滅種が非常に多く発生している状態」(原因は私たち人間)だと語った。これは恐竜が絶滅して新しい種が台頭してきたように、生物の入れ替え(小林氏の言う"ターンオーバー")が始まっている可能性もある。この先数百万年かけて新しい地球に適応した生物が現れるのかもしれないが、そこにヒトの子孫が残っているかはわからないそうだ。
「人類よりもっと科学的に進歩した宇宙人が地球を訪れる可能性が遠い将来にないわけではありませんが、それ以前に人類が滅びている可能性のほうがだいぶ高いのかもしれません」(同書より)
「死」が「生」にプログラムされているのだとしても、「死」に対するそこはかとない恐怖感は拭えない。小林氏は第5章「そもそも生物はなぜ死ぬのか」で、なぜヒトは死ぬことが怖いのかについても考えを述べている。
「この恐怖から逃れることはできません。この恐怖は、ヒトが『共感力』を身につけ、集団を大切にし、他者との繋がりにより生き残ってきた証なのです。
ヒトにとって『死』の恐怖は、『共感』で繋がり、常に幸福感を与えていてくれたヒトとの絆を喪失する恐怖なのです」(同書より)
小林氏の記述で何かがストンと腑に落ちたように感じた。私たちは「死」が「怖い」のではなく「寂しい」のではないか? 「死」はヒトだけの感覚だというが、「死」の意味が一番わかっていないのもヒトなのかもしれない。小林氏が「昆虫は最も進化した生物」と語るのも納得だ。
自分の内臓を吐き出して(足りなければ自身の体も)子供に食べさせる母グモ、24時間しか生きられず「食べる」必要がないため口を持たずに生まれてくるカゲロウ。どの生き物も「生」を全うして子孫のために死んでいく。生きることは死ぬことなのだ。私たちは「生きる」ことに執着しすぎて、「生きる内容」がおざなりになっていないだろうか。
ここ数十年で世界はデジタル化が進み、AIが発達した。死ぬことなくバージョンアップを続けるAIと私たちの未来がどうなるのかについても小林氏は触れている。いつでも合理的な答えを出すAIにヒトが頼りきることは「考えることをやめる」ことと同義だ。ヒトは知能を使うことで進化して生き延びてきた。知能を使わなくなったヒトは衰退するだろう。
「大切なことは、何をAIに頼って、何をヒトが決めるのかを、しっかり区別することでしょう。
ヒトが人である理由をしっかりと理解すること」(同書より)
AIが宗教的な存在となり、ヒトがただ服従する立場になるのではないかと小林氏は危惧する。AIとヒトの立場が逆転するかどうかはヒトの手にかかっているのだ。
共感力を身につけてしまったヒトは、昆虫や動物のように死を悟って死んでいくのはこの先も難しいだろう。しかし恐れる気持ちは生きている証ともいえる。死の意味について考え、「精一杯生きなければ」と思うことこそが祖先から受け継いだ進化の一端なのかもしれない。