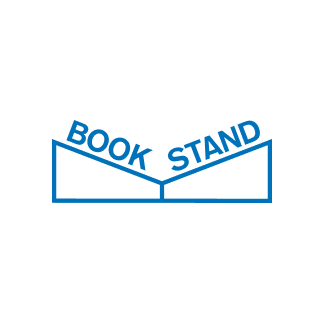「保育園落ちた日本死ね」という言葉に象徴されるように、昨今の日本では、待機児童の問題が深刻さを帯びています。国や自治体が策を講じてはいますが、なかなか効果を上げられていません。一体なぜなのでしょうか?
本書『経済学者、待機児童ゼロに挑む』では、3人の子どもがおり待機児童問題をその身をもって経験し、国や自治体の待機児童対策に関わってきた経済学者・鈴木亘氏が、経験談を交えながらその謎を解き明かします。
本書によれば、待機児童数は毎年2万人から2万数千人規模で恒常的に存在。一進一退を続けているだけで、この10年何も改善されていないというのです。しかし、だからといって政府が何もしていないわけではありません。
実際、2010年以降、児童待機数を上回る受け皿を供給し続けています。特にここ数年はそれが顕著であり、15年に10万7千人、16年の8万5000人、17年には8万8000人と、実に待機児度数の3倍というペースで保育の受け皿を拡充。それにもかわらず待機児童数が減らないのは、行政が把握できていない「潜在的な待機児童」の存在だといいます。
「潜在的な待機児童」は、育休を延長して認可保育所が空き次第、入園させようとしている子どもなどの「隠れ待機児童」、審査に通らないからとはじめから認可保育園に申し込みしていないといった「見えない待機児童」の2種類。こうした問題は「氷山の海面下にある部分」にあることから、「対策を打って海面上の待機児童がいったん解消できても、すぐに下からせり上がってきて新たな待機児童を生み出します」と著者は主張します。
さらに、著者は待機児童問題の根本的な原因として、日本の保育の構造的問題に言及。大部分を占める認可保育園では、保育料が行政によって定められているため、保育園不足が生じても保育料を値上げすることができず、経営者には園新設という動機が生まれにくい。認可保育園の設置許可も行政であり、経営者が自由に設置できない。そうした参入規制は民間企業の進出障壁にもなっているというのです。著者はこう指摘します。
「日本の保育は社会主義だと考えれば、待機児童という形の長い『行列』に並ばなければならないことも納得でしょう。我々は、お上から保育サービスの『配給』を受けているのであり、配給量が足りなくて待機児童が発生する仕組みになっているわけです。」(本書より)
日本の保育制度が社会主義的であるのは、保育が「児童福祉」であり、「社会福祉」であることが原因。それゆえ、高水準の公費投入という高コスト体質が生まれており、将来的に財政の圧迫が懸念されるため、財政面から見ても保育を「ごく普通の産業」にする改革が必要であと著者は指摘しています。果たして日本の保育に夜明けは来るのでしょうか。
経済書というよりは、著者の体験や活動から待機児童問題の理解を深められるノンフィクションの色合いが強い本書。共感はもちろん新鮮な驚きや感動が待っているはずです。