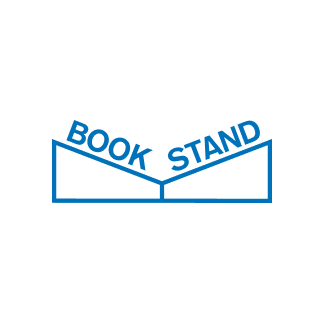BOOKSTANDがお届けする「本屋大賞2018」ノミネート全10作の紹介。今回、取り上げるのは原田マハ著『たゆたえども沈まず』です。
*******
パブロ・ピカソの名画に潜む謎を追った『暗幕のゲルニカ』が「本屋大賞2017」にノミネートされた原田マハ。今回の新作は、美術史に燦然と輝くフィンセント・ファン・ゴッホが、まだ売れない画家だった頃の話が綴られていきます。
舞台は1886年の、栄華を極めたフランス・パリの美術界。開成学校(後の東京大学)の諸芸科でフランス語を学び、首席で卒業した加納重吉が、浮世絵など日本の美術を扱う美術商「若井・林商会」を営む、先輩の林忠正のもとにやってきます。
同じころ、フィンセントは、名のある画商である伯父の縁で、伝統的な古典の技法を意識したアカデミー関係の画家たちの作品を取り扱う「グーピル商会」で、画商を務めていました。4歳年下の弟テオは、兄を慕い憧れており、自らも跡を追うように画商になります。
2人は「悲しみも喜びもすべてを分かち合える親友同士」「互いを自身の半身であると感じる双子のような」と形容されるほど仲睦まじい関係。しかし、フィンセントは失恋や画商の仕事がうまくいかず、人生に絶望し退職。聖職者を目指しベルギーに渡るも挫折。テオのいるパリに戻り、28歳にして"画家"を志します。テオは兄の才能を信じ「このさき何があっても支えよう」と決心。経済的にも精神的にも全力で支えていきます。
フィンセントは後に「後期印象派」を代表する1人として名を馳せることになりますが、その源流である「印象派」は当時、「おぞましい絵」「芸術の範疇に入らぬもの」などと酷評されることもしばしば。構図も決めず、配置もよく練られていないことから、「印象」だけで描かれた「劣悪な印象に過ぎない」とされていたからです。
そうした印象派が影響を受けたのが浮世絵でした。1876年にパリ万博で初めて紹介されて以来、フランスでは浮世絵などの日本美術が流行した「ジャポニズム(日本趣味)」が広がりをみせていました。フィンセントとテオは、印象派、そして当然のように浮世絵に魅せられます。そんな2人の前に忠正と重吉が現れたことで、大きく運命が動き出していくことになります。
タイトル「たゆたえども沈まず」は、現代のパリの標語。意味は「どんなときであれ、何度でも。流れに逆らわず、激流に身を委ね、決して沈まず、やがて立ちあがる」。水害が多かったパリならではの言葉です。いかなる苦境に追い込まれようとも、決して沈むことのない兄弟の力強い意志と愛を、この作品から感じ取ってみてはいかがでしょうか。