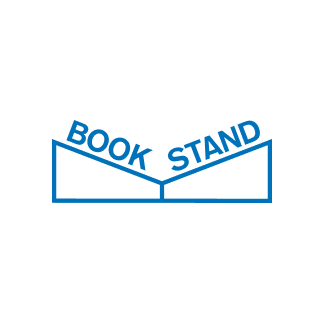まんが原作者・批評家である大塚英志さんの最新作、『クウデタア 完全版』が発売になりました。舞台は敗戦の開放感と新時代への不安が入り混じる60年安保の前夜、三島由紀夫、大江健三郎、石原慎太郎、江藤淳という戦後文学の担い手たちと、「クウデタア」を決行した10代の少年たちを描いた青春群像です。原作者の大塚さんに『クウデタア』の時代についてお話を聞かせていただきました。
■戦後文学者と少年テロリストたち
---- 今回発売になった『クウデタア 完全版』は原作者の大塚さんからするとどういう人に読んでほしいと思われていますか?
大塚:こういう読者に届けたいという建前を言うべきでしょうけれど、今回は、読者は全く想定していません。もともと星海新書で批評で書くつもりだったんだけと、結局、まんがにしました。
出版社から原稿料をもらって仕事として作った作品ではなく、まんが家の方の原稿料もぼくの事務所が負担した、自主制作作品ですから。
---- この作品の時代背景は安保闘争があった時期で、首相も現在の安倍首相の祖父である岸伸介が首相の時代になっています。
大塚:ええ、岸が中にいる議事堂の周りを安保に反対する学生や市民に囲まれていたという光景があった時代です。それが去年の安保法制をめぐって孫である安倍の時代に繰り替えされたわけですが、決定的に違うのは文学者の役割です。あの時、大江健三郎、石原慎太郎、江藤淳ら文学者たちは現実に関わることことを躊躇しなかった。だからこそ彼らは世代が上の三島由紀夫も含め、政治的少年たちのテロルや犯罪にも過敏すぎるほど反応しました。
---- テロリストになった少年たちと文学者の関係についてという部分もあります。
大塚:ええ、「文学者」とテロ少年・犯罪少年をめぐる物語を書きたかったわけです。作品について少し説明すれば、『クウデタア 完全版』は三部作の第二部にあたります。第一部は70年前後、全共闘の時代を背景に永山則夫をモデルにした『アンラッキーヤングメン』(タイトルは大江健三郎の小説の作中からとりました)で、時代に妙にシンクロしたんだけど、それ故、つまずいてしまった彼らの物語でした。
今回は3人の犯罪少年やテロリストになった少年たちが主人公ですが、彼らもアンラッキーヤングメン、な訳です。当時、彼らは「恐るべき17歳」と言われていたけれど時代の気配に過度に反応した少年だったわけです。
今だと一人の若者が事件を起こしたらまずは自己責任、次が親のせいだ、そして、即、極刑を望む。コメンテーターや評論家たちもその同調圧力に乗るか、社会学的に一歩引いたメタな立場から分析している。他人事です。そして彼らの内で起きていることは、「サイコパス」か「心の闇」の一言で終る。
---- ええ、ある種の生贄のようにされてワイドショーでこの人は叩いてもいいんですよって感じになっています。
大塚:だけど、少なくとも60年代の時点では文学者たちは違っていた。言葉を発しない代わりに行動を起こしてしまった子たちの、犯罪とは違う彼らの内側で何が起きたのかってことを代わりに語るのが文学なんだってことが、自明の如く彼らの中にあった。『クウデタア』の作中で大江健三郎や三島由紀夫や石原慎太郎や深沢七郎といった戦後文学者たちが様々な形で犯罪少年、テロ少年について語ろうとする姿が描かれますがそれは事実としてそうでした。
---- その戦後文学者たちと、テロリストになってしまった少年たちについて描いた作品ですが、今の状況の始まりでもあったのかなと読んでいて思ったのですが?
大塚:始まりというより、やはり、「違い」かな。今の政治の状況や言論の状況と対比して読んでもらえたら、現在が見えるみたいなことは言えると思います。今だったら例えば、「秋葉原通り魔事件」の加藤だとか「黒子のバスケ脅迫事件」の彼だとか、最近のいくつかの事件に関してはネット上の一部の同年代の人々のなかには、行為の是非ではなく、どこかで自分たちの姿みたいなもの重ねた人は少なくないはずです。
でも、一人の犯罪青少年に、ああ、あれは自分だったかもしれないと重ねあわせることが、ひどく言いづらいみたいな感じでしょう。犯罪青少年が言語化しそこねて、行為化してしまった何ものかを言語化するのが文学の役割だっていうことが、当時は自明の時代だったわけです。
---- 何人かの小説家の人が彼らや事件をモチーフやイメージして小説を書いていたりしますが?
大塚:もちろん、今も、最近の事件の当事者の内側を描こうとする作品がない訳でないし優れたものもある。でも、よくも悪くも今の小説なり文学を象徴するような人は書いていないでしょう。一方で、元少年Aの手記が妙に「文学」的だったり、「黒子のバスケ」事件を起こした人物の分析が社会学的だったりして自己完結してしまっていて、文学と犯罪少年が切断されている。
---- 本当ならばそれについてもっと多くの作家が書いたりだとかドキュメンタリーとして書かれるべきだと?
大塚:文学者が描くってとは、社会がどう受け止めるかを共有することだったわけです。でも、そもそも、「社会が受け止める」「社会に責任がある」っていう言い方が成立しないでしょう。だからこそ、「社会」のことばがいる。
---- 当人のことばではなくてですか?
大塚:17歳の犯罪について大江や石原や三島たちが語るっていうことは、そこで犯罪の是非とは違う、彼らの示そうとしたもの、結果として示したものの意味を読み取ろうというのが文学の義務の遂行だった。そうすることで彼らを社会の側にブリッジする。当たり前のように文学がそれを果たしていた時代があったことを前提として読んでいってほしいと思います。
■石を投げる対象がいない現代と対象のいた60年代
---- 今回の作品のテーマについても聞かせていただいていいですか?
大塚:敢えて不穏当な言い方をしますが、『クウデタア 完全版』の基本的な一番のテーマというのは、「今の日本にどうしてテロリストが出てこないだろう」ということなんです。
例えば、web上のことばのレベルでの左右の政治的憎悪や、政治に関わらずに社会自体の閉塞感はものすごく強い。戦前の2.26事件の時期でも、戦後のこのまんがで描かれているような時期でもかつてならテロリズムがでてくる。あなたは『クウデタア』の作中の時代と今が似ていると少し感じたようだし、今の政治状況を昭和初頭に喩える人は多いけれど、テロリストが出てこないことが決定的に違う。
---- やはりネットでのヘイトとかで息抜きができちゃうってこともあるのでしょうか?
大塚:社会の閉塞感が「ヘイト」レベルの書き込みやことばで解消してしまうのなら、不確かなものを言語化する「文学」の必要はなくなっているということです。
---- それがテーマであり疑問の一つだったんですね。
大塚:テロリストが出てくればいいってことではなくて、なぜ出てこないんだろうって考えないと。出てこないことの意味っていうのが、果たして社会の現状の「正しさ」を反映した結果なのかという疑問がある。
---- 確かにアメリカは銃社会ですけどテロは起きてます。
大塚:アメリカではイスラムへのカウンターとして白人たちのテロもある。ヨーロッパでのテロも現地に行けばわかるけれど、イスラム原理主義というより、若い世代の閉塞感が
基調にある。
---- アメリカだと白人が昔の白人至上主義を未だに持っていたり、時代に取り残されてしまった人が反逆としてテロを起こしたりしています。
大塚:そういうものが出てくるべきだとは思わないけど、日本の若者がテロに向かわないってことの意味ってなんなんだろうと考える必要はある。日本社会が安全だから健全だからとか、政権が素晴らしいからだとかそういうことなのか?
---- そういうことがテーマだと言われるとしっくりきますね。
大塚:実はテロリズムは本当はあるはずなんだけど、ただ、テロリズムとして見えなくなっている、と考えることも出来る。『感情化する社会』のなかでも触れたけど、さっきも言った黒子のバスケ脅迫事件とかね。
---- その中では大塚さんはあの事件は一種のメディミックス的なシステムに対してテロを仕掛けたと書かれていました。
大塚:黒子のバスケ事件は、オタクを搾取し疎外するメディアミックスのシステムへの「テロ」だったんだろうなって気がする。アイドルを握手会で襲った人もいたけれど、自分はなにか搾取されているっていう感覚が根底にあった気がする。
---- それが理由なのに秋元康のところには行かないんだっていう疑問がありますけどね。
大塚:そうだよね。結局、弱いところにしかいかない。そこが情けないところだよね。老人か女の子とか弱者の方にしか行かないんだよ。
それをすこし遠回りして考えてみると、今の子たちにとってはテロを起こそうとした時に、「社会」がそもそもどこにあるのかっていう問題が出てくるわけです。彼らの起こした事件を受け止め思考してくれる場としての「社会」が無いってことは、同時に意義を申し立てる「社会」、破壊すべき「社会」もないってことです。
60年安保の時点、70年の全共闘の時点では「社会」というのは一人の政治家やひとつの政権が象徴していた。実際に変り得ないとしても、岸内閣を倒せば社会が変る気がしたけれど、安保法制以降、安倍政権があれだよねって思ってるわけだよね。でも、安倍政権打倒っていう野党のキャッチコピーは全然届いていない。
---- 届いていないですね。本当にごく一部のリベラルっぽい人ぐらいな感じがします。
大塚:なぜ届かないかって言ったら、一個の政権や政治家が自分を抑圧する「社会」を象徴しなくなっているってことなんだよね。
---- しかも、多様であるということがみんなわかってしまっているので、石を投げようがないですね。
大塚:そう。「社会」というものは、一方では、何か自分を抑圧するものの名、疎外するものの名でもあった。今、それが思えない。「誰を殺したら社会が変わるか」という問いは全くただしくないけれど、同時にその問いが不成立な時代が健全な時代なのか。
---- はい、思えないです。
大塚:相模原の事件だったら、社会的弱者と呼ばれている人たちを保護しているような社会の在り方そのことが自分を抑圧しているというのが彼らの感覚だよね。それは在特会も在日朝鮮人の人たちの存在っていうものが自分たちを抑圧していると感じる。そうすると在日朝鮮人に対するテロリズムでもないけどヘイトデモみたいなものが起きる。「弱者を庇護する」というのが「社会」の機能の一つだけれど、そのような社会システムが自分たちを搾取したり、疎外しているというのが、彼らの主張でしょう。かつて資本主義やそれと結びついた政治から労働者が疎外され搾取されているという感覚が、弱者から疎外・搾取されているっていう感覚にすり替わる。すると、社会的弱者や在日コリアが自分を疎外するものの象徴にすり替わる。
---- 最近だとモデルの水原希子さんに対してのSNS上でのヘイトみたいなものがすごくて炎上していました。
大塚:しかも自分を庇護するものが「社会」じゃなくて「日本」になってしまうから民族的ヘイトも過剰になる。「日本人」であることって、「あなたは日本人ではない」と名指すことで立証出来る気がしてしまうから。あなたは「社会人じゃない」っていっても「社会」は見えないけれど。
---- まんがに描かれているテロリズムは権力や権威に対してのものですね。
大塚:ええ、でも、今は弱者へのテロリズムが相模原のように起きたけれどテロに見えない。
---- 国会に突入して警察と衝突した際に亡くなった美智子がいます。彼女は樺美智子さんがモデルですが、彼女の友人の元に新聞記者と名乗る人物が現れて目撃者の証言を求めたというシーンがありました。
大塚:あれは、デモ隊に踏みつぶされて圧死したのを目撃した青年の証言が新聞記事に載ったっていうのは本当の話で、しかもその目撃した青年が存在しなかったのも事実です。
---- あっ、存在してないんですか。
大塚:そういう名前の人物はいなかった。記事の中に出てきた証言を語った人がいないということは事実です。
---- そこを読んでいると思い出したのが、マスコミを使ったプロパガンダのことで『アンラッキーヤングメン』の三億円事件の時にもマスコミの話が出てきます。
大塚:これは、新聞やテレビに限らず、今のwebも同様です。メディアのある種の馴れ合いや談合みたいなものによって「事実」が作られていくし、自分たちが政治状況を演出できるんじゃないかってことを考えもする。今は新聞やテレビがもうそれを上手く出来なくてぼろが出て叩かれているけれど、webが力を持ったってことは、かつての「マスコミ」の負の部分も同じようにwebでも生じうるよってことです。
■大江健三郎と石原慎太郎という対象的な小説家たち
---- 作中で大江健三郎が「ぼくは自分で言うのも何だがこう見えても仲々滑稽な男なんだ」と自分でいうシーンがありますがあれは本当に言っていたことなんでしょうか?
大塚:大江は自分ことをちゃんと小さく見せることが出来る人です。
---- 小さく見せる?
大塚:昔、ぼくの『サブカルチャー文学論』という本で書いたことなんだけどね、石原慎太郎の『太陽の季節』という小説で有名だから知ってると思うけど、主人公の青年が部屋の向こう側に女の子がいる時に裸で自分の勃起しているペニスで障子を破るっていうシーンが戦後の石原のパブリックイメージになっている。つまりそのペニスが日本だとか男性原理の象徴だった。それを許してくれる女性との関係性も含めて、ね。
ところが大江健三郎の『芽むしり仔撃ち』は、冒頭のところで子どもが自分の小さなペニスをおばさんたちに向かって見せつけるシーンがあって、おばさんたちが哄笑するというところから始まる。
---- わかりやすい対比ですね。
大塚:だから、せいぜい障子しかやぶれない男性器に石原が強い日本みたいなものや男性原理みたいなものを象徴させたとしたら、大江は失笑される男性器にこそ戦後や自身を象徴させたというすごくわかりやすい話でしょう。誇大にみせるのでなく矮小さを直視する。だから、大江は攻撃しやすいわけです。
---- 大江と石原は対比として見ても面白い存在としての作家なんですね。
大塚:大江は強いんですよ。三島も江藤も伊丹十三も大江のライバルたちは皆、自死し、しかし大江は死なない。
---- あとはまったく知らない人が読むと大江健三郎の『死者の奢り』がプールの死体洗いという都市伝説の元になったことを知ることになるのかなと思いました。
大塚:まあ、これはウィキペディアにさえ書いてありますが、死体洗いのアルバイトっていうのは都市伝説で本当には存在していなくて、『死者の奢り』で書かれたことをみんな真に受けた。
---- 『死者の奢り』のラストではプールから死体が起き上がってその死体たちが町を歩く話として終わる形にしたかったという話を大江健三郎が作中で話していますが、そうすると虚実入り混じるまったく違う文学になってましたね。
大塚:ウォーキングデッドになってた。本来にそういうオチになるはずだったという当時の友人の証言があります。実際の小説では歩かなかった。
---- 大江さんって、まだ生きてますか。
大塚:生きてるよ、失礼な(笑)。
---- そうなんですが、この『クウデタア 完全版』には実在する、していた人の名前を表層として借りている部分があるので、ちょっとその辺りが(笑)。でも、存命の方が何人かいますよね。
大塚:そうですね。
---- 大江健三郎さんも石原慎太郎さんも美輪明宏さんもご健在ですし。
大塚:庄司薫さんは生きているけどフェイドアウトしたし、江藤さんは亡くなったし三島も。
---- 何人かの美智子が出てきますが、同じ名の皇后もまだお元気ですしね。
大塚:でも、もうすぐ元号も変わる。元号ってことに関して言えば、いま、1960年、つまり、昭和45年を描くってことは、昭和だった時代に二つ前の元号の時代の明治の時代を書くのとたいして変らなくなっている。今は、戦後レジームを終らせることに熱心な時代だけれど、終らせようとしている「歴史」としての戦後が何だったのか、理解せずに終らせれば済むというものでもない。
(後編)に続く
取材・文/碇本学
<プロフィール>
大塚 英志/おおつか えいじ/まんが原作者・批評家
まんが原作者として活動する傍ら、89年の宮崎勤事件の一審公判に関わる。その後、「イラク自衛隊派兵差し止め訴訟」に参加、違憲判決を得る(『「自衛隊のイラク派兵差止訴訟」判決文を読む』川口創と共著、星海社)。現在は、ヨーロッパの移民居住区や東アジアなど、海外でまんが創作を教えるワークショップ「世界まんが塾」を10カ国15地域で開催。
まんが原作者としての作品に、一連のサイコホラー作品以外に、本書姉妹編として三島由紀夫を狂言回とし、永山則夫をモデルにした『アンラッキーヤングメン』(藤原カムイ画、KADOKAWA)、柳田國男と田山花袋を軸に明治文学青年のロマン主義と「社会」に揺れ動く様を描く「恋する民俗学者」(中島千晴画、webコミックウォーカー連載中)、89年に「平成」が訪れないもう一つの日本を描く「東京オルタナティブ」(西川聖蘭画、『ヤングエース』連載中)などがある。
本作に対応する批評としては、『サブカルチャー文学論』『江藤淳と少女フェミニズム的戦後』がある。