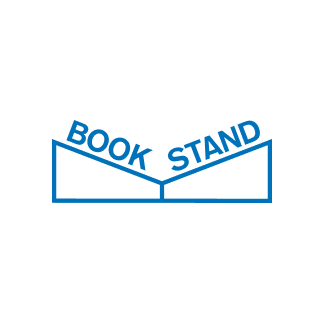BOOKSTANDがお届けする「本屋大賞2017」ノミネート全10作の紹介。今回、取り上げるのは川口俊和著『コーヒーが冷めないうちに』です。
*******
過去や未来に戻り現実を変えるために奮闘する物語はよくあります。しかし本書では、過去に戻ったとしても現実は何も変わることはありません。過去に戻ることで、何モノにも代えがたい何かを得た人たちの物語が4篇綴られます。
過去に戻れるのは、明治7年にオープンしたエアコンのない「フニクリフニクラ」という名の老舗喫茶店のある席。特定の席に座ると、その席に座っている間だけ、望んだ通りの時間に移動ができる「過去に戻れる喫茶店」として、かつて連日のように長蛇の列ができるほど、有名になりました。しかし、過去に戻れた人は「皆無に等しい」というのです。このような少々、面倒臭いルールのせいかもしれません。
「1.過去に戻っても、この喫茶店を訪れた事のない者には会うことができない」
「2.過去に戻ってもどんな努力をしても、現実は変わらない」
「3.過去に戻れる席には先客がいる 席に座れるのは、その先客が席を立った時だけ」
「4.過去に戻っても、席を立って移動することはできない」
「5.過去に戻れるのは、コーヒーをカップに注いでから、そのコーヒーが冷めてしまうまでの間だけ」(本書より)
こうしたルールのもと、「第2話」では、記憶が消えていく男性と看護師の女性の夫婦の物語が描かれています。
若年性アルツハイマー型認知症を患い、記憶障害を起こしていた喫茶店の常連である房木。症状は、妻がいたことはわかっていても、もはやそれが誰なのか、その名もわからず、ついには喫茶店に来た高竹(こうたけ)を妻と認識できないようになっていました。
そんな状態の夫に、高竹は「私は看護師だから。たとえ、あの人の記憶から私という存在が消えてしまったとしても、関わっていくの、関わっていけるのよ」と職業を全うしようと気丈にふるまっていたのです。
そんな矢先、房木が妻にずっと渡したいと思っていた手紙があることだけは覚えていたおり、過去に戻りたがっていたことを知った高竹は、過去に戻ることで、その手紙を受け取ることを決意したのです。
過去に戻り、高竹が久しぶりに妻を認識できる房木に涙ながらに語ったこと、幼いころに学校に満足に通わせてもらえず、読み書きが苦手だった彼が「ミミズが這うような文字」で懸命に綴った、愛する妻に残したメッセージとは何だったのか。そして、何故2人は"旧姓"で呼び合っていたのかも注目すべき点です。
結論から言えば、房木は妻の記憶は戻らず、一切の記憶を失ってしまい、病気は進行していくことになります。現実は何も変わらなかったにもかかわらず、あるモノだけは変わったのです。他の3篇「恋人」「姉妹」「親子」も独立しておらず、1つにつながっており、最終ページで、彼らが共通して変わったモノが明らかになります。
ときに過去に戻って現実を変えたいと嘆く私たちですが、本書を通じて現実とどう向き合うべきか、そのヒントを幼いころ、誰しもが読んだまるで"童話"のように優しく諭してくれる一冊といえそうです。