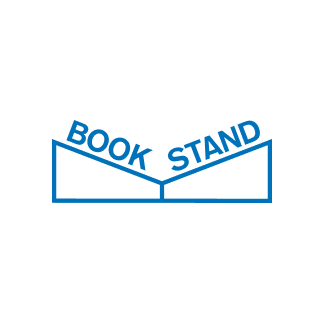1月15日(日)に、作家の石井光太さんとフォトジャーナリストの林典子さんがトークイベントを行った。
2016年12月に著書『砂漠の影絵』を刊行したばかりの作家・石井光太さんは、ノンフィクション作品を中心に幅広いジャンルで活躍を続けている。今回発表した『砂漠の影絵』は、イラクで実際に起こった日本人人質事件をモチーフに執筆された小説。物語は、人質となった日本人被害者、彼らを救おうと奔走する家族や友人、そしてテロリストという三方向から描かれている。 そんな石井さんの対談相手となったのは、昨年末に写真集『ヤズディの祈り』を刊行した林典子さん。人気テレビ番組『クレイジージャーニー』で、IS(イスラム国)に故郷を追われた少数民族「ヤズディ」や、キルギスに今も残る風習「誘拐婚」を紹介して注目を集めている気鋭のフォトジャーナリストだ。
石井さんは、これまでに行ってきた海外取材の集大成となる小説として、林さんは滅びに瀕する民族宗教を撮影することで、ともに中東の現実を伝えている。時を同じくして混迷を極めるイラクをテーマとした作品を発表した2人は、一体どんな話を聞かせてくれるのだろうか。
*****
公開対談イベントの会場となった三省堂西武池袋本店書籍館4Fイベントスペース<Reading Together>には、2人の話を聞こうと多くのファンが詰めかけ、満員でのスタート。対談のホスト役でもある石井さん曰く、このトークショーを依頼され、対談候補として真っ先に上がったのが林さんだったのだとか。
「林さんの、硫酸をかけられて火傷をしたパキスタンの女性の写真を見た時に凄いなって思ったんです。僕自身もかつて最初の著作である『物乞う仏陀』などで葛藤しつつ障害のある物乞いを取材してきましたので、どれだけの関係性を築かなければいけないのか分かる。撮影する中で苦しみや罪悪感があるし、さらに認めてもらうまでには人には分からないいろんなことがあった。 それをやり遂げて作品として世に出せるというのは凄い」(石井さん)
さらに話題は、中央アジアのキルギスで今も行われている壮絶な慣習「誘拐結婚」に迫った林さんの写真集『キルギスの誘拐結婚』へと移っていく。石井さんによれば「悲惨だろう」「悲しいだろう」「辛いだろう」と思って取材に行くと、その予想は必ず裏切られるのだそう。
「僕は第二作『神の棄てた裸体』で売春婦として働く難民の女性を取材したんですが、悲惨な仕事をしていて可哀想だなと思って行くと、中で物凄く明るくたくましく生きていたりする。良い悪いではなく生きるパワーというか、悲惨な境遇を跳ね飛ばしてしまう明るさみたいなものがあって。僕は悲惨さよりも、むしろそこにあるエネルギーのようなものに魅了されて、それを書きたいなって思ったんです」(石井さん)
林さんの『キルギスの誘拐結婚』には、<悲惨>と表現するほかない写真も多数収録されている。が、一方で誘拐した男性と誘拐された女性が結婚して、それなりに上手く行ってしまう不思議な現実も記録されている。それ見た石井さんは「この人も<悲惨>という垣根を超えたところで現実を見つめているんだな」と感じたのだそうだ。
石井さんの「何に目を向け、どういうものを撮りたいのかを知りたい」との言葉を受けた林さんは、スライドを交えて、自身について淡々と説明していく。フォトジャーナリスト・林典子が生まれるきっかけとなったのは、学生時代に得た西アフリカの小国ガンビアでの経験にあるようだ。
「現地で新聞記者をやっていたんですが、ガンビアは独裁政権下で、一緒に働いている記者が行方不明になったり、殺されてしまったりもするんです。でも石油も出ない、観光業も盛んではない、ピーナッツ産業に頼った小さな国なので、日本にとっては重要な国ではない。だから情報が入ってこない。そんな国でいろんなことを見て、卒業後はフリーランスで、いろんな地域で起きていることを伝える仕事がしたいと思うようになったんです」(林さん)
そんな林さんの最新作となるのが、前述の『ヤズディの祈り』だ。今回取材したのはシリアとの国境に近いイラク北部シンジャル。民族宗教ヤズディを信仰する人々が暮らす地域だが、2014年8月にISによって攻撃され、およそ30万人のヤズディ教徒たちが故郷を追われた。当時たまたまトルコにいた林さんは、ISによるアメリカ人ジャーナリストの処刑、そしてヤズディのトルコへの流入を伝えるニュースを目にする。当時を振り返って、林さんは次のように語る。
「ニュース映像を見ている時、私にもこういうことが起こり得るかもしれないし、そうなったらどう思うんだろうと感じました。日本に帰ったら自己責任論で非難されるだろうし、マスコミが両親の家を探して質問をするんだろうなとか、私だけじゃなく周りにも色んなことが起こり得るんだろうとか想像したんです。嫌だったんですけど想像せざるを得ない。石井さんの『砂漠の影絵』には、人質が捕まっている時に考えていること、日本にいる家族の思いが、すごく詳しく書かれている。私の気持ちを代弁していると言ったら失礼かもしれませんが」(林さん)
ニュースでヤズディの存在を知った林さんは、その6ヶ月後に取材のためシンジャルに足を踏み入れるも、戦闘を見ても写真を撮りたいとは思えず、何を伝えれば良いかが分からなくなってしまったのだとか。しかしヤズディの人々と生活を共にする中で、林さんは日常をありのままに切り取った写真を撮影するようになっていく。どうしてだろうか。
もともと他宗教を信仰する人々との結婚を禁じ、また他宗教からの改宗を認めていないため減少の一途をたどるヤズディ教徒だったが、ISに追われる形で離散したことが人口減に拍車をかけた。「あと50年ほどでヤズディは消え失せる」と語る人もいるほどだ。さらにヤズディの歴史は口承で伝えられており、ほとんど記録されていない。その存在はもちろん、やがては存在したという記憶さえ失われる可能性すらあるというわけだ。こうした状況も手伝って、林さんはヤズディから聞いたこと、そして彼らが大事にしていたものを伝えたいと感じるようになっていったのだそうだ。
対談終盤、話題は石井さんの『砂漠の影絵』へと移っていく。学生時代にアフガニスタンを訪れた石井さんは、タリバンを取材したいと感じるようになるが、2001年9月11日に発生したアメリカ同時多発テロによって、その望みは潰える。その後アフガニスタンでの戦争はイラク戦争へと広がり、ちょうど石井さんが海外で取材をしている最中の2004年10月に、イラク日本人青年殺害事件が起こる。犠牲者の青年と年齢も立場も近かったことから、「自分が同じようになっていたかもしれない」と考え、同時に、アフガニスタンでタリバンの人たちと仲良くしたことがあった経験から、テロリストと呼ばれる人々について「本当に彼らは悪人なのか」と悩みはじめた。
「タリバンの人たちとのいい思い出はたくさんあります。タリバンの兵士と一緒に花畑をつくったり、音楽が禁止されているはずなのに外でみんなで歌って楽器を奏でたり、欧米の美人女優のブロマイドを自慢げに見せられたり、家に泊まらせてもらったり、実際はそんなもんなんです。アルカイダだってそう。戦争の前に、何人ものアルカイダという人間に会ったことがありますが、みんなあたたかく思いやりのある人たちだった。つまり、冷酷な殺人者ではなく、ごく普通の人なのです。国際政治の中で『テロリストの支持者』あるいは『テロリスト』とされてしまっているだけ。そういう世界を取材したいと思っていたんです。いわゆるテロリスト側の思い。支持されてる理由にしても、僕らが思いもよらない理由があったりする」(石井さん)
『砂漠の影絵』にも、そんな石井さんの思いはしっかりと盛り込まれている。人質の日本人たち、それを助けようとする家族や友人たちだけでなく、イスラム過激派の視点が生々しくスリリングに、繰り返し描写されていく。
作中、イスラム過激派に「原爆を落としたアメリカを恨まないのはなぜだ」と問われた日本人は「悔しい思いはあるが、勝てるわけないし、戦いは戦いを生むだけ。だから自分たちは怒りや恨みを耐え忍んだのだ」と語る。戦後、アメリカの同盟国として繁栄を享受してきた日本人にとっては自然な回答といえるだろう。
これに対してパレスチナと避難先である難民キャンプで家族や友人たちを虐殺されたイスラム過激派は「俺たちも難民となってキャンプで黙って耐えて生きてきた。しかし、それでも虐殺されてしまった。中東では無抵抗でいれば殺される。生きたいなら戦うしかないんだ」と答える。「どうせ殺されるならば戦って死ぬ」という言い分は決して正しくはないが、完全に間違っているとも言い切れないのではないだろうか。
『砂漠の影絵』には、テロリストや国家や日本人、それぞれの立場からの「正義」が書かれているが、国際関係の中ではそれがうまくかみ合わずに、戦争という名の争いが泥沼化していく姿が見事に描かれている。まさに、小説でしか書けない事実の物語だ。作品の最後に、テロリストと人質の間にこうした言葉が交わされる。
「人と人とでは理解し合えるし、お互いに平和を望んでいるのに、国家と国家とでは争いになってしまう」
なぜ平和を望む人間と人間が、戦わなくてはならなくなってしまうのか。
生きたいという気持ちが、なぜ殺すという行為につながってしまうのか。
この物語は、読者に「平和とは何か」「家族とは何か」「生きるとは何か」ということを強烈に訴えてくる。
*****
石井さんはイスラム過激派の思いを知りたかったという。そして林さんは、ヤズディ個人の生活や想いについて知りたかったという。『砂漠の影絵』と『ヤズディの祈り』は、ともに時代の大局の中で個人に焦点を当てることで、大きな問題の本質をあぶり出してもいる。読めば必ず「テロの世紀」と呼ばれる時代を動かしているものの一端が見えてくるはずだ。
【書籍情報】
『砂漠の影絵』石井光太(光文社)
https://honto.jp/netstore/pd-book_28214009.html
『ヤズディの祈り』林典子(赤々舎)
https://honto.jp/netstore/pd-book_28264231.html
【プロフィール】
石井光太(いしいこうた)
1977年東京都世田谷区生まれ。作家。日本大学藝術学部文藝学科卒業。著書に『物乞う仏陀』『神の棄てた裸体』『絶対貧困』『レンタルチャイルド』『地を這う祈り』『ノンフィクション新世紀』『遺体』『津波の墓標』『浮浪児1945-』『「鬼畜」の家』など多数。
林典子(はやしのりこ)
1983年生まれ。国際政治学、紛争・平和構築学を専攻していた大学時代に西アフリカのガンビア共和国を訪れ、地元新聞社「The Point」紙で写真を撮り始める。「ニュースにならない人々の物語」を国内外で取材。英ロンドンのフォトエージェンシー「Panos Pictures」所属。