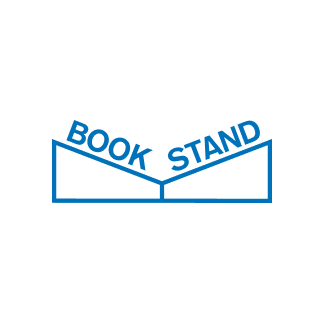2013年12月に「和食」がユネスコ無形文化遺産に登録され、和食の基本「だし」は世界に知られるようになりました。丁寧に取られた「だし」が素材の味を引き立て、「うま味」を引き出すのが和食の特徴。「だし」なくしては、和食は語れません。
そんな存在でありながら、「だし」は、あくまでも縁の下の力持ちであり、「効かせた方がおいしい」というのは間違った常識である¬¬¬---書籍『だしのいろは』著者の本田祥子さんはそう指摘します。
「あれもこれもと足してしまうとだしの濃度が濃くなりすぎて、食材の味がなくなり、うま味を感じられなくなってしまいます。食材にもうま味がありますので、食材に力があればだしはいりません。」「だしを使ったら、調味料は最小限しか使わない"引き算"が必要です。食材のうま味とだしとのバランスが料理の味を決めるためです」(本書より)
「だし」の味は、単純に1+1=2ではなく、植物性のうま味成分「グルタミン酸」と動物性のうま味成分「イノシン酸」は組合せることで、相乗効果でうま味が7~8倍になるとか......どうやら、「だし」の世界はなかなか奥深いようです。
ちなみに和食のだしに使われる代表的な素材には、「かつお節」、「昆布」、「煮干し」、「乾ししいたけ」の4種類があります。
「かつお節」はカツオを煮て燻し、乾燥させたもの。特殊なかび菌で水分を15%程度まで吸い出すことで、硬くなり、保存性が増して、同時にうま味成分が凝縮されます。かつお節の主なうま味成分は「イノシン酸」。動物性食品に多く含まれていますが、かつお節に含まれるイノシン酸は100g中600㎎で、食品の中でダントツです。
「昆布だし」は上品な味わいが特徴。植物性のうま味成分「グルタミン酸」は、味と味を結び付けて料理をおいしく仕上げるまとめ役としても秀逸です。昆布は採取される浜によってだしの味が異なるため、ワインと同じように産地で格付けされています。
小魚を煮て乾燥させたのが「煮干し」。「イノシン酸」を含み、安価で身近な天然のうま味食材として、一昔前の「おふくろの味」には欠かせないものでした。一般的にはイワシの稚魚が原料ですが、最近はトビウオを使った「あごだし」が人気を集めています。京都のおばんざい、大阪や香川のうどんなど、だし文化が発達してきた西日本では、料理は煮干しなしでは成り立たなかったのではないでしょうか。
最後は古代中国から伝わった「乾しいたけ」。9世紀ごろには日本に渡来しましたが、日本で自生したしいたけは、味や風味が良く、中国へ高値で輸出されたために、庶民にとっては縁遠い食材だったとか。その後、江戸時代に入り、庶民も盆や正月の「ハレの日」のご馳走に「乾しいたけ」を使えるようになりました。骨粗しょう症やがん、動脈硬化などの生活習病予防、アンチエイジング効果など「乾ししいたけ」には様々な効用があり、うま味成分「グルニア酸」は、「イノシン酸」、「グルタミン酸」と並ぶ、三大うま味成分の一つ。それらは、干すことで10倍にも増加するので、「乾しいたけ」には栄養とうま味が凝縮されていると言えます。
さて、そんな「だし文化」ですが、食のグローバル化に伴い、ある変化が見られるそうです。2015年4月には築地の和田久がスペインのガリシア州で鰹節の生産を開始。続いて今年9月にはフランス・ブルターニュ地方で鹿児島県枕崎市の水産加工業協同組合とかつお節関連会社9社が出資して「枕崎フランス鰹節」の工場が稼働を始めました。こうなると、ヨーロッパ産の「かつお節」を使った和食が、パリやローマの日本料理店ばかりでなく、欧州の一般家庭の食卓に並ぶ日もそう遠いことではなさそうです。