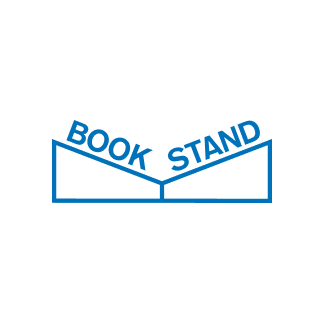今年2016年12月9日で没後100年を迎える文豪・夏目漱石。漱石と妻・鏡子を主人公に描いたドラマ『夏目漱石の妻』(NHK総合)をきっかけに、改めて関心を持たれ方も多いのではないでしょうか。
ドラマでは、尾野真千子さんが漱石の10歳下の妻・鏡子を生き生きと演じていましたが、漱石が自身の夫婦関係を投影したとされる小説『道草』からのイメージや、漱石の弟子たちが後世に伝えた評判から、世間ではすっかり"鏡子=悪妻"とのレッテルが貼られています。
しかし、漱石夫妻の長女・筆子を母に、漱石の弟子で作家・松岡譲を父に持ち、漱石の孫に当たる半藤末利子さんは、エッセイ『夏目家の福猫』で、以下のように異議を唱えています。
「世間ではソクラテスの妻と並び称されるほどの悪妻として通っているが、母に言わせれば、鏡子だからあの漱石とやっていけたのだと、むしろ褒めてあげたい位のことが沢山あったのだそうである」(同書より)
また、半藤さんの叔父で、漱石の長男・夏目純一氏も、当時を振り返り、こんな言葉を残しています。
「結局母は父のためにはいい奥さんではなかったかもしれないが父を心から愛し尊敬していたのだと思う。母を悪妻のようにいうのは当たらない。ぼくたちにしてみれば、母はごく普通の女だったと思う」(岩波文庫刊『漱石追想』収録の『父の周辺』より)
半藤さんによれば、お嬢様育ちの鏡子は宵っ張りの朝寝坊で料理が苦手、何かといえば占いや迷信に凝っていました。さらに漱石没後は印税を好き放題に浪費したのは事実であり、およそ"良妻"には程遠かったようです。一方、普段の漱石は人当たりがよく、弟子の前では温厚な人物で通っていましたが、気難し屋の一面もあり、神経衰弱の発作が爆発した際には、鏡子や子供達にまで暴力を振るうことも多かったのだとか。
そんな夫婦関係を、半藤さんはエッセイの中で、以下のように指摘しています。
「今ならドメステックバイオレンスと騒ぎ立てて訴えることも出来ようが、当の漱石にはその自覚がまったくないのだから医師の診断を仰がせることも叶わず、常軌を逸した漱石が振るう暴力に鏡子はひたすら耐えるしかなかった」(同書より)
半藤さんは、いわばDV夫の暴力に耐えるしかなかった鏡子が、藁をもつかむ思いで縋ったのが占いやお祓いの類であり、夫の死後に重荷から解放されたかのように贅沢三昧をしたのも無理からぬことではないか、と同情的に述べています。
とはいえ、漱石夫妻は2男5女、計7人の子宝に恵まれています。また、鏡子は、かの有名な"修善寺の大患"の際、漱石の500グラムもの大吐血で自分の着物が真っ赤に染まっても、たじろぐことなく気丈に看病したと伝わっており、世間の評判はさておき、2人の夫婦仲は極めて円満だったと言えるのではないでしょうか。
漱石の代表作『吾輩は猫である』のモデルになった猫についての逸話をまとめた『漱石夫人は占い好き』をはじめ、軽妙な語り口で漱石夫妻のエピソードを収録した同書は、100年前の文豪とその妻の息遣いを今に伝えるエッセイとなっています。