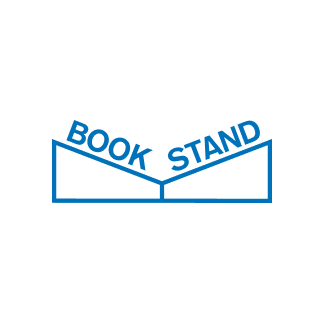作家の営みは、無から有を生み出すという創造であり、いわば生き物を造ることであるというのは、『聖ヨハネ病院にて』などの病妻物でも知られる小説家・上林暁。生き物であるがゆえ、机に向かったところですぐにペンが動きはじめるとは限らない----彼は以下のような言葉を残しています。
「〆切などといふ便宜的な設定を突き破つたり、それからはみ出したりするのは当然のことである。しかしそれを〆切内に引つ捕へねばならぬところに、作家の骨折があり、編集者の苦労がある。実際、〆切が迫つても捗の行かない時には、作家の頭はのぼせ上り、編集者の顔は歪むのである」
本書『〆切本』では、こうした〆切にまつわる作家たちの苦悩や葛藤について、作家自らが書き記した文章を掲載。明治から現在にいたるまで、90名にも及ぶ書き手たちの、さまざまなエピソードが伝わってきます。
たとえば、〆切が差し迫っているときに限って眠たくなるというのは、小説家・坂口安吾。
「仕事の〆切に間があって、まだ睡眠をとってもかまわぬという時に、かえって眠れない。ところが、忙しい時には、ねむい。多分に精神的な問題があろうけれども、どうしてもここ二三日徹夜しなければ雑誌社が困るという最後の瀬戸際へきて、ねむたさが目立って自覚されるのである」
普段はお酒がないと眠りにつくことが難しいにも関わらず、〆切に追われているときには一滴のお酒の力もかりずに眠れるのだといいます。
あるいは、〆切が差し迫り、切羽詰まって名作が生まれることも。川端康成の作品のなかでも評価を受けることの多い『禽獣』について、川端本人はこんなエピソードを綴っています。
「小説の締切が明日に迫り、夜中の十二時過ぎてもなんの腹案もなく、一番いやらしいことを書いてやれといふやけ気味で、翌日の正午過ぎまでに書きなぐつた」
ひとつの作品が生み出される際に巻き起こる、知られざるドラマの数々を本書から垣間みることができるはずです。