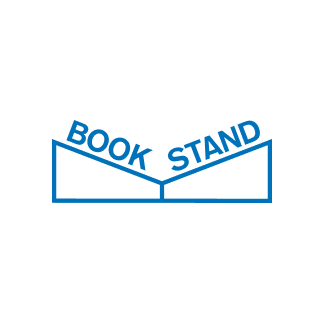「板倉さんが鍵盤を鳴らし、耳を澄まし、また鍵盤を鳴らす。一音、一音、音の性質を調べるように耳を澄まし、チューニングハンマーをまわす。
だんだん近づいてくる。何がかはわからない。心臓が高鳴る。何かとても大きなものが近づいてくる予感があった。
なだらかな山が見えてくる。生まれ育った家から見えていた景色だ。普段は意識することもなくそこにあって、特に目を留めることもない山。だけど、嵐の通り過ぎた朝などに、妙に鮮やかに映ることがあった。山だと思っていたものに、いろいろなものが含まれているのだと突然知らされた。土があり、木があり、水が流れ、草が生え、動物がいて、風が吹いて。(中略)ピアノって、こんな音を出すんだったっけ。葉っぱから木へ、木から森へ、山へ。今にも音色になって、音楽になっていく、その様子が目に見えるようだった」(本作より)
ピアノも弾けない、音感が特別いいわけでもない外村が、どのようにして森の匂いを立ち上げることのできる調律師へと育っていくのでしょうか。
「人にはひとりひとり生きる場所があるように、ピアノにも一台ずつふさわしい場所があるのだと思う」(本書より)
ピアノとピアノを巡る人びとの成長の物語。穏やかな暖かさに満ちた一冊です。