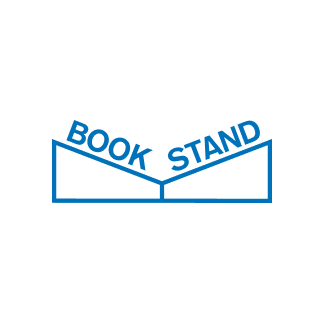好評のうちに最終回を迎えたドラマ『コウノドリ』。産婦人科医役の綾野剛さんをはじめとしたキャスティングの妙もありましたが、何と言ってもその魅力は、子どもが生まれる現場がいかにドラマティックであるかということを表していたから。同ドラマは、幸せな出産も、そうでない出産も、すべてが実際に起こりうるものであることを視聴者に教えてくれました。
写真家・繁延あづささんによる『うまれるものがたり』には、彼女自身が出産に立会い、撮影した家族が登場します。繁延さんは雑誌や広告の仕事の傍ら、ライフワークとして出産撮影を手がけ、それらにさまざまな形があることを実感。本来は依頼のあった家族のためだけの写真のため、公に出ることはないものですが、今回は6つの家族が登場し、その産前、出産、産後のようすを著者の写真と文章で綴っていきます。
立会い出産でビデオカメラをまわすお父さんもいるでしょうが、それとプロによる出産写真は別もの。「撮りながら考えること」として、繁延さん自身は次のように語ります。
「出産の現場というのは、妊婦さんが必死で痛みに耐えているときでもあり、肉体的にも精神的にも余裕がない。他人の私がいようが、もうとりつくろってはいられない。なりふり構わず、必死に痛みをこらえて産もうとする姿や、陣痛の合間にふと見せる笑顔、疲れ果てて意識が遠のいている様子、さらに気持ちの向けどころがなく、ご主人に怒りをぶつける様子さえも、私にはすべて必死に生きている姿に見える。その様子を見守る家族のもどかしさや、喜びや不安の様子からも、また必死さがうかがえる。"生きている"を感じる風景を目の前にして思うことは、"私も生きよう"ということだ。出産の最中の母子というのは、ある意味ともに危うい命でもある。生きていて当たり前のように感じられる日常の中で、"生きているのが当たり前ではない"と感じるとき、人は本能的に生きようと思うのかもしれない」(本書より)
そして、家族の中に入りこみながら第三者とはいいがたい、独特な立ち位置で特別な瞬間を切り取っていく繁延さんは、出産する妊婦だけでなく、父親や他の子どもたちなど家族の様子もとらえ、新しい命の誕生を家族がどんなふうに待っていたのか、どんなふうに受け入れたのかも記録していきます。
出産後、かわいいわが子を抱く母親の傍らで爆睡する父親。妹の誕生を喜んだあと、産後の母をいたわるように見つめる5歳の女の子など、笑みがこぼれたり、涙が出そうになったり、読者がそれぞれの出産にまつわるストーリーを感じることでしょう。
本の終わりには、死産を経験した家族の物語も。
誰もが自分が生まれたときのことに思いをはせるきっかけになると同時に、これから母になる方、すでに子どもがいる方、結婚前の若いカップルなど読む人の経験によって感じ方に大きな差がでる本かもしれません。しかし、どんな読み手にも、人はけっして一人で生まれてきたわけではないという当たり前のことを、改めて感じさせてくれる内容となっています。