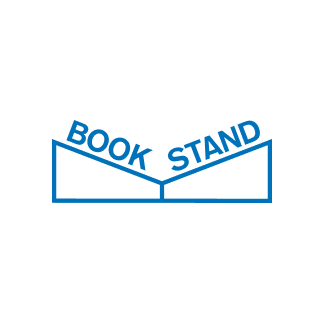12月に入り、忘年会をはじめ何かとお酒を飲む機会も増えてくる頃。しかし、長引く不況による所得の減少、そして収入の格差拡大は、非飲酒率を上昇させ、酒文化を衰退させつつあるといいます。
書籍『居酒屋の戦後史』において、「人々がどんな酒を飲むか、どんなとき、どんな場所で酒を飲むか。そして人々が集まる居酒屋の姿。これらは時代によって変わり、その時代の社会のあり方を、色濃く反映する」と語るのは、著者の橋本健二さん。
本書では、戦後のヤミ市からビヤホールの登場、チェーン居酒屋の勃興と、お酒と居酒屋の変遷を辿ることにより、戦後の日本社会の歩みをとらえていきます。
戦後70年、酒文化はいかなる歴史を歩んできたのでしょうか。戦中から戦後間もない時期には、多くの人にとって貴重品だったお酒。食料さえままならぬ時代、ヤミ市には安価な芋や麦などの糖質を発酵させて造ったカストリ、燃料用アルコールを水で薄めたバクダンと呼ばれる密造酒を出す飲み屋が無数に立ち並んでいたそう。
バクダンにはメチルアルコール入りのものがあり、死者や失明者が続出したのに対し、カストリは鼻につく匂いはあるものの、中毒の心配がないため、新聞社や出版社が集まっていた有楽町界隈には、酒好きの多い作家や記者、編集者などの集まるカストリの屋台が林立していたそうです。
そして織田作之助や石川淳、山田風太郎をはじめとする文学者たちは、こうしたヤミ市の飲み屋街を題材とする作品を残していますが、坂口安吾もそのひとり。自らもカストリを愛飲していたといいます。
安吾は執筆中、ヒロポンと呼ばれる覚醒剤を常用し、5日間ほどは眠らずに作品を書き上げるため、書き終えたときにはカストリを飲むことで酔いを導き、眠りについていたそうです。
あるいは"原稿料の代わりに酒をよこせ"と言ったのは内田百閒。大のお酒好きである百閒、大空襲により麹町にあった自宅を焼け出され、避難するとき手に持っていたのは、なんと飲み残しの日本酒の瓶。大空襲のなか、酒をちびちび飲みながら逃げ回ったのだといいます。
当時の日記には、次のような記述があるのだそうです。
「昨夜気分進まず飲み残した一合の酒を一升瓶のまま持ち廻った。これ丈はいくら手がふさがっていても捨てて行くわけに行かない。逃げ廻る途中苦しくなるとポケットに入れて来たコップに家内についで貰って一ぱい飲んだ。土手の道ばたへ行ってからも時時飲み、朝明るくなってからその小さなコップに一ぱい半飲んでお仕舞いになった。昨夜は余りうまくなかったが残りの一合はこんなにうまい酒は無いと思った」(本書より)
戦後に比べ、質も格段に向上し、多くの種類のお酒も次々に生まれ、世界にも通用するようになったにも関わらず、なぜここにきて酒文化は衰退しつつあるのか。歴史を振り返りながら、さまざまなデータとフィールドワークをもとに解き明かされていきます。